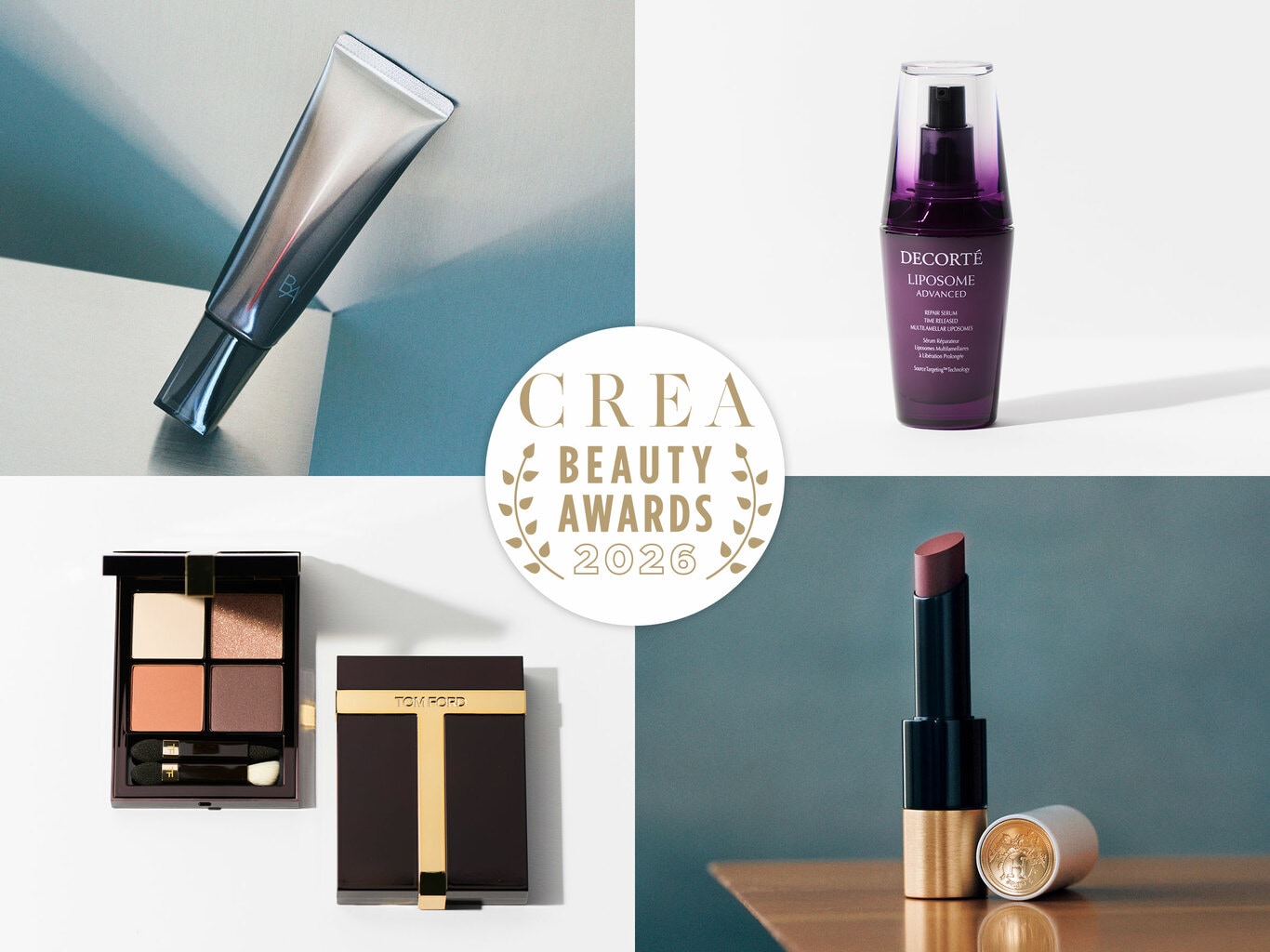しかし見どころは終盤だけではない。繰り返すが、過去の「銃弾」のエピソード集は、銃撃戦を交えつつも、実にエモーショナルで、詩的で、ときに象徴的ですらある。鮮烈な場面の連続といっていい。過去の秘密を明らかにする場面なので曖昧に書くけれど、ホーリーとリリーのキスの深遠さと愛しい傷をめぐる会話も(「銃弾#5」)、ギャングの妻が語る花のような骨の模様に神様を信じる話も(「銃弾#7、#8、#9」)、リリーが失われていくことを一つ一つ確かめる場面も(同)、ホーリーが死の淵へと誘い込まれる場面も(「銃弾#11」)、何と心に響く名場面だろうか。「銃弾#3」に出てくる片目が濁ったギャングの妻が語る手紙やウェディングドレスの話ですら、愛の神々しさを伝えてはっとするほどだ。醜悪で汚らしいものからでさえ、ハンナ・ティンティは、一滴の美と愛をつかみとる。至るところから、人生の詩を汲み上げて僕らの心をふるわせるのである。
「銃弾#2」がそうであるように、一つひとつが独立して読めるけれど、クライム・サスペンスのなかにホーリーとリリーとの恋愛小説、ルーを交えての家族小説、さらに成長をたどる青春小説の輝きが重なり合い、小説としての厚みをもつことになる。
『ザリガニの鳴くところ』では、湿地の自然や動物たちが鮮やかな風景の中で象徴的に捉えられていたが、本書では重要な場面で鯨が登場して、生命の危機と再生、あるいは孤高の生き方の美しさを見せつけて、きわめて印象深い。ギャングたちの銃撃戦ですら名場面に昇華され(グラフィカルな活劇と独特の表現による負傷の感覚など)、ときに荘厳な響きをもち、読者の胸を激しくうつ。「まるで交響楽のような驚嘆すべき一冊」(ニューヨーク・タイムズ)という賛辞は決して誇張ではない。いつまでも心に残る作品であり、おりにふれて読み返したくなる作品なのではないか。
最後に本書刊行時の情報も書いておこう。本書は、二〇一八年のアメリカ探偵作家クラブ賞(エドガー賞)最優秀長篇賞にノミネートされたものの受賞には至らなかった。受賞作はアッティカ・ロック『ブルーバード、ブルーバード』だが、はるかに本書のほうが優れている。日本では二〇二一年に翻訳刊行され、「このミステリーがすごい!」と「ミステリが読みたい」で第四位、「週刊文春ミステリーベスト10」では第五位に入ったけれど、さまざまなジャンルをもつ物語の面白さ、端役の一人一人までめざましいキャラクターの鮮やかさ、そして硬質な文体の質の高さからいっても、第一位にふさわしい。それほどの傑作である。
文=池上 冬樹(文芸評論家)