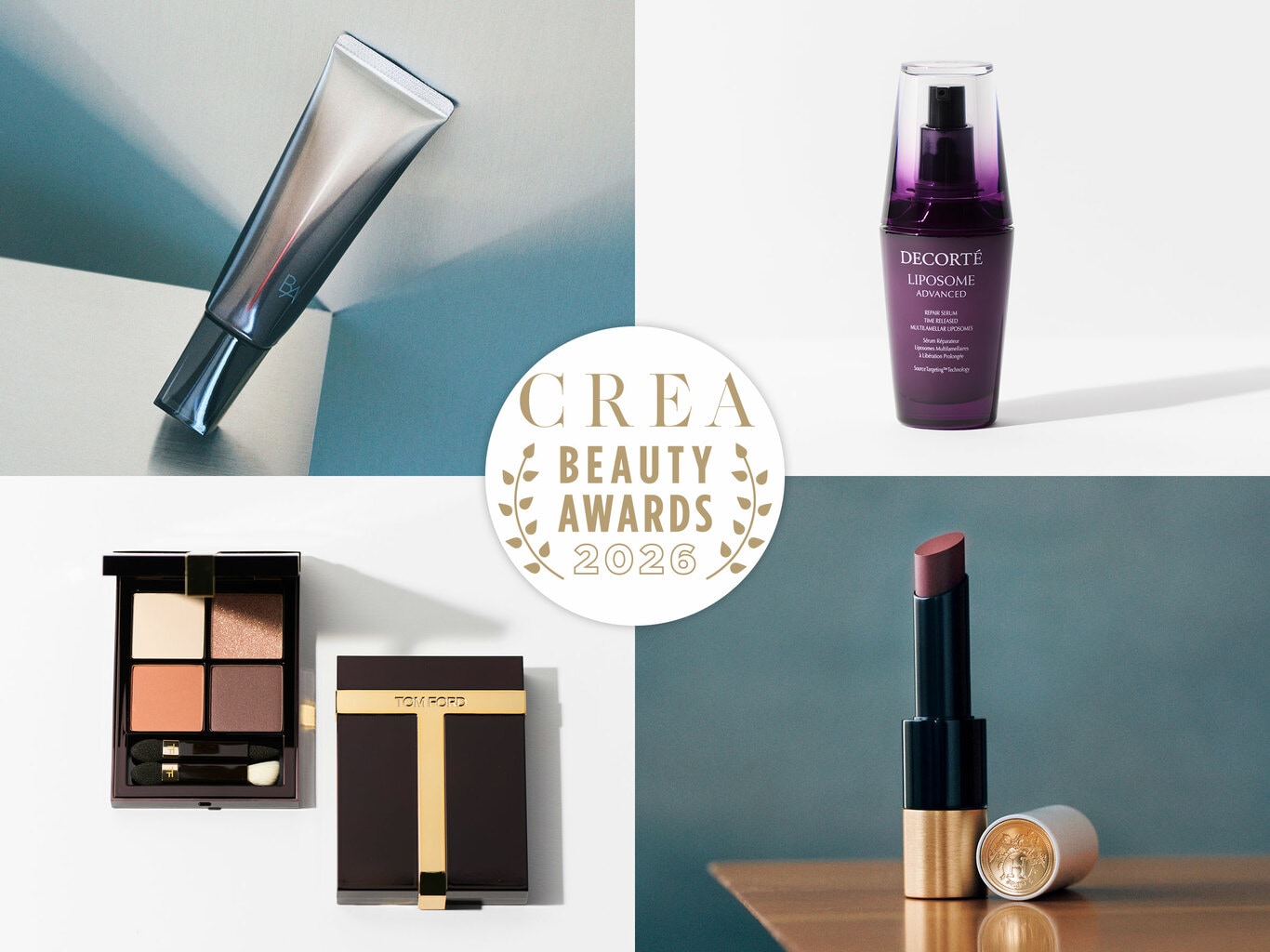幼子を手にかけた死刑囚の最期の言葉
「我が子を含む幼い命を奪った犯人への“一体なぜ、どうして?”という恐怖にも似た強い疑問が出発点でした」
幼児二人が亡くなり、被害者の母親が逮捕された事件がかつて実際にあった。何年経っても消えない“なぜ?”を、主人公と共に突き詰めるようにして書かれたのが本作だ。
「デビュー直後から書こうと思っていた題材でしたが、まだ手に余ると躊躇していました。作家として10年を過ぎた今ならばと取り組みましたが、何度も挫折しそうになって。こんなに苦しかったのは初めてかもしれません」
埼玉で暮らす32歳の香純は、東京拘置所から突然の電話を受け、死刑執行された遠戚・響子の遺骨を受け取りに行く。香純にとって響子は母の従姪――互いの祖父が兄弟という続柄に過ぎないが、母の故郷・青森で一度だけ邂逅した姿を忘れられなかった。我が子ともう一人の幼女を殺害した死刑囚と、儚げに微笑んでいた制服の少女が結び付かないのだ。刑の立会人から「約束は守ったよ、褒めて」という最期の言葉を聞いた香純は、誰と何を約束したのかを調べに北へ向かう。
「こういう事件では、私も含め多くの人が『分からない』と理解を放棄すると思います。自分とは違う、と切り離すことで安心したいんです。でも、香純が謎を追う過程を書きながら、本当にそうだろうかと思うようになりました。少し運命がずれれば、誰にでも起こり得ることなのでは、と」
山端に日が隠れるため暮れの早い北の町。橋から見下ろす川の流れ、しんしんと冷える空気、他所者を警戒し、代々のしがらみが残る狭い人間関係。寂しい情景と、段々と明かされる響子の寄る辺ない境遇が重なり、何もかもを失った彼女が、それでも守ろうとした約束の真相に引き付けられる。
「響子がした事は決して許されません。それは揺るがない一方で、響子という人間が絶対悪であるわけでもない。香純が響子に迫れば迫るほど、最初は“悪”一色に見えたものが渾然としたマーブルになっていく。ラストシーンだけは決めていたものの、どういう道筋で至るのか、執筆中ずっと手探りでした。分からないまま進むのは不安でしたし、書き終えた今でも明確な答はないように思います。でも、それでいいんでしょうね……。
一つの答に辿り着いたと思った先にまだ別の面があるのが人間。『分かった』気になるのは、身勝手なことでもありますから。私は作家として“事実と真実は違う”ということをテーマにしてきました。その隙間にあるものを、これからも書いていくのだと思います」
ゆづきゆうこ 1968年岩手県生まれ。2013年『検事の本懐』で大藪春彦賞、16年『孤狼の血』で日本推理作家協会賞を受賞。著書に『ミカエルの鼓動』など。
文=「オール讀物」編集部