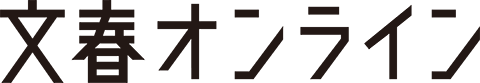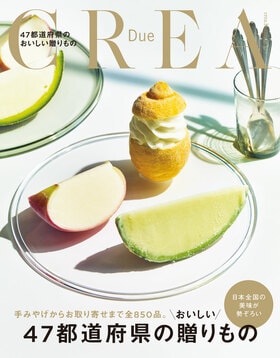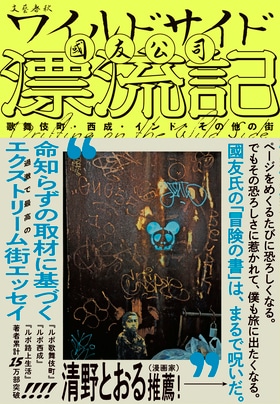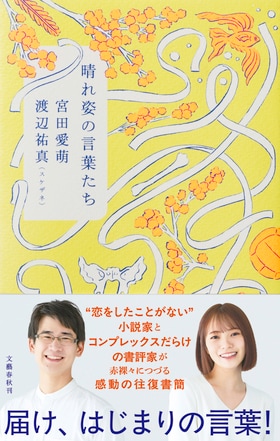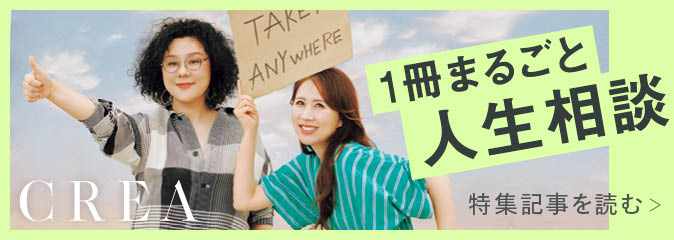注2 録音した音声を、音楽の素材として活用すること。機材が低価格化した90年代以後にはごく一般的な手法となった。
注3 「ゴーゴー幽霊船」の「あんまり急に笑うので」などもその範疇の内である。
注4 80年代、ラップが「うた」になったことは革命であり階級闘争でもあった。調性内的な「うた」を操るんいは教育が要り、格差がそれぞ阻む。ラップはその参入障壁を破壊した。
たとえば大和田俊之『アメリカ音楽史』(講談社選書メチエ、2011年)はラップを「うた」ではなく「語り」だとしているし、解釈依存的な部分もある。しかしどちらにせよ、ラップはずいぶん以前から大衆音楽である。1994年時点で、ニューヨーク・タイムズ紙の「How pop music lost the melody」という記事はラッパーのスヌープ・ドッグを論じている。
注5 ボカロの声に慣れない上世代の人にとっては、いまだボカロの声もそうであるということを指摘しておく。
「結局どれが真正のミクちゃんなの?」現役ボカロPが語る、初音ミクの“キャラクターとしての特異性” へ続く
2022.07.19(火)
文=鮎川ぱて