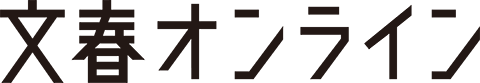細かい手仕事が得意な日本の民は、古くからよくできた郷土玩具をつくってきた。福島県の《三春人形 橘弁慶》や埼玉県の《鴻巣人形 女に松梅》は、その格好の例だ。


陶器・陶磁器も各地で味わいの異なるものが産出されてきた。愛知県でつくられた《鉄絵菊に蝶文行灯皿》は、さらりと描かれた絵柄にたしかな職人技が感じられる。

朝鮮半島産の見事な陶磁も、3点が並んで展示してある。柳の尽力で1922年にソウルで開かれた李朝陶磁器展覧会に出品されたものが、百年の時を超えてまた一堂に会したのだ。いずれの器も、薄い肌合いと淡い彩色が美しい。

戦後になって柳が盛んに蒐集した丹波の《自然釉甕》には、人知を超えた造形の迫力がある。やきもの文化の地域ごとの多彩さには驚かされる。

地域の特色が強く出たものとしては、雪深い青森の地で使われた《蓑(伊達げら)》がある。最先端のファッションショーに出ていてもおかしくないほどスタイリッシュではないか。

柳は、新しい民藝的実用品の考案にも積極的だった。彼がデザインを考案した《本立》は、いまも多くの人が使いたくなるような普遍的デザインにまとまっている。

他にも会場では、民藝の現状と活動を一枚にまとめた巨大な《日本民藝地図(現在之日本民藝)》や、柳宗悦が書斎で愛用した机と椅子、彼が1931年に創刊した布表紙の雑誌『工藝』なども実地に見られる。

民藝の名のもとに集められたモノの数々はどれも決して華美ではないが、「なるほどこれは、こうでしかあり得ない」と思わせるユニークかつ美しい形と色をしている。「用の美」とはまさにこのことかと感じ入る。
これら民藝の考え方や思想を体現するモノが、なぜいまを生きる私たちにもこれほど沁みるのだろう。不思議に感じたが、思えば事情や状況はよく似ているのだ。柳らが民藝に思い至った1920年代には、明治維新以来の近代化の進展で、昔ながらの道具や生活習慣が日常から消えつつあったという。
そのことを憂えた柳らは、古くから伝わるモノに美しさを見出し、光を当てた。各地の風土や人の暮らしぶりが反映されたモノこそすばらしいと強く訴え、そこからよりよい生活とは何かを追求していったのだった。
展示を観終えると、柳宗悦とその仲間たちにきっと強い共感を覚えることになる展示だ。
2021.11.21(日)
文=山内宏泰