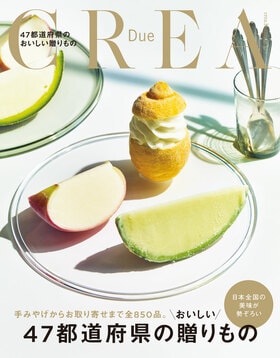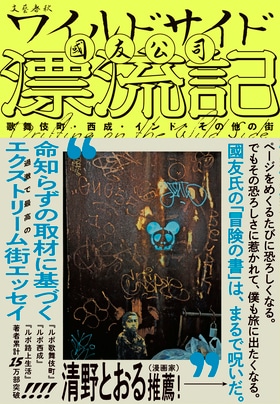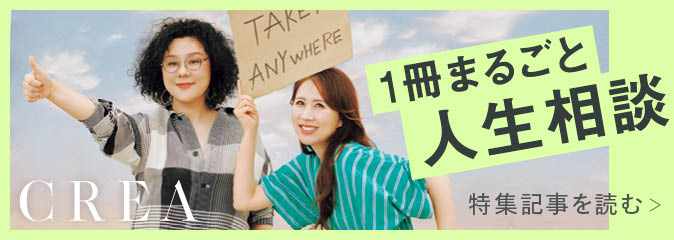「気風がよくてべらんめえ」という江戸っ子像ができたのは蔦重の時代
日常的に地口を使っていた江戸っ子の、「気風がよくてべらんめえ、宵越しの金をもたねえ」というテンプレートは、蔦重の時代にできあがった。
徳川家康の江戸開府から150年以上、3代にわたって江戸で生まれ育った人たちの心意気は「粋と通」に代表される。反対に「無粋や野暮」はサイテー扱いだ。
当時の江戸は人口100万人を超え、京や大坂どころかロンドンやパリをも凌駕する大都市だった。もちろん日の本の政治、経済の中心地でもある。それでも江戸っ子の常套句は「地口」といわれたし、蔦重が扱う黄表紙や細見、遊女名鑑などは「地本」、酒だって「地酒」、女房や娘たちまで「地女」と呼ばれていた。
「地」には田舎のニュアンスが色濃く、上方からみた江戸への蔑視が込められている。
しかし蔦重の時代には、そういった京・大坂至上主義に翳りがみえ始める。上方から「下ってくるもの」が上質&上等で、江戸の産物はバッタ物、つまり「下らない物」という価値判断が通用しなくなっていく。
江戸の産物は格段にレベルアップ、江戸っ子のプライドも高くなってきた。地本が愛されたのも当然の成り行き――蔦重はそんな機運に乗じて江戸っ子を魅了する。吉原から日本橋へ、江戸でいっち(一番)の本屋へのし上がっていくのだ。

「百川」は日本橋の高級料亭で、江戸のセレブが集う名店
「べらぼう」の展開はめまぐるしい。コミックさながら、次々にシーンが変わっていく。そこに新しい大河ドラマへの意気込みが感じられる。
でも、展開の早さゆえに、伏線を張りながら回収しきれていないところ、解説不足な点もチラホラ見受けられるのはもったいない。初回で廓の顔役たちが宴席をはったシーン、その食膳にのぼった「百川」は好例。
意味ありげに写されたひょうたん型のトレードマーク。これに関しては何の説明もなされなかった。
百川は日本橋にあった高級料亭で江戸のセレブたちがこぞって足を運んだ名店だ。同名の落語になっているし、蔦重と深い関係の大田南畝も贔屓にしていた。
南畝といえば、黄表紙と共に天明期(1781~89)のトレンドとなった狂歌の頭領格。
蔦重は南畝を取り込むことで狂歌師たちを掌握、天明文壇というべき文芸サロンのパトロンに収まる。で、南畝と有名料亭の関係だが――彼は「山手連」なる狂歌のグループを率い、毎月のように百川で狂歌の会を催していた。宴席には蔦重だって何度も顔を出したことだろう。
2025.02.05(水)
文=増田晶文