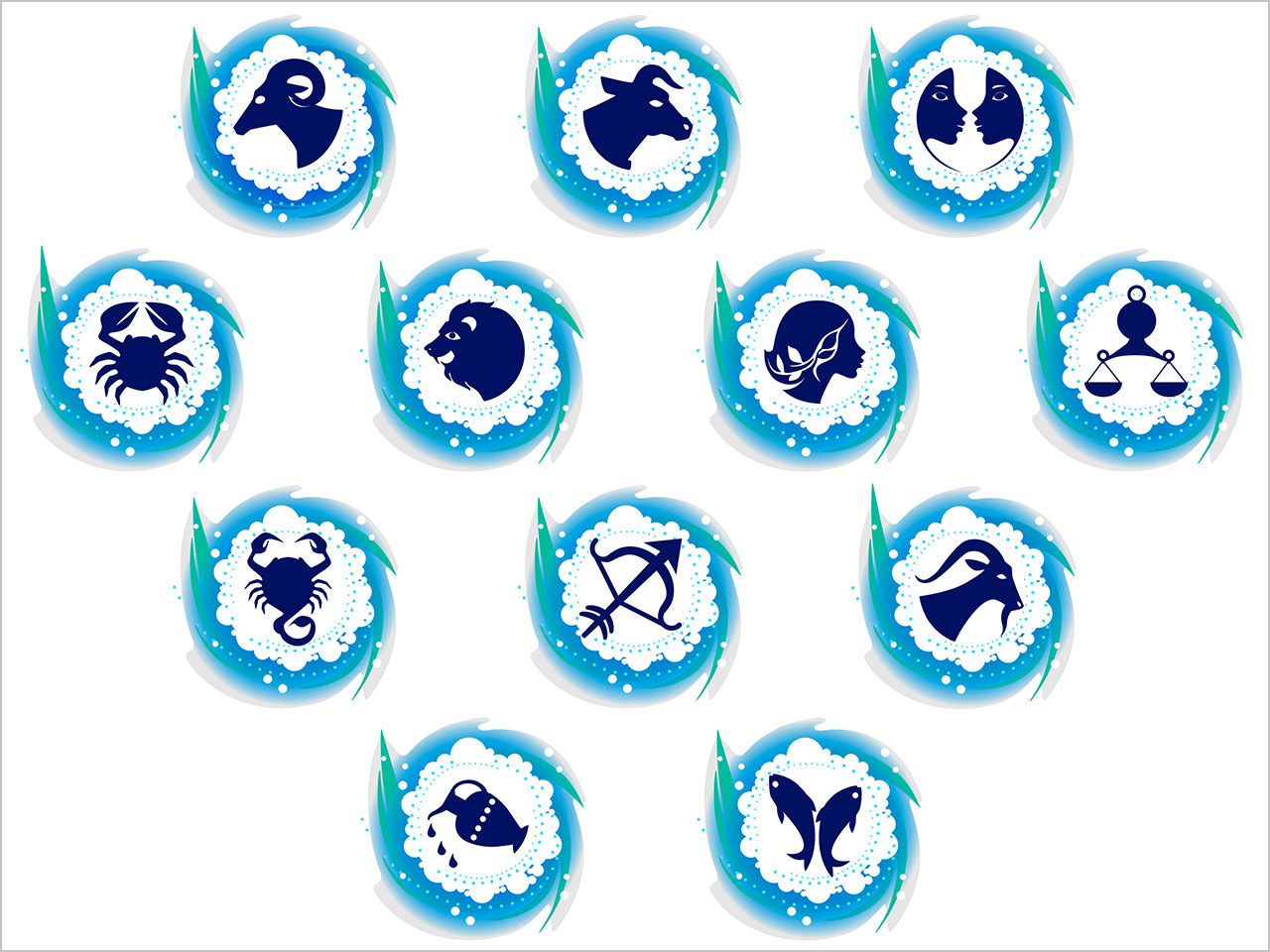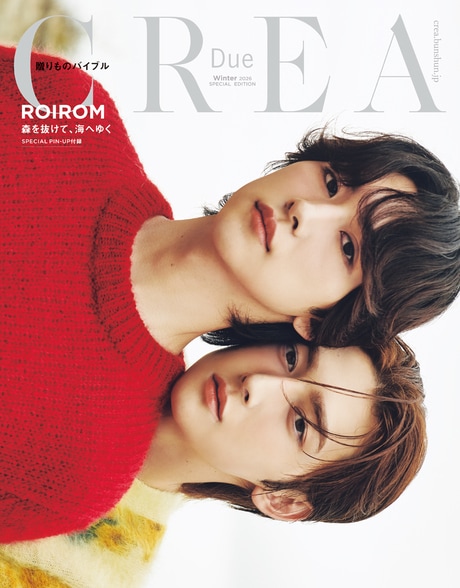田中が去ったあと武藤は、「アイツ[田中]との調整で精魂が尽きる。これでは何んにも出来ない」と漏らしている(同上)。二人の対立はそれほど激しかったのである。
対米開戦論の田中と慎重論の武藤との対立の原因と詳細については後述するが、田中の対米強硬論は陸軍内でも際立っており、強い影響力をもっていたのである。
後世の目で見ると、国力において格段の差があったアメリカとの戦争はいかにも無謀で非合理に思える。もちろんアメリカとの国力差は、田中をふくめ開戦時の指導者たちも認識しており、武藤のように、できうる限り対米戦を避けたいと考えるものは少なくなかった。彼らの懸念は一九四五年(昭和二〇年)の敗戦で現実となる。
太平洋戦争開戦に関わった軍人としては、東条英機や武藤章などがよく知られているが、田中こそ、開戦を最も強硬に主張し、陸軍を動かしていった人物だったのである。
では、なぜ田中は対米戦を強硬に主張したのか。本書の目的の一つは、その論理を確かめることにある。
田中は開戦前後のキーパーソンの一人であり、また当事者としての貴重な資料を多く残している。にもかかわらず、これまで田中の本格的評伝は書かれていない。
東京裁判において、慎重論の武藤はA級戦犯として死刑となり、開戦論の田中は戦犯指定を受けなかった。武藤と田中の運命の交錯も、陸軍と先の戦争を考えるうえで興味深いものがある。
まず、日米開戦前、独ソ戦直前の田中の議論をみてみよう。
一九四一年(昭和一六年)四月一六日、大島浩駐独大使から、ドイツが対英戦を行いながら、並行して対ソ開戦を企図しているとの極秘情報がもたらされた。日ソ中立条約締結の三日後である。
その後、五月一三日、坂西一良ドイツ駐在陸軍武官からも、「独ソ開戦必至」を知らせる電報が届いた。
四月二三日頃、大島大使からの情報を知らされた参謀本部作戦部長の田中は、次のように考えていた。
独ソ開戦の可能性が強くなり、いずれ日本は三国同盟と日ソ中立条約との「矛盾」に直面することになる。いったんは三国同盟と日ソ中立条約の連動によって、対米牽制の効果をもちえた。だが、今や独ソ関係が危機的状況にあり、三国同盟と日ソ中立条約の連鎖は「内部崩壊」の状況にある。それゆえ対米牽制効果はもはや期待できない。また中国重慶政府に対する効果もほとんど認められない。
- date
- writer
- category