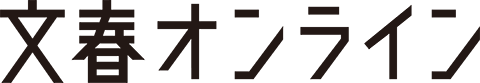コロナ禍が変えてしまった人間関係
安岡事務局長も「LINEスタンプなどを張りつけて送信すれば簡単に謝れてしまいますからね」と話す。
私は「ChatGPTなどの生成AIに謝罪文を作成させ、そのまま張りつけてメールしたあとは知らんぷりの若手社員がいた」と憤慨するベテランに話を聞いたことがある。そうなれば、もはや「言いそびれた『ごめんなさい』」などとは無縁な世界だ。謝罪は気持ちのやりとりではなく、機械を介した通知になる。
そうした風潮も背景にあるのだろうか、徳久さんは「人間関係の変化」が応募に影響を与えているのではないかと考えている。最終的な引き金を引いたのは新型コロナウイルス感染症だ。
「感染防止のために他人と接触しないようにしようという社会運動が起きました。他人と深く関わらない生活に慣れてしまうと、もうこれでいいんだと思うようになります」

こうした傾向は以前から進んでいた。
「高校生の中にはスマホ中毒でないかというほど、スマホばかり見ている子もいます」と徳久さんは語る。結婚もマッチングアプリに頼る人が増え、人工知能(AI)が仲介してくれる。
人との関わりが薄れれば、「ごめんなさい」を言わなければならないような行為そのものが少なくなる。
地域社会や他人とどうつながっていくのか
徳久さんは、略称「ふてほど」が流行語大賞になったTBSドラマ『不適切にもほどがある!』を観る機会があった。令和と昭和が対比された物語だった。
「別に昭和がいいというわけではないのですけど、何か人間臭いものがありました。どろどろした人間関係も含めてです。それが一つのパワーになっていた時代でした」。人間臭さの喪失が、「ごめんなさい」の減少につながっているのだろうか。
ハガキの値上げや、ハガキ離れ、伝達手段のデジタル化に加えて、人間関係の希薄化と機械への依存。
応募ハガキの激減は、これら多くの変化が重なって、一気に表面化したのかもしれない。そうした面では、コンクールの苦境は日本社会の曲がり角を象徴する一つの現象とも言える。
「ただし、人間は一人では生きていけません。地域社会や他人とどうつながっていくか。皆で真剣に考えていく時期に差しかかっているのではないでしょうか」と徳久さんは訴える。
「コンクールではやなせ先生の提案通りに『言いそびれたごめんなさい』を募集してきました。しかし今回、改めて『ごめんなさい』が持つ意味について、ごめん町の皆で考えたいと思います。『だからこそ、このコンクールは今の社会に必要なんだ』という共通意識を持って発信していきたい」と力を込める。
「ごめんの町」で「ごめんなさい」を言う。
だじゃれで始まった催しが、日本社会に重い問いを発する。

2025.01.01(水)
文=葉上 太郎