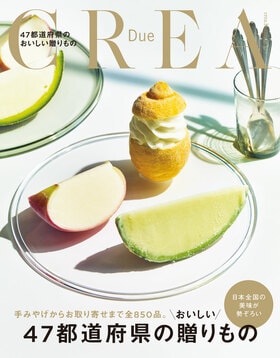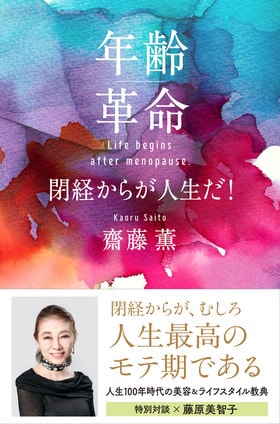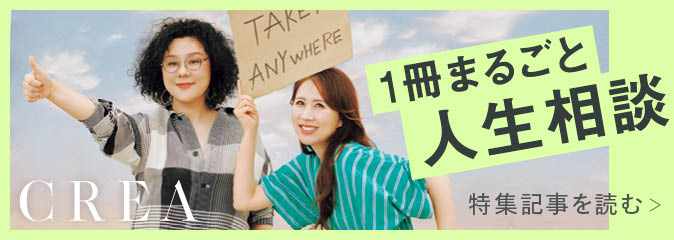「モン・パパ」の音声はリバーブがかからなくなり、あたかも寅子の脳内に直接この歌が流れているかのような感覚となる。それが記者の「さすが、日本で一番優秀なご婦人方だ」という台詞で突然にカットアウトされる。
寅子はこの歌を怒りながら歌う。その怒りは、自分だけではなく、志半ばで去らねばならなかった女たちがこうむった理不尽に対する怒りであり、いまだ解消されない女性の構造的排除に対する怒りだ。それにしてもこのコミカルな歌は、怒りを表現するにはいかにもふさわしくないように思えるかもしれない。
シリーズもまだ先の長い現在、これは推測でしかないが、この歌はジェンダー秩序がひっくり返ったユートピアを歌っているようにも見えつつ、実のところ先述の「温情的な父権主義」の歌でもあるのではないだろうか。
最初の結婚式の場面に表現されるように、この歌は男性たちに大いにウケている。披露宴で酔っ払って歌い踊るのは男性たちだけであり、女性たちは「スン」っとしている。コミカルな歌の中では「女性が強い」ことを歌いつつ、現実には男性優位の社会は保存する──この構図は、ドラマ、映画、アニメのようなフィクションの中では女性が活躍しつつ、現実には男性の優位が確保されるという構図に似ていないか。
または、「多様性の時代なのでこんなことを言うと怒られますが」といった言葉を枕にしたお偉いさん(もちろんおじさん)のスピーチに似ていないか。
寅子の「はて?」は男性社会だけでなく、それを追認する女たちへも向けられている
ロシアの批評家ミハイル・バフチンは「カーニバル的なもの」という概念を提唱した。ある種の文学の中で、カーニバル(祝祭)的に日常的な価値観が転倒されることである。このカーニバル的なものは、日常の価値観を転倒させつつ、じつは(祭りの時だけ転倒させることで)日常の権力関係を保存していると見ることもできる。「モン・パパ」にはそのような、カーニバル的なものの二面性がある。
2024.05.27(月)
文=河野真太郎