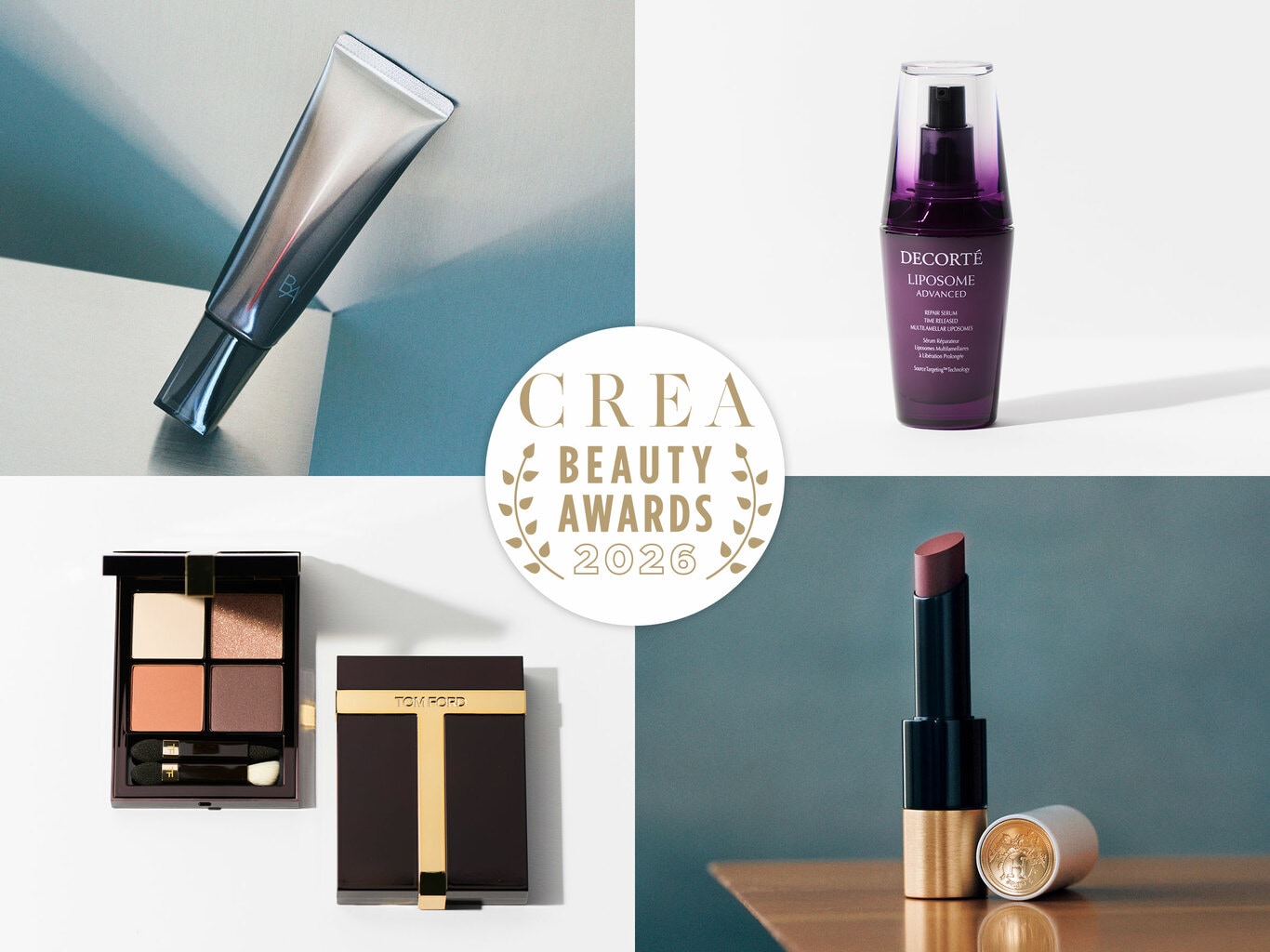吉村昭氏の小説は常に、静かな声で語られる。戦争をテーマとする作品では、ときに無残な死が描かれるが、非日常の異様な状況や心理に迫るときも、決して声高になることはない。
あいまいなこと、大げさなこと、主情的なことを拒む吉村氏の文章の背後には、徹底した取材と調査にもとづく事実の探求がある。
吉村氏の取材の広さと深さ、とりわけ当事者に直接会って話を聞くことを重視する姿勢は、つとに知られるところである。それは、小説にリアリティを持たせるエピソードを拾う、というのとは根本的に違う。
当事者の談話を貴重な歴史の証言として受け止め、しかしすべてを鵜呑みにするのではなく、突き合せ、裏付けを取り、あらゆる角度から検討する。そこから作品を生み出すのが吉村氏のやり方なのである。
吉村氏はこう述べている。
〈記録は、人体にたとえれば骨格に似ている。それに肉をつけ血を通わせるのは、生存者の肉声しかない〉(『万年筆の旅 作家のノートII』所収「眩い空と肉声」より)
私はノンフィクションを仕事にしており、戦争を題材にしたものもいくつか書いている。若い頃から吉村氏の作品を愛読していたが、この職業についたあとで改めて読むと、数行の記述であっても、その背後にどれだけの調査と取材があったかが推測できて、いつも圧倒される思いがする。
では、吉村氏の取材スタイルはどのようなものだったのか。随筆「一人で歩く」(『わたしの普段着』所収)で氏は、他人に調査を依頼することはせず、必ず自分自身で出かけていくと書いている。
吉村氏の担当編集者だったことがある作家の森史朗氏によれば、費用も原則、自弁だったそうだ(吉村昭記念文学館企画展図録『戦後75年 戦史の証言者たち――吉村昭が記録した戦争体験者の声』所収「吉村昭と戦史小説」より)。そして、取材にはいつもテープレコーダーを持参した。吉村氏の子息である吉村司氏はこう書いている。
〈母(筆者註・夫人で作家の津村節子氏)は録音機を基本回さない。自分の作品に有効となる情報はメモをすることで足りる、というのが持論だ。しかし、父の場合、取材帰宅後にテープを再生してみると、証言者達の感情の起伏や、微妙な表現はメモでは書き留めることが出来ないと強く自覚していた〉(同前「父と戦艦武蔵」より)
文=梯 久美子(ノンフィクション作家)