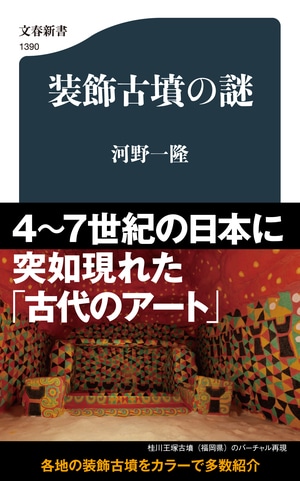
今、古墳時代が熱い。古墳女子に墳活、古墳フェスに古墳フードなど、考古学の研究を始めた私の学生時代には思いもよらなかった大ブームが到来中だ。有難いことに、本書のテーマである装飾古墳も「古代のアート」として各所でワークショップがしきりに開催され、描かれた様々な文様をアレンジしたグッズが販売されている。しかし、装飾古墳は、いつでも好きな時に見られるものではなく、気候が落ち着いた春や秋のみに見学時間も限られるケースが大半だ。したがって、脚光を浴びている割に実際に見た人はあまりいない。
装飾古墳の魅力とは何だろう? 私自身の経験でお許しいただければ、高校時代にさかのぼる。考古学ボーイ(大学で考古学を専攻する前から考古学が好きな少年)だった私は、家の近くに装飾古墳があることを知り、遺跡地図を片手に藪をかき分けながら探し回った。しかし、現地に到着しても夢にまで見た古代の芸術には出会えなかった。石室の入口は土嚢で固く閉ざされ、落胆して帰途に就くほかはなかった。しかし、ちょっと遠くまで足をのばせば装飾古墳を見ることができた。有名な特別史跡の福岡県桂川王塚古墳は、当時閉鎖されていたが、筑後川中流域には日岡古墳、珍敷塚古墳など国史跡に指定された有名な装飾古墳があった。高校生からの依頼は珍しかったのか、町の文化財担当の方は、車に乗せて懇切丁寧に装飾古墳を説明してくれた。もっとも、当時の私がそれを十分に理解できたとは思えないけれど、初めて装飾古墳をこの目で見た興奮と感激は今でも忘れられない。
漆黒の闇を照らす懐中電灯の光に浮かび上がる、黒や赤の線。次第に目が慣れてくるとそれらが、人物や動物、幾何学文などの像を結ぶようになる。そして、絵解きのように装飾全体が一斉に語り始めると、1000年の時を経て古墳時代の芸術家と向き合っているという感覚に満たされる。まさに、装飾古墳とは古代からのメッセージなのだ。
しかし、不幸なことに装飾古墳は、はじめから日本美術史の巻頭を飾る存在として評価されてきたものではなかった。文明開化を旗印に体系化された日本美術史は仏教美術から始まり、古墳時代以前のような先史・原史文化は埒外であった。今でこそ、縄文土器や土偶は、特別展を開催すれば、多数の来場者を数えるようになった。しかし、岡本太郎が縄文土器の美しさを再発見するまでは、美術と見なされなかった。装飾古墳も同様である。そのため、昭和39年(1964)に『太陽』で装飾古墳特集が組まれ、国民にその美が知られるまで古墳は荒れ放題のまま、多くの文様や古墳が人知れず消えていった。さらに、装飾古墳の分布が九州北部および中部と関東や東北南部に偏っており、古墳時代の中枢であった近畿地方中部に少なかったことも災いしている。後に畿内と呼ばれるこの地域を対象に研究が進められてきた考古学の世界では、装飾古墳はローカルな古墳文化に位置づけられた。逆に、飛鳥の高松塚古墳、キトラ古墳など壁画古墳のセンセーショナルな発見以降になると、装飾古墳は奈良県の飛鳥にしか無いという誤った認識も一般には広がった。
文=河野 一隆



























