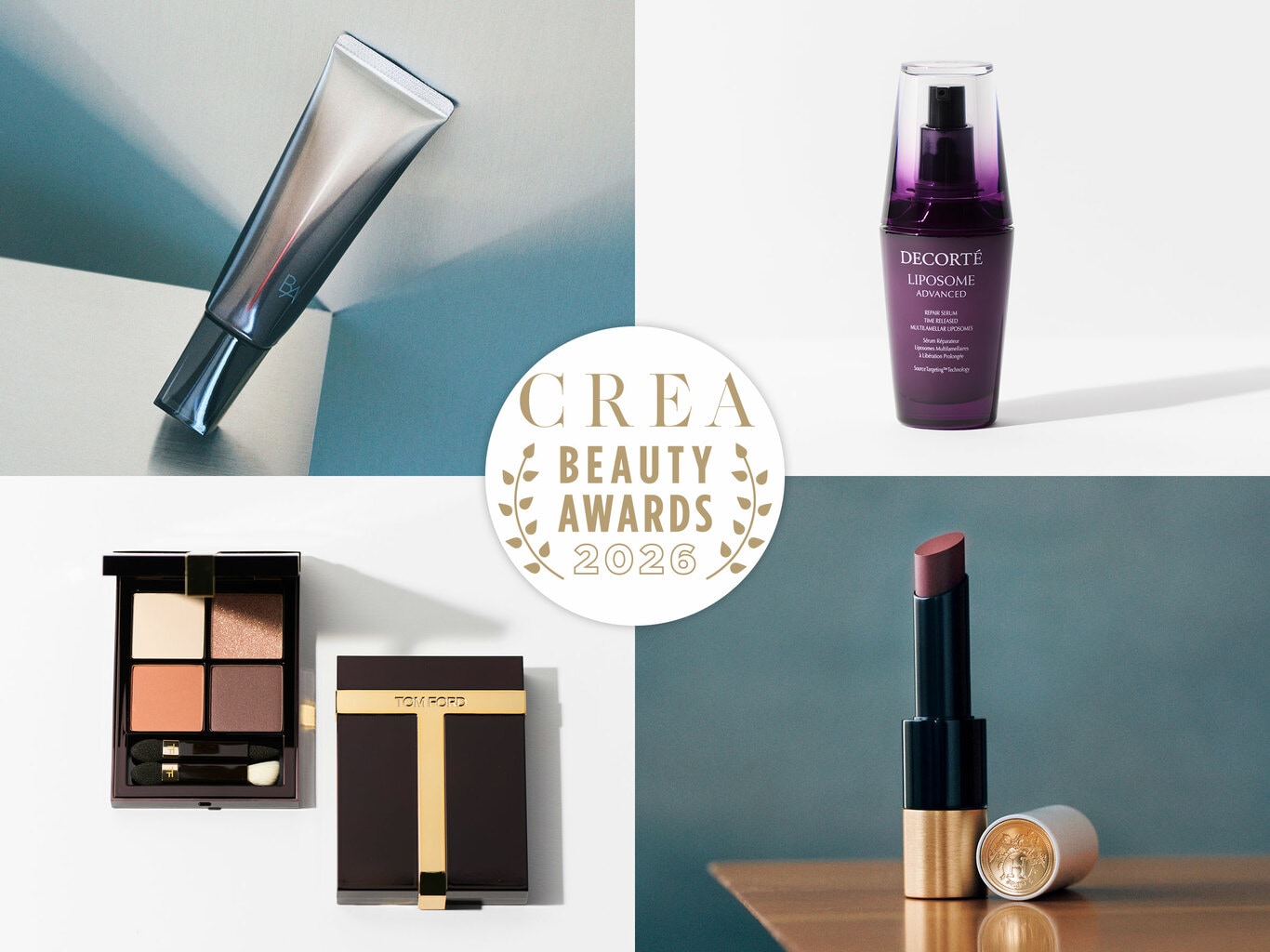江戸時代という長く、相対的に平和な時間は、人々の趣味や文化を豊かに育んだ。そのうちのひとつが「園芸」だ。幕末に来日した英国人の植物学者、ロバート・フォーチュン(フォーチュンはアヘン戦争後の中国で茶の木を探索するために派遣されたプラントハンターでもあった)が、江戸市中の人々の暮らしを彩る鉢植えを見て、「もしも花を愛する国民性が、人間の文化生活の高さを証明するものとすれば、日本の低い階層の人びとは、イギリスの同じ階級の人達にくらべると、ずっと優って見える」と驚いたとおり、大名や武士だけでなく、庶民の間にも園芸文化が、まさに「花開いて」いた。7月30日から開催される「花開く 江戸の園芸」展では、そうした江戸の人々と草花との親密な関係を、錦絵や版本などによって解き明かしていく。
江戸時代、園芸が盛んだったのはいいとして、ではその園芸ブームはどこから来たものなのだろう? たとえば現代の日本でもっとも人気のある江戸時代の絵師といえば、リアルな鶏の絵で知られる伊藤若冲だと思うが、彼の生き物、そして自然への好奇心に満ちた眼差しは、ひとり若冲だけの特質ではなく、この時代に広く共有されたものだった。そしてそれはやがて「園芸」へもつながっていく、深く大きな水脈なのだ。
 勝川春好(二代)画 「薔薇図」 文化12年~文政2年(1815~19) 個人蔵 (会期全日展示)
勝川春好(二代)画 「薔薇図」 文化12年~文政2年(1815~19) 個人蔵 (会期全日展示)
あらゆる人工物は、当時「天産物」と呼ばれた動物、植物、鉱物を原材料に作り出されていた。中でも命をつなぐために必須の、薬用となる天産物の知識をまとめた学問を「本草」といい、中国に起源を持つ。日本にも奈良時代から伝わってはいたが、「本草学」が盛んになるのは、中国本草学の集大成として1596年に上梓された、李時珍の『本草綱目』が徳川家康に献上された時以降のことだ。