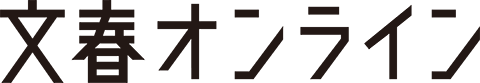アストラゼネカ社側の言い分は、まさに「ベストエフォート(最善の努力)の結果であれば許容される」という「ベルギー法」の原理に基づいた主張だ。
「ワクチン・ナショナリズム」による勝利
当然、EU側のいら立ちは収まらない。法的手続きに続いて、5月9日には、EUのブルトン委員が、アストラゼネカ社のワクチンについて、「来月(6月)以降の追加の注文はしなかった」と明らかにした(仏ラジオ局のインタビュー)。だが、その一方で、ブルトン委員は「アストラゼネカ製のワクチンは温度管理が容易だ」とも述べ、今後再び購入する可能性は排除しない中途半端な態度をとったのである。
現在のワクチン接種率を見ると、4月13日時点で、英国は47.62%、フランスは16.68%、ドイツは16.9%、EU全体は15.94%で、英国が突出している(Our World in Data調べ、ちなみに日本は、0.91%)。

そもそも英国は、昨年7月10日の時点で、EUによる「新型コロナワクチンの事前買い取りスキーム」への不参加を表明していた。このスキームは、ワクチンの早期確保を目指し、EUが加盟国に代わって個々のワクチン製造業者と契約を結ぶことを企図したもので、正式なEU離脱前で英国も参加可能だったが、「参加をしたところで、発言権は与えられず、価格やどのメーカーと交渉するかなどの自由度も奪われ、ワクチンの供給時期も一方的に言い渡される」(英ワクチン・タスクフォース座長)という判断で参加しなかったのだ。
ワクチン不足に悩むEUだが、実は、EU域内で生産しているワクチンの3割を輸出している。しかも最大の輸出先が英国なのだ。「EUがワクチン・ナショナリズムを貫き、ワクチンを輸出しないという選択肢を取っていれば、英国よりも接種が進んでいた可能性もある」(オランダ人研究者)という恨み節が聞こえてくるのも無理もない。
英国在住の筆者の友人に「英国のワクチン戦略の成功」について尋ねてみると、「EUは英国に嫌悪感を抱いていて、英国が極めて貪欲だと感じていると思う」と語っていた。
こうして見ると、英国が「欧州とは違う」という姿勢を貫いたことが、少なくともワクチン戦略においては功を奏したわけで、英国のコロナ対策「大逆転」の勝因もここにあったと言える。だが、こうした英国の「強欲さ」(=ワクチン・ナショナリズム)は、「欧州」の人々に嫌悪感を抱かせるものでもあるようだ。
◆ ◆ ◆

近藤奈香氏による「英国コロナ対策「大逆転」の勝因」は「文藝春秋」6月号および「文藝春秋digital」に掲載されている。
2021.05.25(火)
文=近藤奈香