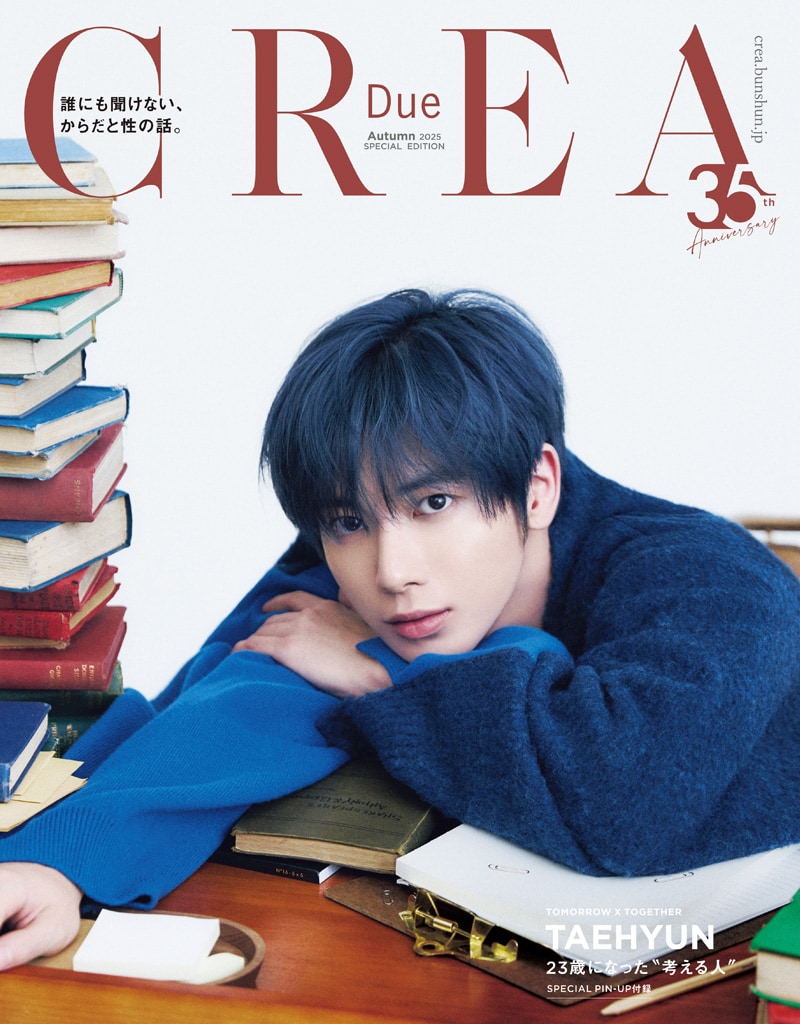朱鷺が生い茂った雑草の中にしゃがみ込んだ。もちろんトンボもそれに倣う。
「これから喋ったらいかんさけね。聞こえるのはすごく小っちゃい音っていうから、しっかり耳を澄ませんと」
「わかった」
朱鷺が胸の前で祈るように指を絡めて目を閉じる。しばらくトンボも同じようにしていたが、すぐに飽きてしまった。そっと薄目を開け、水面を泳ぐ鳥や雲が空を流れていく様子にぼんやり眺め入った。
向こう岸に女が現れたのはそんな時である。女もまた、水際のカキツバタを覗き込んでいる。物好きというのはどこにでもいるらしい。
最初は同じひがしの芸妓かと思ったが、顔に見覚えはない。髪形や着物の崩し方から堅気でないことは確かなようだ。女はトンボたちに気づくことなく、さかんに花を見回している。
その時、朱鷺がはしゃいだ声を上げた。
「聞こえた。確かに今、ポンって鳴ったわ」
弾んだ声で言った。
「そう、よかったな」
「あんたは聞こえんかった?」
「まあ、聞こえた気もせんでもないけど」
トンボはとりあえず返しておく。
「そんならよかった。これで早起きして来た甲斐があったというもんや」
朱鷺は満足そうに頷くと、やけにしみじみとこんなことを言い出した。
「カキツバタって花は別々に咲いていても、根っこはみんな繫がっているんやて」
「へえ、そうなんや」
「あたし、それ聞いて何やら似とるなぁと思ったが」
「似とるって?」
「あたしら芸妓と。いろんな事情を背負ったいろんな芸妓がおるけど、何だかんだ言ったって、みんな根っこのところは同じなんやって」
「ふうん」
すぐには意味がわからない。
「だからな、あたし決めたが。みんなも辛いことたくさん抱えとるんやさけ、自分だけが不仕合せやなんて嘆くのはやめとこうって」
「そうか、うん、そうや、その通りや」
何にしても朱鷺がその答えに行き着いたのであれば、トンボは安堵するばかりだ。
朱鷺が満足げに立ち上がった。
「さ、そろそろ帰ろ。あたし、もうおなかぺこぺこ」
トンボも立って、ひとつ大きく背伸びをした。長い時間しゃがみ込んでいたせいで、ふくらはぎがじんじん痺れている。気が付くと、向こう岸の女の姿は消えていた。

おとこ川をんな川
定価 2,090円(税込)
文藝春秋
» この書籍を購入する(Amazonへリンク)
- date
- writer
- category