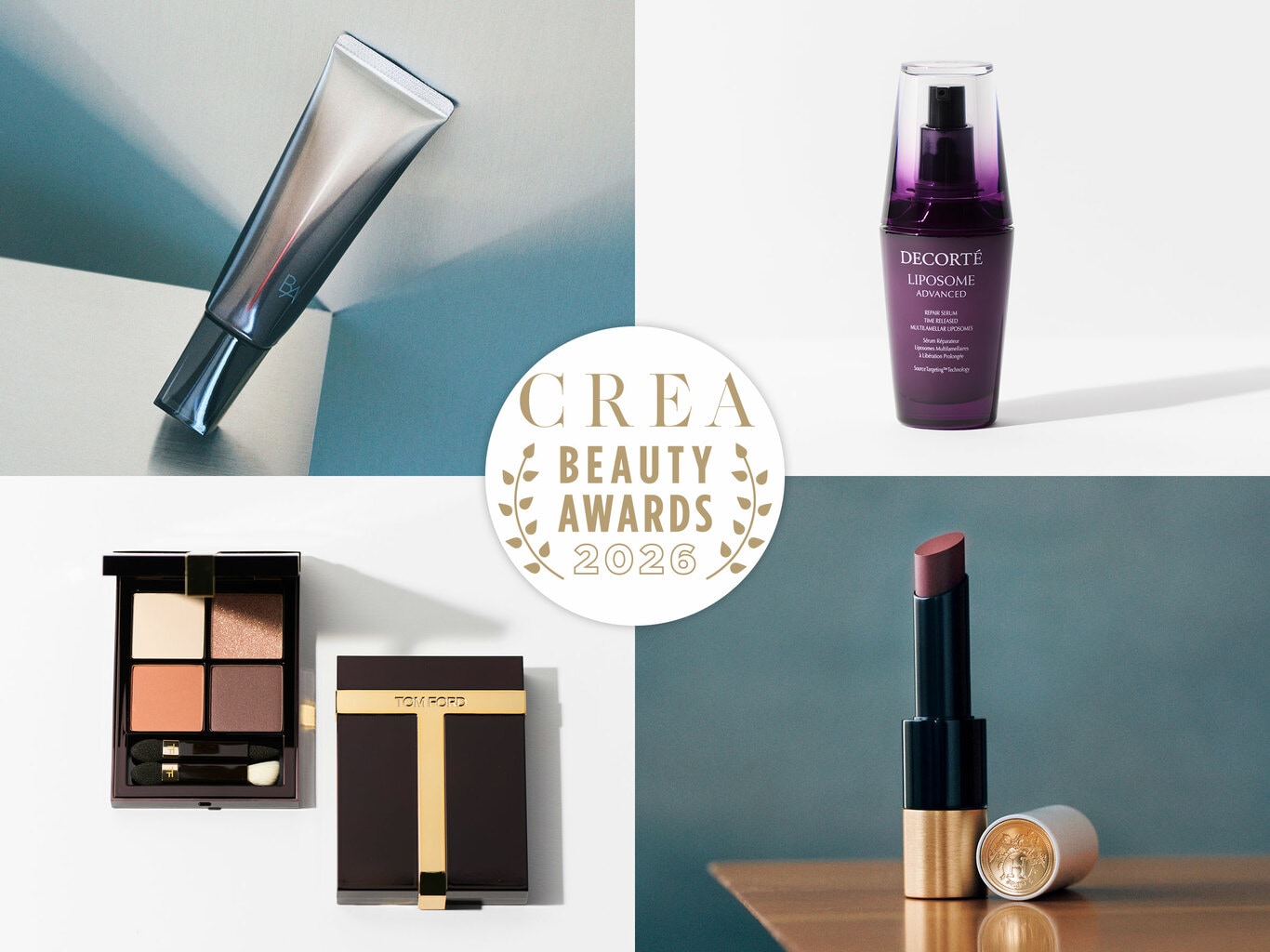『大菩薩峠』を書いた中里介山は随筆「『峠』という字」の中で、「峠」は日本で作られた漢字「国字」であり、本来の漢字なら「嶺」だが、これは「山の最頂上では無く、領とか肩とかいう部分」のことで、「西洋語のパスとかサミット」も意味合いが違うだけに、「峠」には「含蓄と情味がある」と書いている。その上で、「上る人も、下る人も」立たなければならない「峠」を、「人生そのものの表徴」と位置づけていた。
岡野藩領内で結城藩との国境にある峠は、近くにある弁財天の御堂にちなみ弁天峠と呼ばれていた。そこで茶店を営むわけありらしい夫婦が、峠を通る人たちのトラブルを解決していく本書『峠しぐれ』も、峠を人生そのもの、あるいは人生の岐路になぞらえている。
茶屋の主人の半平は四十過ぎ、達筆で帳簿付けなどもできるので麓の安原宿で武家の一行が泊まるときの手伝いを頼まれることもあり、宿場役人の評判もよかった。女房の志乃は三十五、六、目鼻立ちがととのい色気があり客の面倒見もよいため地名にあやかって「峠の弁天様」と呼ばれていて、弁財天の御堂ではなく志乃が弁天峠の名の由来と誤解されるほどになっていた。
ある日の早朝、志乃が夜逃げらしい家族に声をかけた。事情を聞くと、主の吉兵衛は結城の城下で味噌問屋をしていたが、藩政改革の一つで産物が特定商人の専売制になり、結城家に金を貸している島屋五兵衛が巨利をむさぼる一方、販売権を奪われ没落する商家も出ており吉兵衛もその一人だった。現代でも、有力な政治家と結び付いた業界や財界人が優遇されているという噂があり、そこまで露骨でなくても政策や税制が変るだけで打撃を受ける業種はあるので、吉兵衛一家の境遇は生々しく感じられるのではないか。
吉兵衛一家を見送った半平と志乃は、翌日やってきた麓の安原宿の宿場役人・金井長五郎から、吉兵衛一家の荷物から高価な珊瑚の簪が出てきて、それが城下の材木商に押し入った盗賊が奪った品ではとの疑惑をもたれているという話を聞く。無罪を証明するため宿場の番所に向かった志乃が、吉兵衛一家から話を聞き、その証言を過不足なく使って論理的な謎解きを行うところは、ミステリ・ファンも満足できるのではないか。近隣を荒らしている盗賊夜狐との戦いは、物語を牽引する重要な鍵になっていく。
文=末國 善己(文芸評論家)