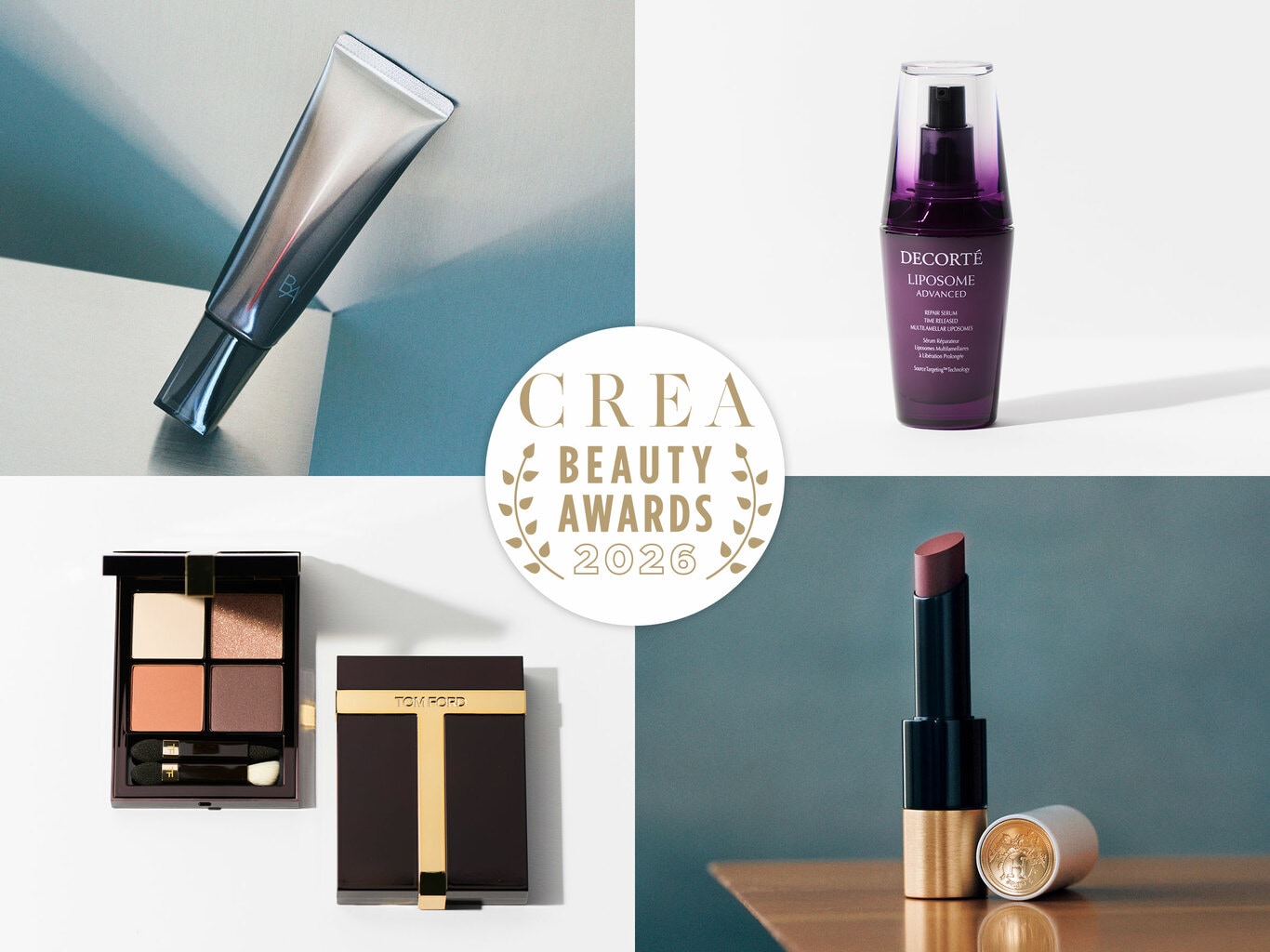マイノリティとの深いつながりが彼女を戦いに駆り立てた

映画のなかでもっとも痛ましいものとして映るのは、1980年代から90年代にかけておきたHIV/エイズ危機。性的マイノリティの人々と親密な関係を築き、そのコミュニティのなかで生きてきたゴールディンにとって、HIV/エイズ危機は、親しい人たちの命を次々に奪っていく、無慈悲な戦争のようなものだったはずだ。
HIV/エイズ危機をめぐる描写のなかで、ある市民運動家たちの姿がクローズアップされる。ゲイの劇作家ラリー・クレイマーらが1987年に設立した活動団体「ACT UP(アクトアップ)」は、HIV/エイズの蔓延に有効な手立てを講じようとしない政府にしびれを切らし、政府や製薬会社らを相手に、大胆な抗議活動を行うようになる。ニューヨークで始まったその活動は他の都市にも伝わり、ヨーロッパにも波及した。そのひとつである「ACT UP Paris」の姿を描いた映画が『BPM ビート・パー・ミニット』(2018)で、ロバン・カンピヨ監督自身の経験をもとに、90年代のフランス・パリでのACT UP Parisのメンバーたちの戦いが描かれる。治療薬の開発を求め、製薬会社に乗り込み血のりを投げつけるパフォーマンスを行い、エイズ=同性愛という偏見と戦いながら若者たちに性行為での感染を防ぐ方法を周知させる。メンバーたちが、命をかけて政府や製薬会社と戦い、自分たちを見殺しにする社会に抗う様子に、ただ圧倒される。

ナン・ゴールディン自身が「ACT UP」に参加していたわけではないようだが、現在の彼女の戦いと過去の痛ましい記憶が交互に映ることで、現在の「P.A.I.N」の活動が、いかに「ACT UP」の活動から強い影響を受けたものであるのが、よくわかる。
同時に、ゴールディンがなぜサックラー家という、美術界でも巨大な力を持つ大富豪に立ち向かうのかも見えてくる。おそらく自身もバイセクシュアルであり(映画では、女性と男性、両方との恋愛経験が語られる)、10代の頃からゲイやレズビアン、ドラァグクイーン、トランスジェンダーの友人たちと家族同然につきあい写真の被写体にしてきた彼女は、性的マイノリティと呼ばれる彼らが社会のなかでいかに蔑ろにされ、暴力に晒されてきたかを、いやというほど目にしてきたはずだ。HIV/エイズ危機では友人たちの多くを失った。数が少なく弱い立場に置かれた人々は、社会のなかで、いつだって真っ先に見捨てられ、命すら奪われる。そんな現実を見つめてきた彼女にとって、巨大な資本によって名もなき人々の命が奪われていく「オピオイド危機」を見過ごすことなど、できるはずもなかったのだ。
ナン・ゴールディンとその仲間たちが、どんなふうに大きな力に抗い、弱き人々の命を救おうとするのか。そしてLGBTQのコミュニティとの深いつながりが、どのように彼女を戦いに駆り立てたのかを見つめ、自分なりの戦い方を考えてみたい。
文=月永理絵