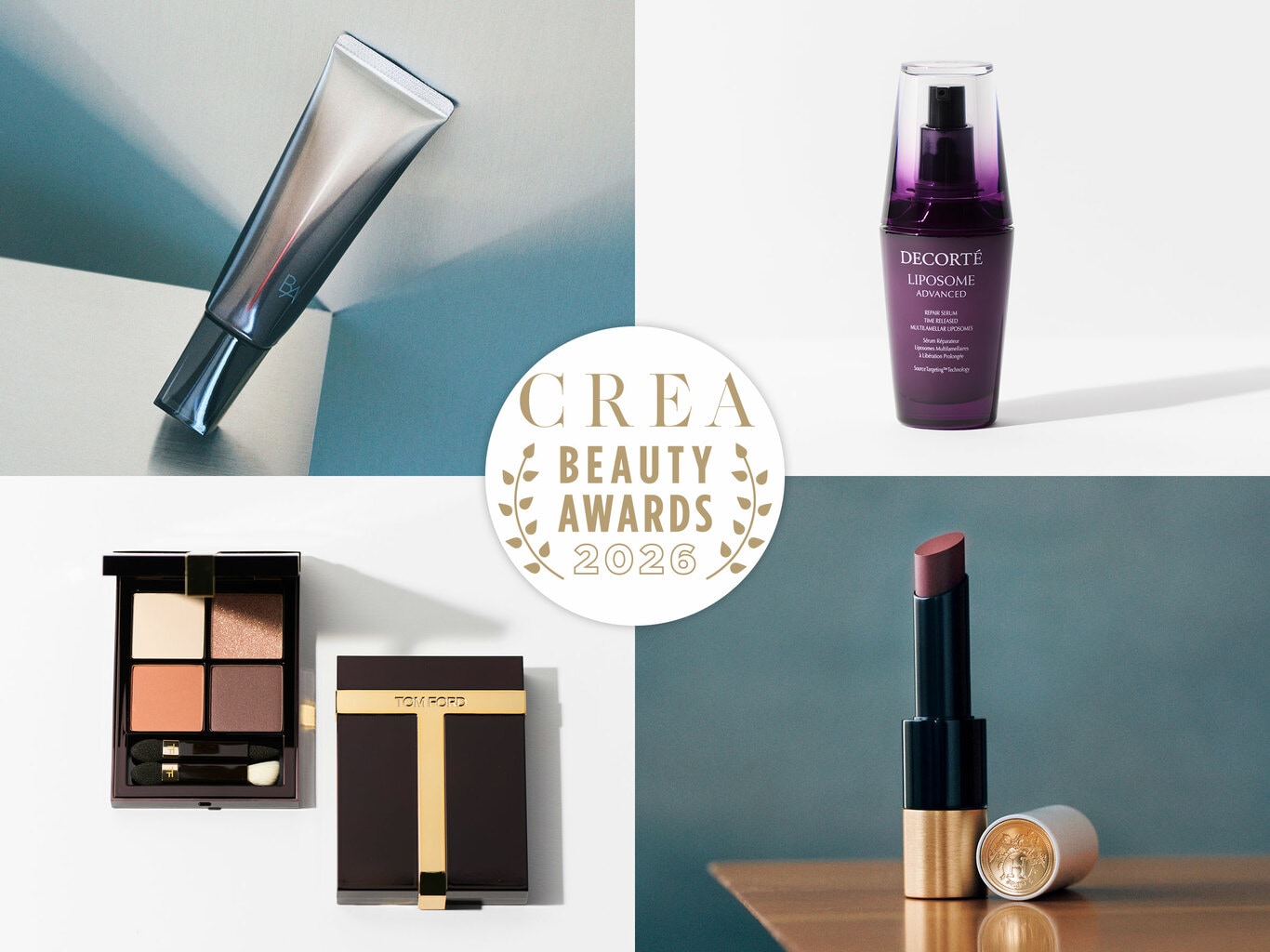また、“聖”の側の人々が物語に深く関わっている点も澤田作品的である。澤田作品において、「僧」には重要な役割が与えられている。東国武者の平将門と仁和寺僧の寛朝との交流を描いた『落花』(中央公論新社→中公文庫)や、悪僧(僧兵)として興福寺に身を置く範長が、平家、ひいては戦乱の時代と向き合う『龍華記』(角川書店→角川文庫)などがその好例として挙げられようが、武家や庶民といった“俗”とそこから隔絶した世界である“聖”を対置して作品のテーマを浮き彫りにする手法は、澤田作品においてしばしば散見される。それらを踏まえて眺めると、本作もまた“聖”と“俗”の対照による物語と位置づけできよう。
様々な階級の人間を登場させる人物配置も、澤田作品らしさの一端を担っている。本書は皇女の住持元秀や前住持の元瑶、青侍の梶江静馬や滝山与五郎、尼の浄訓の他、元秀の乳母の賢昌尼、住持に仕える大上臈の慈薫や、林丘寺を運営面から支える侍法師の碇監物や中通の嶺雲など、様々な人々が彩をなしている(個人的には、どこか生意気で、静馬に対して甘えが見え隠れする浄訓がお気に入りである)。こうした「様々な階級の人々を描き出し彩をなす」やり方も、天平期のパンデミックを描いた『火定』(PHP研究所→PHP文芸文庫)などにも見ることができ、後に石見銀山の人々を重層的に描く『輝山』(徳間書店)に結実していく要素である。
わたしが本作を著者王道作の系譜に連ねるべきと考えているのは、ざっとそうした理由からである。
しかし、本作において、右記の“澤田作品らしさ”が、物語の底流で少しずつ“ずらされ”ていることも指摘しておかねばならない。
先に「本作は近世離れした(空気が流れている)」と書いたが、厳密には正しくない。比丘尼御所の林丘寺は非近世的な雰囲気を湛えつつも、やはり近世という時代から自由ではない。それは、江戸時代のシステムに従い運営される林丘寺の姿が活写されているからであり、本作の事件の多くが林丘寺の外からもたらされるがために、林丘寺が絶えず近世社会と交渉せざるを得ないからでもある。
文=谷津 矢車(作家)