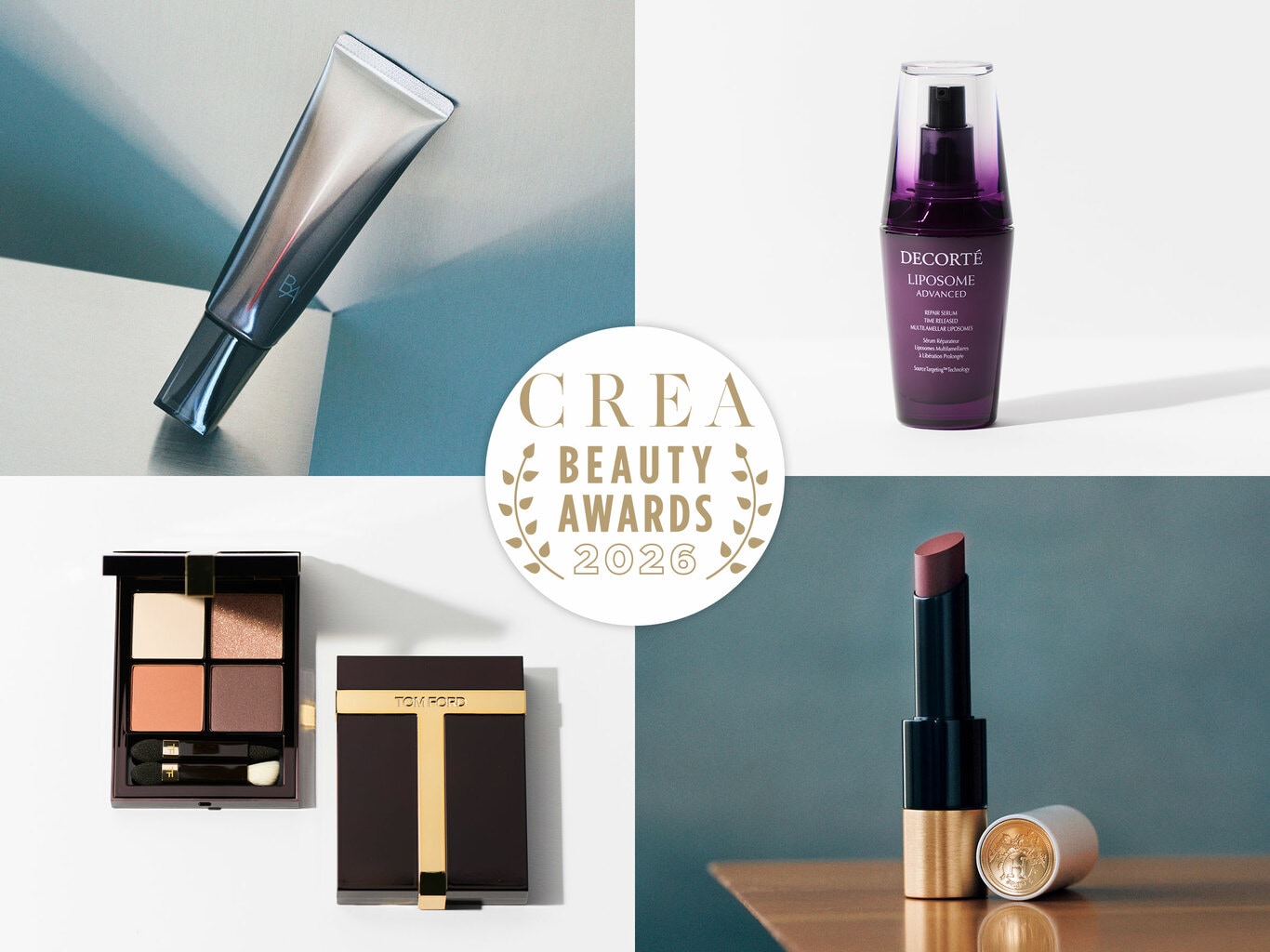「お前はクビだ!」
半年無給で働かされたのちに20人いるインターンのうちひとりだけが本採用されるという『幸せのちから』の設定は、「無理ゲー」であるように思えるかもしれない。けれども、そのような設定は21世紀初頭の新自由主義的なアメリカ文化においてはさほど珍しいものではない。たとえば、ドナルド・トランプ主演のリアリティTV『アプレンティス』(2004−2017年)を考えてみよう。
トランプ人気を確固たるものにしたこのリアリティTVにおいては、十数人の参加者たちがふたつのチームに分けられ、毎週何らかのビジネス(レモネードの売り上げを競う、など)に一種の「企業家」として挑戦する。成績が悪かったチームのなかから毎週ひとりずつが「クビ」になり、最後に残ったひとりが「見習い」(アプレンティス)として25万ドルの給与を保証され、トランプの会社に雇用される。
新自由主義的な競争社会の縮図とも言えるこの番組は、トランプの「お前はクビだ!」(“You’re Fired!”)という決め台詞とともに大きな話題を呼んだ。トランプの大統領就任を可能にしたのは、この番組の爆発的な人気であったと言っても過言ではない。新自由主義的な競争社会のなかでトップに立つ有能なビジネスマンというイメージが、彼の当選を後押ししたのである。

『幸せのちから』においては『アプレンティス』と同様に、個人の才覚で道を切り拓く企業家的な主体が、リアリティTV的なビフォア/アフターの枠組みのなかで理想化されている。けれども、『幸せのちから』におけるアメリカン・ドリームの礼賛は、より直接的にはトランプの前任者であるバラク・オバマのことを想起させるかもしれない。この映画が公開された2年後の2008年に大統領に当選したオバマのモットーは、「ここは、どんな見た目であろうと、出自がどうであろうと、懸命に学び、働く気があれば、才能の許すかぎり前進できる国です。やればできるのです」という言葉であった。
もちろん、アメリカン・ドリームの理念がオバマの専売特許であるわけではない。けれども、能力主義(メリトクラシー)の弊害を論じた『実力も運のうち』のなかでマイケル・サンデルが指摘しているように、オバマは大統領在任中にこの類いの表現を計50回使用しており、その使用頻度は他の大統領と比べると群を抜いて多い。オバマが目指していたのは、(たとえば人種差別などの「ハンデ」をなくして)全員が同じスタートラインから競争を始められるような仕組みを整えることであり、競争社会という原則そのものを問い直すことではなかったのである。
文=関口洋平