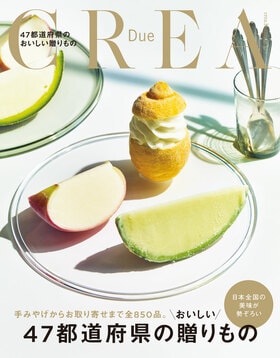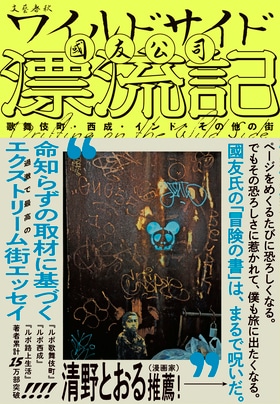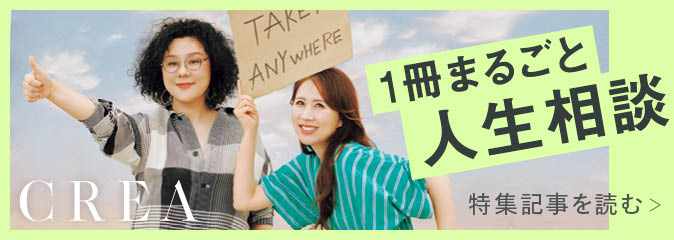(4)過度のきれい好きである
世の中がきれいになりすぎたために食物や花粉などのアレルギーが増えたという声がよく聞かれますが、はたしてどうなのでしょう。
私たちの体に異物が侵入した時、白血球が連携して防御してくれるシステムには、細菌やウイルスなど万人にとって有害な異物に対して作用する「免疫反応」と、食物の成分など無害であるはずの異物(アレルゲン)に対して作用する「アレルギー(反応)」があります。
異物侵入を察知した抗原提示細胞は、白血球の1つであるT細胞にそれを知らせます。
すると、T細胞のうち、細菌やウイルスが侵入した時はTh1細胞(1型ヘルパーT細胞)が、アレルゲンが侵入した時はTh2細胞(2型ヘルパーT細胞)が、リンパ球の一種であるB細胞に対して武器(抗体)をつくるように指令を出し、それが異物にくっついて撃退します。
アレルギーを発症しやすいかどうかは、このTh1細胞とTh2細胞のバランスが関係しているといわれています。
最近は衛生環境が整い、世の中が清潔になりすぎて感染症が激減したことなどからTh1細胞の出番が減り、代わってTh2細胞の働きが優位になり、本来攻撃する必要のない食物の成分や花粉にまで過剰に作用するようになったという考え方があります。
このようなメカニズムが、アレルギーの患者さん一人ひとりのメカニズムとしてどの程度重要かは十分明らかになっていません。しかし、世の中全体としてアレルギーの人が増えてきているのは、このようなメカニズムがあるからではないかと考えられています。
(5)ビタミンDが不足している
生活習慣とも関係していますが、乳幼児の場合、食物アレルギーを発症する数は、季節によって異なることが報告されています。
2歳以下を対象に行った疫学調査(あいち小児保健医療総合センターアレルギー科)で、食物アレルギーと診断された乳幼児は秋冬(10~12月)生まれが多く、春夏(3~5月)生まれが少ないという報告があり、日本以外の国からも同様の結果が聞かれます。
2022.03.21(月)
文=福冨友馬