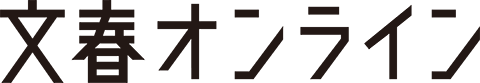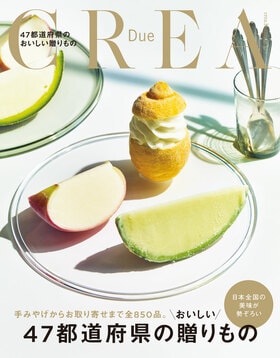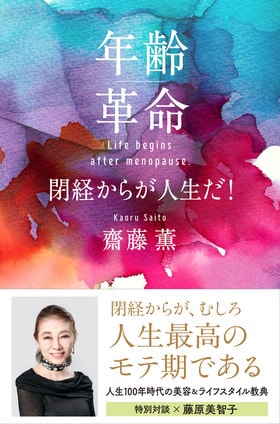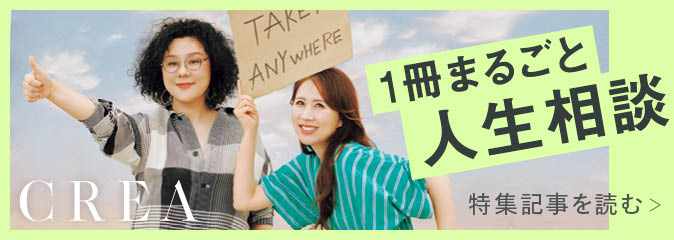お好み焼ならばどうしても大阪でなければならない
同種の発酵食品は、若狭の「へしこ」も名高い。鯖の糠漬けである。ものすごく塩辛くて癖のある食べ物だが、やはり小浜あたりまで足を延ばせば目から鱗。
これらもやはり、現地において最上級の品を消費していると思えるのだが、あるいは保存食品とは言えあんがい繊細で、よその風に当たればたちまち風味を損うのかもしれない。
さらに考える。
名産品というより、郷土の味覚。たとえば、お好み焼ならばどうしても大阪でなければならない。東京にも大阪からの支店があって、メニューも同じなのだが、この場合でもなぜか納得できぬ。似て非なるもの、という気がする。
具材の産地や油のちがいであろうか。いや、やはり私たちはお好み焼とともに、風を食べているのであろう。あのコッテコテの道頓堀の空気を。
これは全国各地のご当地ラーメンでも顕著である。トンコツには博多の力強く寛容な風が、またミソラーメンには札幌のツンと鼻に抜ける冷気が似合う。
ミソのついでに手前ミソを述べるなら、東京ならではの味は江戸前のファストフード。すなわち「鮨」「蕎麦」「天ぷら」「鰻」である。東京の風とともに食うならば、これらに尽きる。
ところで、私はしばしば中国を訪れるのだが、大好物の「フカヒレの姿煮」を現地で食べたためしがない。

メニューにある「魚翅湯(ユーチータン)」を注文すれば、出てくるスープは姿煮ではなく、定めて細切りのフカヒレである。
あれほど食にこだわる中国人が、姿煮を嫌うはずはない。そしてあまり知られていないことだが、中華料理に欠かせぬ「魚翅」は、あらまし日本の宮城県で生産され、輸出されているのである。
ということはもしや、「最もうまいものは自分たちで食べちまう」の原則にのっとり、姿煮は日本人の専有物なのではあるまいか。
名産品は現地に行って食べるべきである。
しかし、かく言う私もことほどさように暇を持て余しているわけではない。
そこで、いわゆる「お取り寄せ」。これは妙手である。
◆ ◆ ◆
文春マルシェ 文藝春秋の公式お取り寄せ
文藝春秋が、その「取材力」「編集力」を発揮して、食の通販サイトを始めます。
生産者やシェフ、仲買人など食の世界のプロとコミュニケーションをとり、ときには商品開発にも関わり、産地や素材や鮮度、調理法にこだわった品々をすべて試食してセレクト。
「これってニュースだね!」と会話が弾むような、喜びと驚き、そしてとびきりの美味しさをお届けします。ぜひお立ち寄りください。
文春マルシェ
本エッセイに関連する商品



2020.10.19(月)
文=浅田次郎