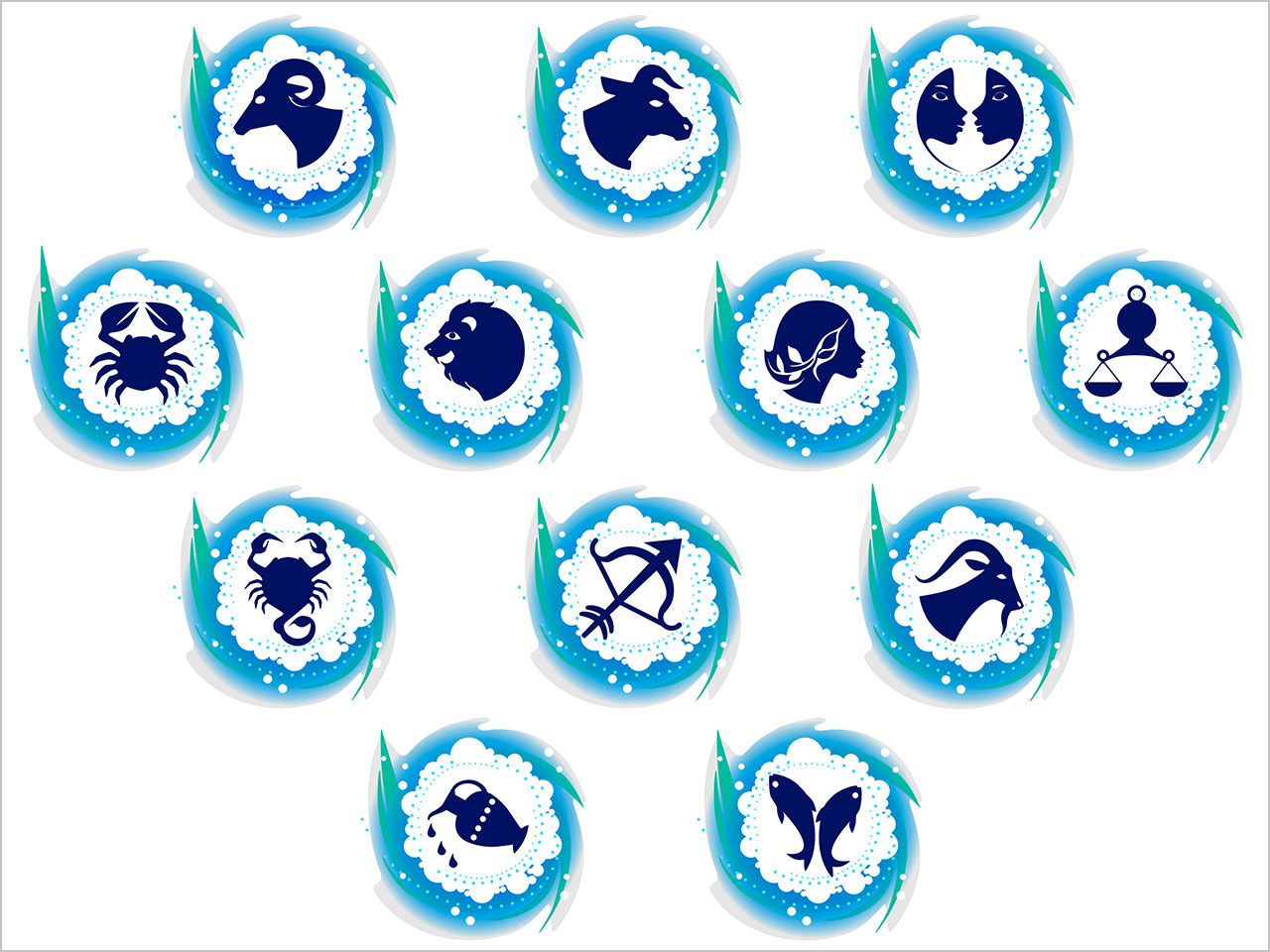妊娠しているとわかり、血の気が引いた
私が妊娠したのは、こんな詩人との同棲生活も10年目となったときだった。私には婦人科の持病があり、妊娠は難しいと言われていた。それなのになぜか身籠ったのである。受診した産婦人科の女医から受胎告知を受けたときは、血の気が引くのが分かった。
女医は茫然自失状態の私に「今回は諦めたら?」と助言した。カトリックでは堕胎は許されないが、彼女はそれに縛られない解釈をする人だった。そう志願したわけでもない子どもに、かすみを食べさせるわけにはいかない。女医の言葉が響いた。モモの仔猫たちも結局、食べさせることができないから1匹残らず貰われていった。自分は母親になる器ではないかもしれない、と感じた。

詩人に妊娠を告げると、露骨に動揺を顔に浮かべ、押し黙ってしまった。自らの無力感しか晒せない詩人を見ているうちに、急に悔しさが込み上げてきた。よりによってこんなときに初めて妊娠するなんて、これは何かの思し召しなのではないか。イタリアから一回は離れて別の仕事をしてみろ、ということなのではないか。そんな気がしてならなくなった。世が世なら、詩人もパトロンにお金を出してもらって、詩を書いたり、作曲したりして生きていった人だったのかもしれない。でも、残念ながらそれが叶う時代はとうの昔に終わっている。
- date
- writer
- staff
- 文=こみねあつこ
- category