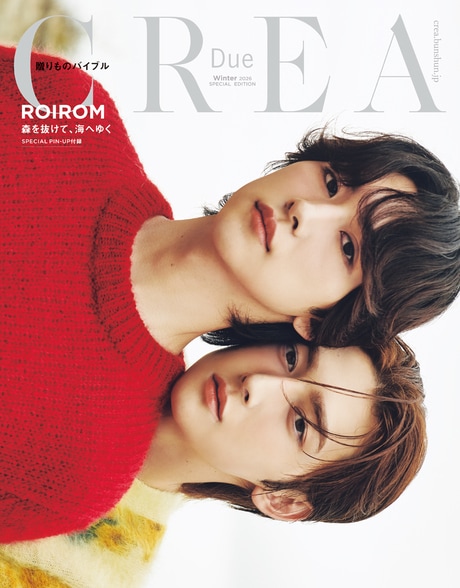精神論ではなく、「仕組み」によって生きづらさを改善するカウンセリングを行っている臨床心理士の中島美鈴さん。「決められない」モヤモヤを解決するための指南書、『マンガで挑戦 とっちらかった頭の中を整理して決められる人になる』(主婦の友社、マンガ:あらいぴろよ)を6月25日に上梓しました。
「時間にいつも追われている」「やるべきことにどうしても取りかかれない」――こうした状態は、決して「意志が弱い」からではないと中島さんは言います。
どうしたら「決められる」人になれるのでしょうか。中島さんにお聞きしました。
意思決定の教科書のようなものがあったら

――中島さんが、「頭の中の整理」に着目されたきっかけを教えてください。
中島美鈴さん(以下、中島) 私は日々のカウンセリングや講演会などで、時間管理やスケジュール帳の使い方についてお話しする機会がこれまで多くありました。でも、ご相談に来る方の中には、そもそも「何をするか」が決まっていない方がとても多いことに気がついたのです。
例えば「転職したいけれど、どういう仕事が向いているのかわからない」「何から手をつければいいか決められない」など、時間やスケジュールを管理する以前の段階で立ち止まっている方が非常に多い。そう思ってまわりを見渡してみると、実は本当の問題は「時間の使い方」ではなく、「意思決定」についての支援が足りていないことなのではないかと考えるようになりました。
――意思決定ができない人が多いということでしょうか?
中島 近年は情報量の増加により、選択肢が過剰になっています。その結果、情報収集の段階で迷子になってしまったり、自分が何を大切にしたいのかが分からなくなったりと、さまざまなかたちで思考が止まってしまう方が増えているように感じます。
そこで、こうした状況を改善するために、誰もが簡単に頭の中を整理して、問題を解決できる方法はないかと考えた時、私たち専門家が使っている「意思決定」のプロセスが活用できるのではないかと思いついたのです。
そして、意思決定の教科書のようなものがあったらいいのではないかと思い、本書を執筆することにしました。
――意思決定のプロセスを「もじせか」としてフレーム化しています。
中島 はい。心理学の分野では、意思決定のプロセスとして7つのステップが一般的です。私もカウンセラーとして大人のADHD(注意欠如多動症)のクライアントさんに向き合う時などに、この7つのステップにあてはめて整理することが多いのですが、専門家ではない一般の方が、日常生活において頭の中を整理するのに7つのステップは多すぎます。
ですから、この意思決定のステップを、認知行動療法や行動経済学の知見を交えながら4つに絞り、頭に浮かびやすい言葉に置き換えたのです。これが「もじせか」です。
- date
- writer
- staff
- 文=相澤洋美
撮影=平松市聖 - category