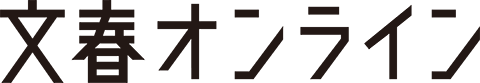震電の射出座席にはドイツ語の注意書きがあり、ドイツ製とみて間違いない。戦時中の日本はドイツから様々な技術供与を受けており、その一環として潜水艦で射出座席のサンプルがもたらされたのだろう。劇中の設定では、震電は現実世界よりも開発が進み、ごく少数の試作機が実戦配備されたことになっている。「それらの一つに試験的にドイツ製射出座席が装備された」という筋書きには、現実にも起こりうる説得力がある。
敷島が駆る震電に射出座席が搭載されていたのは決して「物語のつじつまを合わせるためのご都合主義」ではなく、いくつかの「if(もしも)」が重なれば十分にあり得たことなのだ。仮に零戦に射出座席を装備する展開だったら、映画のリアリティーは大きく損なわれていただろう。
「いくつものあり得たかもしれないif」
ぶっちゃけた話をすれば、仮に震電の初飛行がもう少し早かったとしても、実戦で活躍した可能性は高くない。震電と同様の「先尾翼機」としては米国も戦争中に「XP–55アセンダー」という機体を開発していたが、操縦性が劣悪だったことなどが原因で開発中止に追い込まれた。震電の試験飛行についての記録にも、プロペラのトルク(回転力)に負けて機体が右に傾く癖がひどかったことや潤滑油の温度の上昇傾向があったことが記されている。複雑な機構のスーパーチャージャーを搭載したエンジンも、欧米よりも工作精度が劣る上に原材料の調達もままならず、爆撃で多くの工場が破壊された当時の日本では、まともに生産・稼働させることは難しかっただろう。

それでも山崎監督は「主設計者を務めた鶴野正敬技術大尉の天才性によって、震電が空力的に高い完成度の機体であったとしたら」「ごく少数の試作機が技倆の高い熟練工によって精度の高いパーツで製作され、計画に近い性能を発揮していたとしたら」「試作機の一つにドイツから輸入された射出座席が装備されていたとしたら」「その試作機が戦争を生き延び、優秀なパイロットと巡り合えたとしたら」という、「いくつものあり得たかもしれないif」を緻密に積み重ねていくことによって、劇中の震電に「対ゴジラ戦兵器」としてのリアリティーと生命力を与えることに成功した。私はそのことに対して心から敬意を表する。
◆
本稿の全文「『ゴジラ-1.0』の謎を解く」は、「文藝春秋 電子版」に掲載されています。
2023.12.05(火)
文=太田啓之