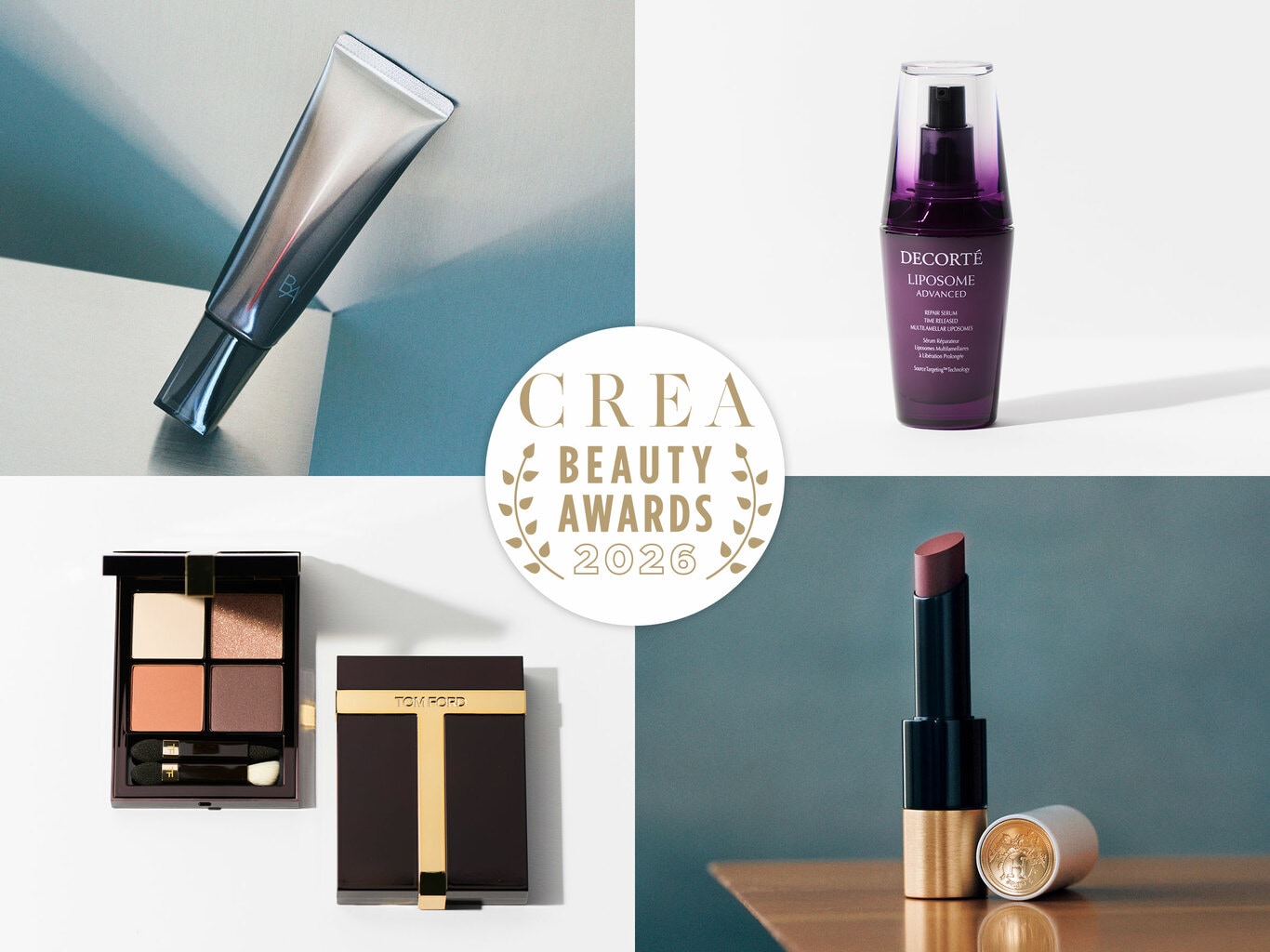映画パンフは日本独自の文化ではない??
――じゃあ、パンフも続編というのを踏まえているんですね。
大島 実はぼく、いままで長い間、映画ビジュアルの仕事をやってきていますが、続編をやるのは初めて。なので、冊子としてもシリーズ感がありつつ、時代をさかのぼる感じにできればと。それで、神保町の古本屋へ行って古い映画のパンフレットを物色したんです。1950年代の映画のパンフをかき集めて。

――というのは?
大島 『Pearl パール』は1910年代の話だけど、映画のルックは1950年代のテクニカラー。『オズの魔法使い』や『メリー・ポピンズ』、そして、ダグラス・サークのメロドラマがテーマになっているんです(注:ダグラス・サークは50年代のハリウッドで活躍した映画監督。数多くのメロドラマを手がけている)。なので、その時代の映画の雰囲気を出せればと。
――だからビビットな色合いの人工着色感があるんですね、映画自体に。
大島 あと、これは最近思うようになったことなんですが。パンフって、観る前に買って読んじゃう人ってわりといるじゃないですか。だからあんまりネタバレしちゃいけないとずっと思っていたんです。でも、そういうことを気にするのはやめようと。パンフはやっぱり「観終わった」人のためのもの。どんな映画だったのかを振り返るときに、大事なネタが入ってないのはモヤモヤしてしまう。なので、今回はネタバレ全開で作りました。重要なシーンのスチールもバンバン使っているんです。
――最後の最後に出てくるミア・ゴスの変顔とか(笑)。
大島 あれは外せません。あと、『X エックス』と『Pearl パール』を比較し、ショット的に同じようなシーンを並べると面白いなと思い、そういう構成のページを作ってみたり。そして、1918年って、第1次世界大戦の時代であり、スペイン風邪の時代だった。いまと状況が非常に似てるんです。実際、タイ・ウェストやミア・ゴスはコロナ禍で撮影を頑張っていました。ですから、それも物語上非常に重要なフックになっているので、スペイン風邪の記事が載る新聞のビジュアルを入れてみたり。あと、劇中、『PALACE FOLLIES』という架空のミュージカル映画が登場するんですが、そのパンフレットも作って綴じ込みで入れました。パンフ内パンフとして。

――へえ~!
大島 さっきも言ったけれど、映画のパンフレットって「日本特有の文化」だと言われてるじゃないですか。
――ですよね。戦後、「映画プログラム」と呼ばれる有料で販売される冊子が作られるようになったと。有楽町のスバル座で始まったとも言われています。
大島 でも、『Pearl パール』の劇中に出てくるんですよ、パンフが。
――うわ! 確かにそうだったかも。パールが映写技師と出会うシーンですよね。
大島 そう。映画を観終えたパールが、パンフレットを読んでいる。だから、実はアメリカでもパンフ的なものがあったんだなって。販売されていたのか、フライヤー的に配布されていたものなのか、あのシーンからでは判断できませんが、もし販売されていたとすればいつまでそういった文化があったのか。
――もしかすると、アメリカの文化が日本に取り入れられ、現代に至るまでガラパゴス的に残っているのが日本のパンフ文化だったりする?
大島 かもしれない。ちゃんと調べてみないと詳細はわからないけれど。なので、その画像を抜き出しパンフを完コピしたんです。イラストレーターさんにこれと同じものを作りたいので絵を復元してください、とお願いして(笑)。
――うわあ~。大島さんも相当狂ってます(笑)。
大島 そういう部分はつい偏執的になっちゃうんですよ。パンフレットの文字組も50年代の日本のパンフを踏襲してますから(笑)。

文=辛島いづみ 写真=平松市聖