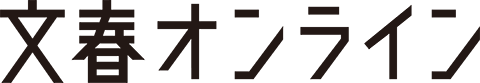しかし、『東京卍リベンジャーズ』は、リアルタイムでヤンキーを知らない世代にウケた。10代や20代の若い世代は、実生活でヤンキーと接した経験などほとんどなく、本作の世界観はあまりにも現実からかけ離れているのに、この作品を支持したのである。
なぜヤンキーは、時代を超えて日本人の心性に響き続けるのか。『東京卍リベンジャーズ』がメガヒットに至った要因を探るとともに、日本ではマンガを通じてヤンキー文化がどのように受容されてきたかを紐解き、日本人とヤンキー文化の関係性を見ていきたい。
画風を変えた理由は作者の”不退転の決意”
『東京卍リベンジャーズ』の作者・和久井健は、元スカウトマンという、マンガ家としては異色の経歴を持つ。スカウトマンとは、歌舞伎町などの繁華街で女性に声をかけ、風俗店やキャバクラなどで働くように誘い、店側から紹介料を報酬として受け取る職業である。マンガ家としての連載デビュー作は「週刊ヤングマガジン」(講談社)での『新宿スワン』(2005~2013年)。スカウトマンとしての経歴を活かした作品で、新宿歌舞伎町を拠点に活動するスカウトマンの主人公を通じて、闇金融やホストといった裏社会を描いてみせた。作品自体はフィクションだが、みずからの体験や見聞にもとづくリアルなアウトロー描写には、ある種のドキュメント性があり、『新宿スワン』は8年以上も連載が続く人気作となった。2007年にはテレビ朝日系列でドラマ化され、実写映画も2015年と2017年と2作が公開された。

『新宿スワン』の連載終了後も「ヤンマガ」で執筆していた和久井が、次なる活動の場を少年誌の「少年マガジン」に求めたのは2015年のこと。移籍第一弾の『デザートイーグル』(2015年)の連載が1年足らずで終了した和久井としては、次作の『東京卍リベンジャーズ』には不退転の決意で臨んだことだろう。
そうした決意のほどは、絵柄にも表れている。それまでの和久井の絵柄は、リアリティレベルの高い劇画タッチを基調に、コメディリリーフのギャグでは小林まこと(『1・2の三四郎』『柔道部物語』など)的なデフォルメを取り入れたものであったが、『東京卍リベンジャーズ』では、より少年誌らしい絵柄へと変化している。その変化が顕著に現れているのは、キャラクターの目の描き方だ。『新宿スワン』と『東京卍リベンジャーズ』の第1巻の表紙カバーイラストを見比べれば一目瞭然である。
絵柄を少年誌用にアジャストしてまで臨んだのが『東京卍リベンジャーズ』であり、その不退転の決意で選んだ題材がヤンキーであった。
◆
フリーライターの加山竜司氏による連載「ヤンキー漫画と日本人」第1回全文は「文藝春秋 電子版」に掲載されています。
2023.05.09(火)
文=加山竜司