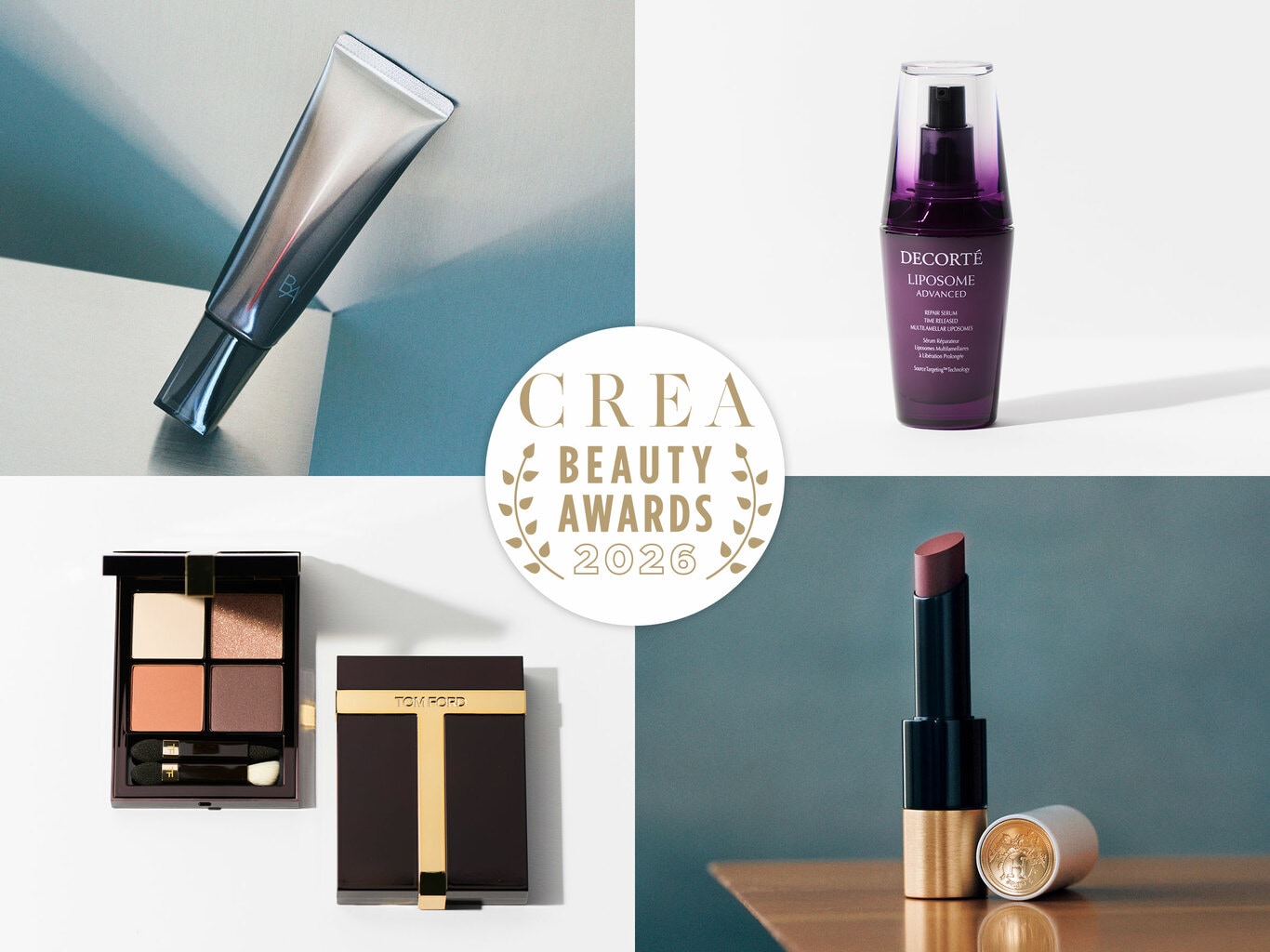1960年代から1970年代にかけて、大学では学園闘争、左翼運動が吹き荒れた時代である。そのあたりの学生運動の話は、これまでかなりの評論で論じられてきたし、小説作品としても柴田翔『されどわれらが日々――』をはじめ、大江健三郎や高橋和巳や笠井潔の作品として描かれてきたところでもある。ところで私が大学生活を過ごした1980年代は、左翼運動や学生運動はあったものの、前面に出てきていたのは宗教の勧誘活動の方であった。それは1990年代になって、オウム真理教事件という禍々しい形で世間に具現化していくことになるが、ある意味でこれはひと世代前の学生運動が浅間山荘事件やよど号ハイジャック事件に行き着いた左翼運動の経緯と相似形をなしているのではないか。そのようなことを、オウム真理教事件の派手な報道をみながら私は考えたことがある。
実際に私の生活圏においては、オウム真理教はそんなに離れた出来事ではなく、今でも覚えているのは、大学に入学した1984年の秋に東大の駒場キャンパスで開かれていた学園祭に、オウム真理教がデモンストレーションをしに来ていて、学内サークルと連携して講演会を開催していたことである。その学園祭で浅田彰と中沢新一という、当時ニューアカデミズムのスターとしてもてはやされていた二人の著名人の対談イベントがあり、両者の思想に興味をもっていた私は聴衆の一人としてこの対談を聴いた。浅田彰は後に、チベット密教などに由来する東洋の神秘思想などを頭ごなしに否定するようになるが、この対談の時点で中沢となごやかに語っていた内容では、中沢が『チベットのモーツァルト』や『虹の階梯』で提唱している神秘主義思想への深い共感と讃歌が基調になっていて、私は感銘をうけた。その講演が終わった後、その当時からオウム真理教の存在に関心をもっていた私は、そちらも聴きに行こうか迷ったが、そちらに誘ってくれる友人はいなかったので行かずじまいだった。もしそのときに私の背中を押す知人か友人がいたら、私はオウム真理教の講演を聴きに行った可能性は充分にあったし、その後の分岐する人生ルートとして、オウム真理教の信者になっていたルートは、自分の中では無視できないほどにリアリティがある人生行路として可能性はあった。
文=小森 健太朗