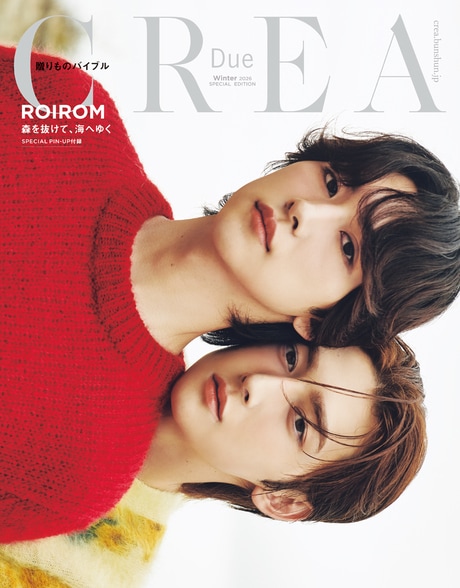この世代の多くに感じられるのは「反抗」です。「欲しがりません勝つまでは」から、一夜にして「民主主義万歳」に転じた大人たちへの不信感。それが彼らのエネルギーになっているように思えます。
その次に来るのが、昭和十五、十六年生まれ。私が昭和十四年、立花隆さんは十五年生まれ、映画監督の宮崎駿、『機動戦士ガンダム』の富野由悠季、思想家の柄谷行人さんたちはいずれも昭和十六年生まれです。敗戦の瞬間と、それに続いた大混乱をぎりぎり覚えている、昭和の戦争を直に体験した最後の世代と言えるでしょう。
私自身の体験でいえば、昭和二十四(一九四九)年か二十五年のことですが、小学校で「将来何になりたいか」と聞かれて、花屋さんだとか電車の運転手だとか答える中で、「陸軍大将」と答えた子がいました。すると、教師は「この平和主義の世に何を言うか」と、その子を殴った。これを「断絶」とみるか、「地続き」とみるか。戦前ならば「陸軍大将」は正解で、殴られることはなかったでしょう。その意味では、戦前と戦後は断絶している。しかし、教師の意に沿わない発言をしたら平気で殴るという点では、戦前も戦後も何も変わっていない。
多種多様な声を聴く
ここまでが戦前に生まれた世代です。
戦後まもなく団塊の世代(昭和二十二〔一九四七〕~二十四年生まれ)が登場し、高度成長の世代(昭和三十五〔一九六〇〕~四十年生まれ)が続きます。戦後復興の軋みを一気に受けた世代と、その恩恵を享受した世代といえるでしょう。
団塊の世代はとにかく人口が多い。この三年間で生まれた子どもは八百万人を超えています。現在では年七十万人を割り込んでいますから、今なら十年分を超える子どもがたった三年の間に生まれたわけです。過剰競争の時代でもあり、政治の季節が終焉を迎えた世代でもあります。
昭和三十五~四十年生まれは、日本が本当に豊かになっていく中で育った世代といえるでしょう。この世代も多くの書き手を輩出しましたが、子どもの頃から大量の文化、情報に接してきたことが窺がえます。
- date
- writer
- category