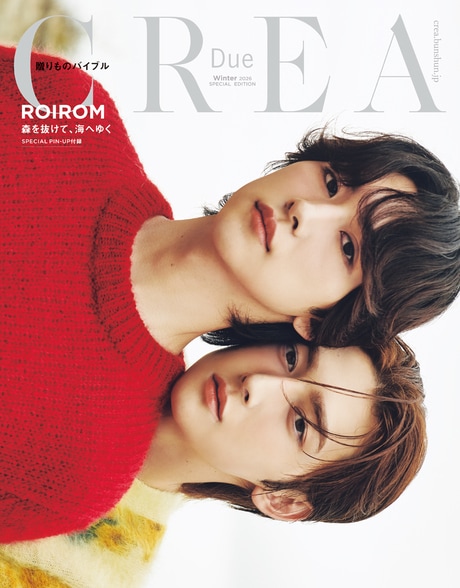しかし、昭和を「歴史」と捉える世代には、それでは通用しなくなります。そもそも「侵略」の定義とは何か、そのとき日中それぞれがどのような状況に置かれており、どうして最終的に軍事的な行動に収斂していったのかを、きちんと検証し、整理する必要がある。これが「歴史」の見方です。
「日本が中国で軍事行動を行い、多大な被害を与えた」「軍部の判断が日本の政治に大きな影響を与えた」という「事実」は変わらなくても、なぜそれが起きたのか、その根源には何があったのか、という、より俯瞰的な議論に重点が移ってくると思います。
なぜ「昭和史」に取り組んできたか
昭和が「同時代」から「歴史」になるということには、もうひとつの側面もあります。それは史料などのかたちに残りにくい、同時代を生きた人たちの体験、感情などが伝わりにくくなることです。
先ほど、「同時代」は「結論ありき」の見方に引っ張られやすい、といいましたが、その反面、昭和を体験した私たちには、この時代に何が起きていたのか、そこでどんな人たちが何を考え行ったのかを知りたいという強い関心がありました。それが、昭和が「歴史」となるなかで失われていくのではないかという恐れもあります。
私は昭和五十四(一九七九)年に『東條英機と天皇の時代』を書きましたが、当時、東條といえば軍国主義の象徴で、日本を敗戦に導いた張本人というイメージが固まっていました。そうした「結論」をいったん横に置いて、虚心に資料を読み、取材を重ねることで、東條の実際の人物像に迫れないだろうかというのが、私の出発点でした。
「同時代」を対象に「歴史」を書く、「歴史」の眼で「同時代」を見るということは実はとても難しく、どうしても歪みや限界も含みます。それでも、どうにかして私たちの生きた時代を「歴史」として位置づけ、それに自分たちの生きてきた姿を照らしてみたい。『日本のいちばん長い日』など多くの昭和史に関する著作で知られる半藤一利さんなども、そうした思いから「昭和史」に取り組んできたと思います。
- date
- writer
- category