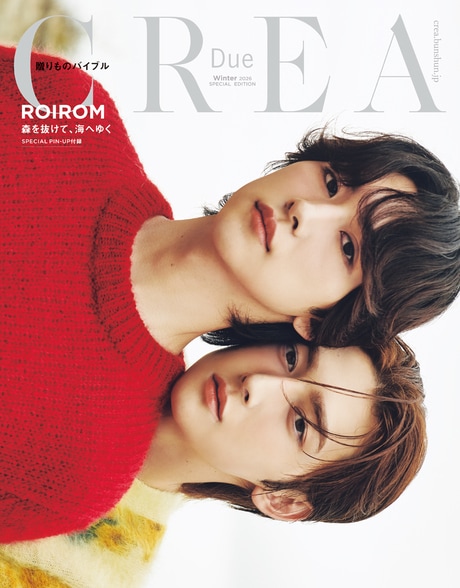昭和を生きた世代
昭和という時代は六十三年の長きに及び、そのうえ、敗戦が挟まっているので、一口に「昭和を生きた」と言っても、世代によって非常に違いがあります。なかでも特徴的な体験をした世代がいくつか挙げられると思います。
まず大正十(一九二一)年から十三年生まれくらいの世代です。大正十年生まれは、昭和十六(一九四一)年には二十歳になるのですが、おそらくこの世代が最も多くの戦死者を出しているはずです。
著名人でいえば、『私の中の日本軍』『ある異常体験者の偏見』などで軍と日本人への考察を著した山本七平が大正十年生まれ。戦争当時の日記(『戦中派不戦日記』)を公刊した山田風太郎、ルバング島で戦後二十九年間潜伏していた小野田寛郎、フィリピン戦線で死線を彷徨ったダイエーの中内功、マンガで優れた戦記も描いた水木しげるはいずれも大正十一年生まれです。大正十二年には『戦艦大和ノ最期』を書いた吉田満、戦車部隊で終戦を迎えた司馬遼太郎が生まれています。
その次の世代で際立っているのが、昭和五(一九三〇)~七年生まれです。半藤一利さんが昭和五年生まれで、日米開戦時に十一歳、終戦時に十五歳、東京大空襲にも被災しています。次は自分たちが戦場に送られる、いつ自分の住んでいるところが戦火にさらされるかもしれない、という意識で青春を過ごした世代で、後に作家、文学者になった人がとても多い。半藤さんをはじめ、澤地久枝(昭和五年)、秦郁彦(昭和七年)といった昭和史の書き手も生まれています。
以下、アトランダムに列挙してみると、野坂昭如、開高健、梶山季之、笹沢左保が昭和五年生まれ、有吉佐和子、小松左京、曽野綾子、大岡信、谷川俊太郎が昭和六年、石原慎太郎、五木寛之、青島幸男、江藤淳、小林信彦、平岩弓枝、小田実、高井有一、黒井千次が昭和七年生まれになります。大島渚、深作欣二、山下耕作、熊井啓、黒木和雄、篠田正浩などの映画監督も輩出していて、彼らには戦争をテーマとした作品も少なくありません。
- date
- writer
- category