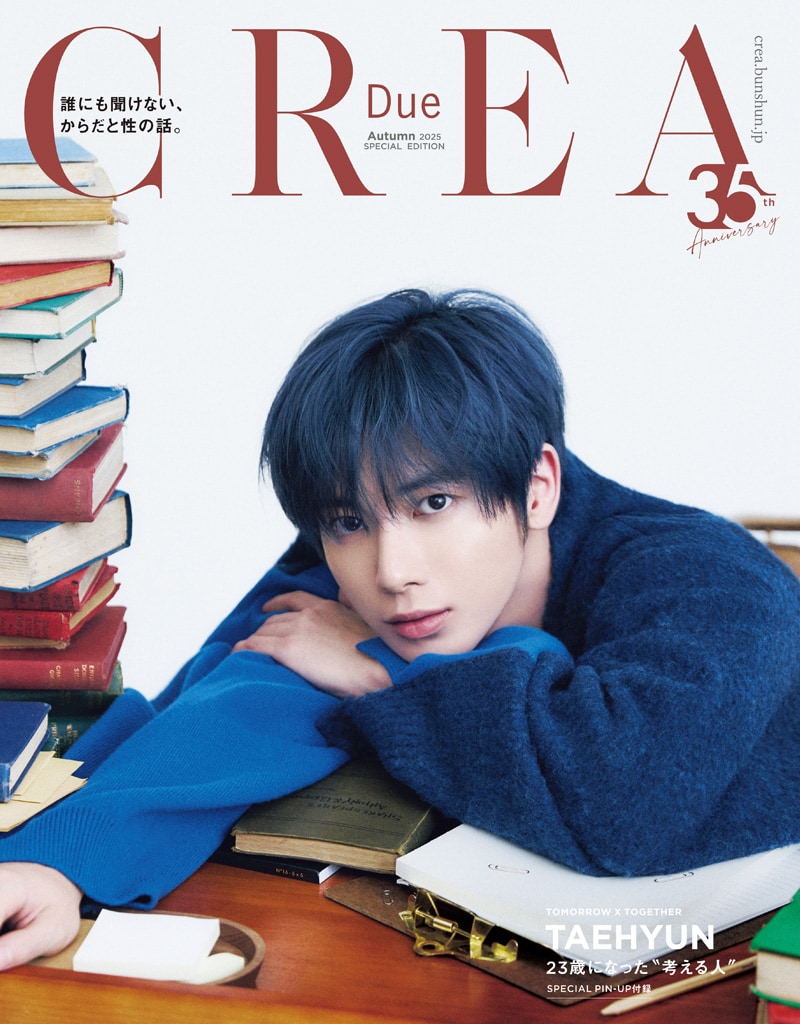慶子は、無言で語っていた。あらゆることにかかわらず、自分が幸せだったということを。告知せずにいたことを含めて、私のすべてを赦すということを。……その無言の会話が、いったい何分、いや何十分つづいたのか、私は覚えていない。そこには不思議に涙はなく、限りなく深い充足感だけがあった。(七八頁)
『妻と私』にこう記される、臨死状態に入った妻に寄り添う経験の際、江藤がかねて切望した「沈黙」に身を浸していたことはあきらかだろう。そうした状況で人が味わう独特の時間の感覚は、同書では「日常的な時間」に対する「生と死の時間」と名指され(初出は六六頁)、繰り返し登場する。しかし介護に疲労し敗血症に陥りつつあった江藤は、いつしかそれは単に「死の時間」でしかないのではと慄き、言葉を喪失する体験への誘惑と抵抗とのあいだを揺れ動くことになる。
「私のすべてを赦す」なる表現に込められた謝罪の対象は、まさか往年の殴打のみではないだろう。病名を告知しないという決断をはじめとして、人は他者を気遣いながら生きようとするとき、どうしても擬態しなければならない虚偽を抱え込む。四歳で母を喪った際、父親に吐かれた「治ったよ」との嘘がまさにそれだが、いまや江藤は夫であり家長である者として、生き続けるかぎりで嘘を吐く側に立たねばならない。
生きるとはその意味で、みずからの真情に対し不断に加えられ続ける「検閲」との格闘であり、だからその検閲は実は、敗戦とも占領とも関係がない。そうした検閲なしに生きることを許されるのは、そもそも内面を言語にする力を持たない乳幼児の段階のみだが、しかし江藤の場合、それは母の死によって断ち切られてしまう。
だから『妻と私』の脱稿後に書き起こされた『幼年時代』の冒頭で、江藤が亡くした妻と母を重ねるのは偶然ではない。人は言語なしに、批評なしに他者と生きてゆくことは、ほんとうにできないのか。検閲不在の境地が死ではなく、生につながる回路を、中途で断ち切られた自身の幼少期を復元することで探してみたい――。
それが妻と最期の時間をともに過ごした、江藤に浮かんだ一念だったと思う。
すでに諸賢の指摘のあるとおり、『幼年時代』の文章はどこかおかしい。誰の目にも江藤の自伝として映ることを前提にしながら、両親は江上堯・寛子(正しくは江頭隆・廣子)、本人は敦夫(正しくは淳夫)と、微妙に名前を変えている。「日本と私」の頓挫後に連載を始めた『一族再会』(単行本は一九七三年)と同一の主題で、そちらではすべて実名で著したのだから、いまさらプライバシーを気にするのも変だ。
- date
- writer
- staff
- 文=與那覇 潤(評論家)
- category