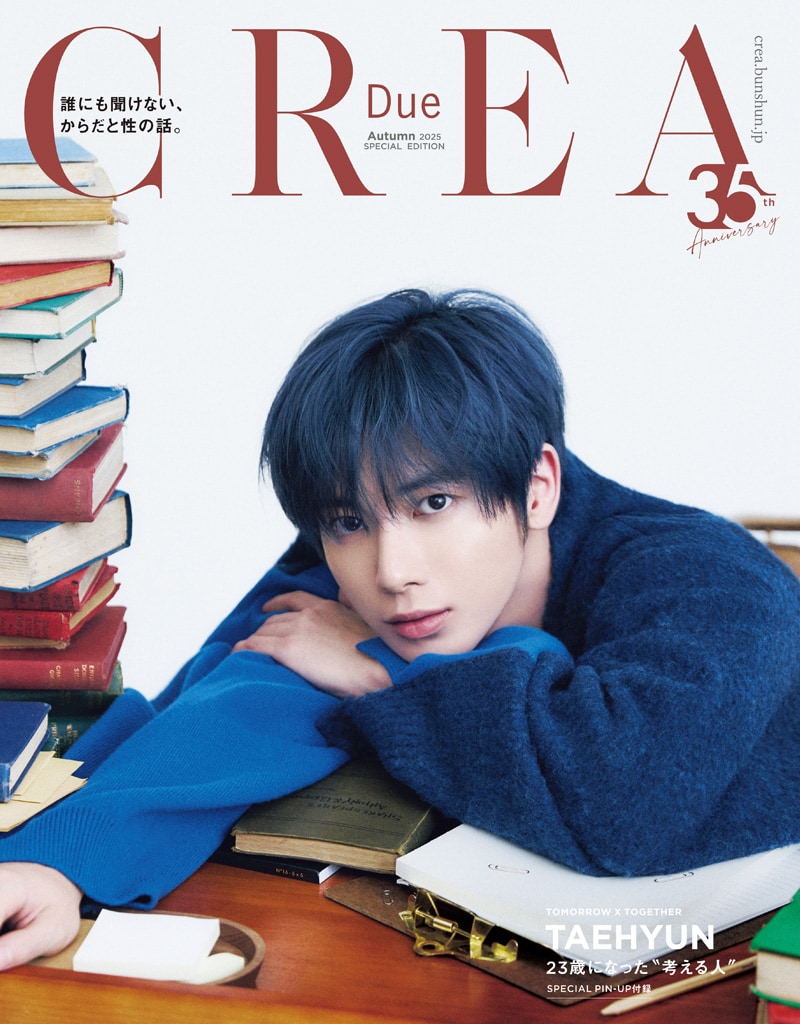「日本と私」はアメリカ風の個人主義になじんで帰朝した夫妻が、日本社会へと再適応できず葛藤する苦労話であり、その象徴として慶子夫人はじんましんに悩まされる。江藤は妻をかばいながら新居を探すものの、ついに「何年ぶりか」で彼女を殴ってしまう。映画鑑賞の後、江藤としては妻の疲弊ぶりを見てディナーを諦めたのに、慶子夫人が「疲れているのは本当は自分ではなくて私〔=江藤〕のほうであり、そういう私を自分が支えているのだとでもいうように」振る舞ったからという、率直に言って褒められない理由だ。
しかしこの身勝手で暴君的な夫は、なにをそこまで会食に求めていたのか。その告白は、卓越した批評家の筆になるものだけに、いまもひどく突き刺さる。
いわばそれはおたがいが一生懸命に生きているということを、ちょっとわきから眺め直してみるような行事だ。そこからみると夫も妻もおたがいに孤独な人間だが、夫は妻が、妻は夫がそうであることを知っていて黙っているので、この孤独にはあまりとげとげしたところがない。……
「まあ、なかなかよくやっているね」
その言葉はもちろん相手の耳には聴えない。聴えないが、だいたいそんなことをいっていることがおたがいにわかっているので、ふたりのあいだの沈黙には本当は言葉が充満している。(『江藤淳コレクション2 エセー』ちくま学芸文庫、四五五頁)
夫妻がともに「孤独な人間」だとさらりと書いているが、これが単に性格の問題を指すのではないことは、連載の中途、自身と慶子夫人の生い立ちを赤裸々に描く箇所から知れる。江藤は母親の結核のために実家から隔離されて育ち、葬儀のために「治ったよ」と嘘を吐かれて呼び戻された際には、「なぜか私は母が死んだことを完全に理解していた」。三浦家は家長が満州勤務の官吏だったことから、敗戦時は平壌で劣悪な収容所に入れられ、脱走して九死に一生を得たものの「小学生だった家内は毎日お葬式ゴッコをして遊んでいた」(同書、三六六・四一七頁)。
時代を考えれば大卒どうしのカップルというだけで知的な夫婦だし、実際に慶子夫人は夫の著作をイラストでも支える才女だった(『妻と私と三匹の犬たち』河出文庫)。しかし穏和な幼少期を奪われて育った二人の目には、戦後日本の社会はどこまでも壊れて見える。その違和感を言葉にすることで生き延びようと健筆をふるう批評家が、心底ではいかに言葉や批評なしでも安堵できる沈黙を欲していたか。
――生前は未刊に終わった「日本と私」で、江藤はそれこそを吐露していた。
四 自死と共存
- date
- writer
- staff
- 文=與那覇 潤(評論家)
- category