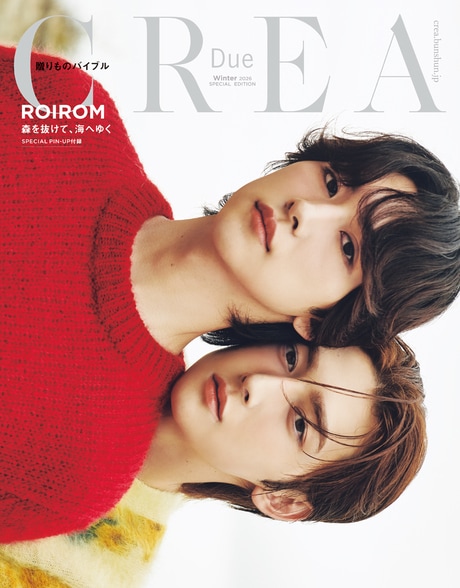1000年以上続く織物の産地である富士吉田にて、テキスタイルと芸術が融合した“布の芸術祭”である「FUJI TEXTILE WEEK」が12月17日まで行われています。
前篇では「アート展」の展示内容についてご紹介しましたが、今回は幻の織物とも言われる甲斐絹(かいき)をフィーチャーした「デザイン展」の様子をお届けします。
» 前篇はこちら
甲斐絹の歴史をたどる
テキスタイルは、糸や繊維が織り合わされて形成されているものですが、文化的・歴史的な意味やメッセージも内包しています。甲斐絹とは、山梨県の富士北麓・東部地域で1940年代まで作られていた織物。羽織の裏地として用いられてきました。
デザイン展「甲斐絹をよむ」では、この甲斐絹にフォーカス。アート展の会場となる建物が立ち並ぶエリアからは徒歩10分ほど離れたところにある、アートギャラリー「FUJIHIMURO」がその舞台です。

富士吉田にはかつて関東屈指の歓楽街として栄えた西裏地区があります。西裏の店に氷を提供するために開業していた富士製氷が、東京理科大学坂牛研究室の手で2019年にアートギャラリーとして生まれ変わりました。

現在では技術的に制作することが不可能な甲斐絹。なぜこの地で発展したのか、そこにどのような思いが込められていたのか。実は現存する資料が少なく、謎めいた部分も多いそう。
そこでデザイン展「甲斐絹をよむ」では、研究者、写真家、詩人を「読み手」に迎え、甲斐絹に込められた意味や思いを多角的に読み解いていきます。
贅沢を禁ずる江戸時代の奢侈禁止令などにより、着物の表地より裏地にこだわる「裏勝り」の文化が誕生。明治時代には、奥行きのある絵柄で表現され光沢美のある、物語性の高い裏地が人気を博したといいます。

こちらは日本全国から集められてきた甲斐絹の展示。当時の人々は羽織を脱ぐときにちらりと裏地を見せることで、おしゃれさをアピールしていたのだとか。表地と裏地の組み合わせを見ていると、1着ごとに着ていた人のプロフィールに想像が膨らんでいきます。

織機の上で折る直前に経糸だけに染めるという、世界でも類を見ない技法が用いられた「絵甲斐絹」は、個性豊かな絵柄がたくさん。
![「絵甲斐絹 西暦1913年[大正2年]南都留郡」江戸時代の金貨、大判金をモチーフにデザインされたもの。](https://crea.ismcdn.jp/mwimgs/1/1/1280wm/img_11b973f7fb81f4c61f0b9b2b0c7c45bb133836.jpg)
![「絵甲斐絹 西暦1913年[大正2年]南都留郡」こちらを見据える虎の迫力が印象的です。](https://crea.ismcdn.jp/mwimgs/8/a/1280wm/img_8a986607c9a5021f0a22e3f541e0dc7493528.jpg)
- date
- writer
- staff
- 文・写真=岸野恵加
- category