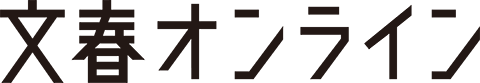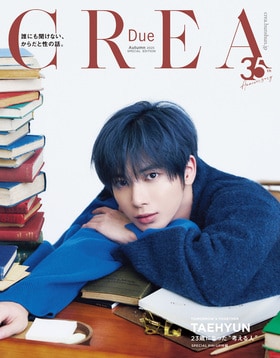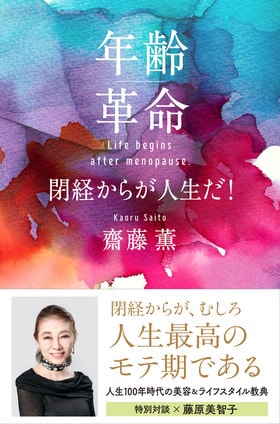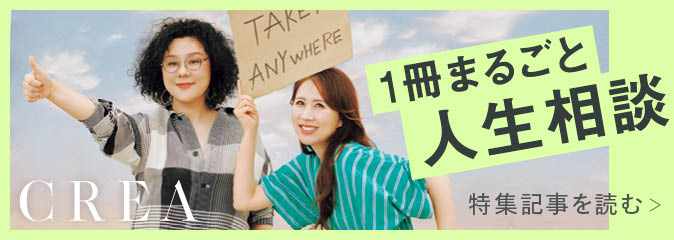結果的にこの作品は、特攻死を否定し、「生きる」ことを肯定する。かといって、この作品は戦後民主主義的な平和主義──つまり、55年体制的な護憲平和主義──なのかと言えば、それも違う。しかしやはり、述べたように、改憲・再軍備を指向するものでもない。それは、どう考えればいいのだろうか?
この作品は「民間」(国家ではなく私企業)による「日本」の再興の物語である──このように言語化してみると、この作品がいかにも時代遅れに思えてしまうのは私だけだろうか。『下町ロケット』や『プロジェクトX』的な、「ものづくりジャパン」へのノスタルジー。そのような夢が破れてしまった、もしくは破れつつあるのが、経済停滞にあえぐ今の日本ではないのか?
ここで私は、この作品における「民間」の人びとのプロジェクトを、『ゴジラ-1.0』という映画そのものへの自己言及とみなせると提案してみたい。つまりこの映画は、文化面における「戦後」を乗り越えようとする。文化面における戦後を映画に関して乗り越えるとは、すなわちハリウッドに伍することである。
そのような映画であるなら、私が否定したセンチメンタリズムやご都合主義は、むしろハリウッドの劇作法に、日本の文脈で忠実に従ったものとみなすことができる。その懐古的でナショナリズム的に見える内容も、じつのところ世界市場にこの映画を売り出すにあたっては、「日本的なもの」としてパッケージ化されたアイテムとみなすべきものである。
(ついでながら、そう考えると、冒頭の大戸島のは虫類的ゴジラは、ハリウッド版ゴジラへの皮肉な言及にも見えてくる。ハリウッドがやったことくらいは簡単にできますよ、という宣言である。)
「ゴジラ-1.0」はクールジャパンの夢を見る
すでに廃れつつあるように思える言葉を使うなら、この映画は「クールジャパン」の夢を見る。この経済停滞の中、コンテンツ産業において一矢報いたいという夢である。

グローバルな(ハリウッド的な)劇作法には背を向けて特殊日本的=庵野的な表現の濃度をひたすらに濃くした『シン・ゴジラ』に対して、『ゴジラ-1.0』は日本的な内容を、ハリウッド的劇作と表現でパッケージ化して世界に売り出している。
北米ではすでに1500館での公開が決まっているというこの作品は、まずはそのミッションに成功しつつあるようだ。この映画は、私たちに「戦後が終わった後」の夢の空間を見せてくれるのだろうか。
2023.11.22(水)
文=河野真太郎