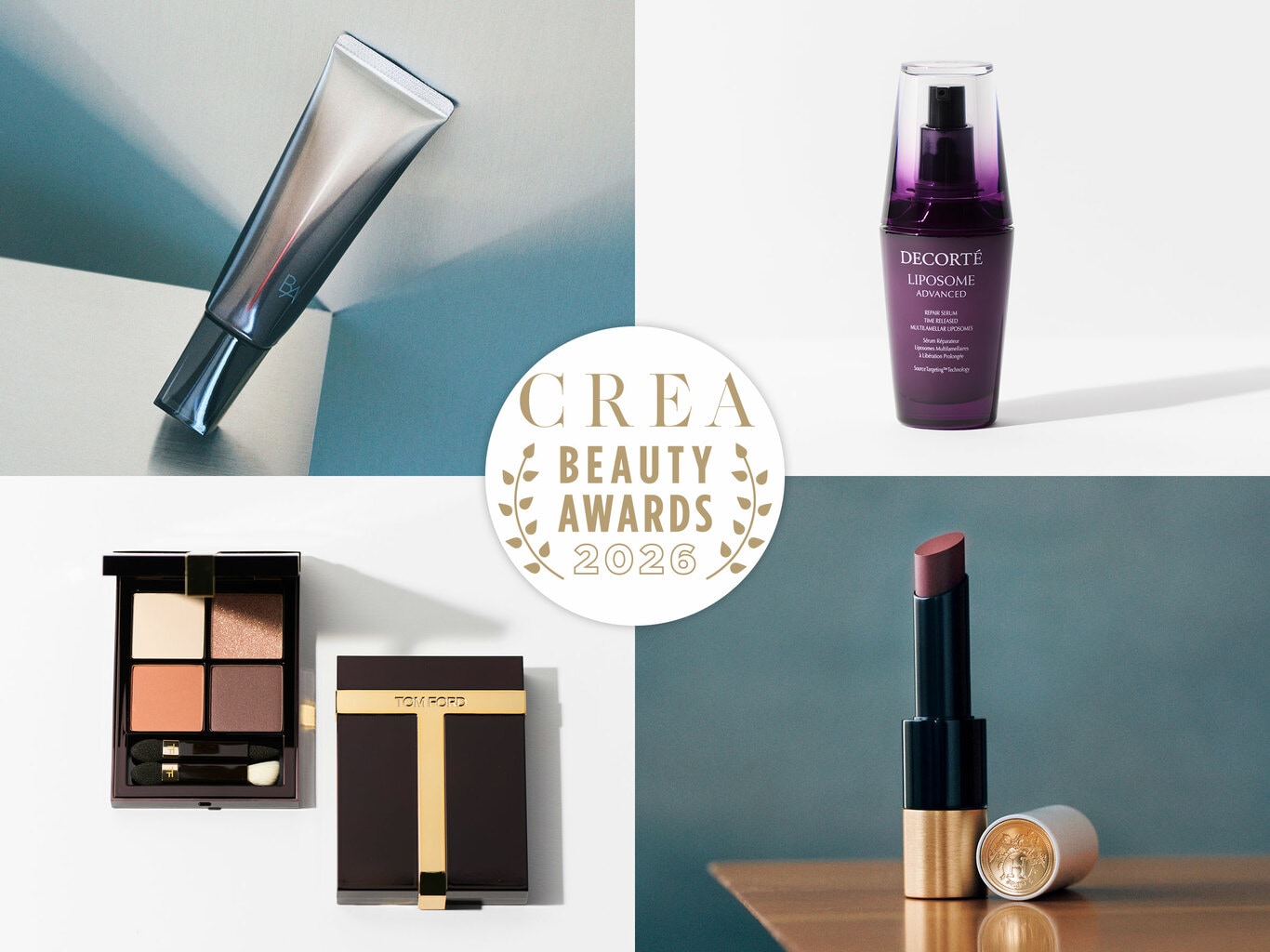「コロナ渦は娘たちの姿に勇気づけられた」

――ユリさんは玲奈に愛情を抱きながらも仕事に情熱を注ぎ、家族公認で不倫をする、強い自我を貫く女性です。玲奈はそんな母親に混乱しながらも理解しようともがく。よくある「毒母」とも違う、愛憎半ばする母娘関係がリアルで身につまされます。
私自身、父親以外の家族とは共有できない部分が多すぎて、特に母親に対しては価値観が違い過ぎたので、別の生き物として接するように棲み分けしてきたんです。だから家族でも理解できない部分があるのは当たり前だと思うし、両方にそれぞれの正しさとか理屈があって、自分とは違うと割り切っていても共存はできなくはないと思うんです。もともとわかりやすい善悪の対比は苦手ですが、今回は特に「毒親」という単純な悪者を作って、対立構造にしてしまうと一元的な話になってしまうので、お互いにどういう存在で、どういう生き方をしていて、何を理想としているかがちゃんと伝わるように書こうと思いました
――対立構造といえば、世の中にある母親像も昔は「良妻賢母か毒母か」みたいなものしかありませんでしたが、最近はより複雑に多様化してますよね。
今の30代~50代の母親像って、それぞれの家庭によって幅があると思うんです。母親が働いているかどうかも別れる世代だし、離婚家庭も多い。いわゆる現代的な核家族家庭でも雰囲気もルールもそれぞれに違う。家庭って本当に強烈な文化の違いがあるものだと思うので、そこは玲奈の友達の家庭に託して描きました。玲奈の友達に帰国子女がいるのも、同じ理由です。
――玲奈が仲良くなる、コンビニで働く中国人留学生の存在も印象的です。
私自身がパリに住んでいたとき、隣人の国籍も知らないような状態で、それがすごく心地よかったんです。相手の宗教とかルーツも知らないのが当然、という状態で生きていると、自分が何者であるかについても頓着しなくなる。肌の色とか人種では括りきれないものがあるということを実感しましたし、その一方で、雑多な人種の街の中に、それぞれの国のコミュニティがあるのを目の当たりにして、それを大切にする人々を自然に受容できた。だから今回も留学生という異分子が入ることで、玲奈が自分自身の異分子性に気付いたり、相対的なものの見方を身につけられたらいいなと思いました。
――本作はコロナ禍の物語でもあって、ティーンエイジャーの暮らしにコロナが大人以上に影響を与えている様子が描かれています。小説の中でコロナ禍を描いておきたい気持ちはありましたか?
ありましたね。この作品はコロナ禍に入ってから描き始めたんですが、あの頃はマスク付ける/付けない、ワクチン打つ/打たないといった不確定要素の中で、みんなが自分はどうしたいか突きつけられた時期でもありました。それを子どもたちと一緒に考えるような気持ちになってもらえたらいいなと。
――コロナ禍で子どもたちの青春が奪われたと言う人もいますが、玲奈とその友達たちはヘヴィな非日常を日常として謳歌しながら、いろんな問題を乗り越えてゆきます。その姿にたくましさを感じます。
そうなんですよね。コロナが始まったとき、うちの子は中学に入学した年で、入学式もないまま初めましての人たちとteamsで授業が始まって。でも投稿すればみんながマスクをしている状況の中でもどんどん友達ができて、ここまではOKでこれ以上はダメって、自分たちで考えながら遊んでる。そんな本能が漲った姿が眩しかったし、大人の私の方が勇気づけられたんです。
――コロナで経営悪化した友達のお店への思い、彼氏に束縛される親友との関わり方など、それぞれの「正しさ」が交錯する中で、玲奈は「複雑な感情に踊らされて、泣いたり怒ったりすることのない人生を送りたい」と願いながらも、必死で自分にとっての正しさを掴み取ろうとします。そんな十代特有のセンシティブな感情を、金原さんがここまでリアルに描けることも凄い。
私は多くの大人がするように、これはこうだと割り切って片付けることができないんです。日々いろんな問題が世界中で起こっていて、それに対して自分はどういうスタンスを取っていくか。常に考えてるし、それによって自分自身も変化し続けたい。常に宙ぶらりんな状態で今の状況と向き合って、自分はどう生きていくべきかを考え続けたい。それを小説に書くことが、私が社会と繋がっていられる方法だと思ってます。
文=井口啓子 写真=佐藤 亘