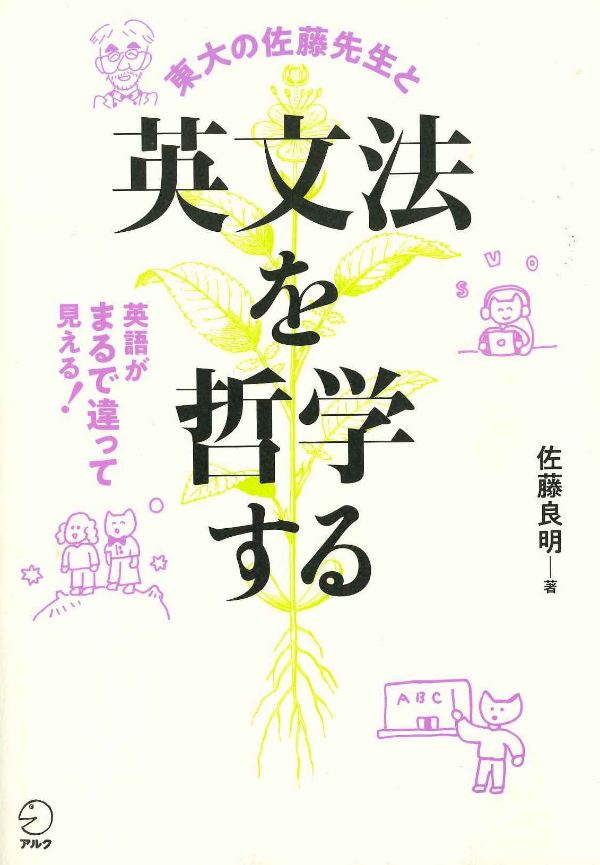
「私が長年かけて掴めるようになった英語の感覚と、世の中で行われている英語教育が、だいぶズレていることを実感したんです」
トマス・ピンチョンの小説『重力の虹』などを翻訳してきた東京大学名誉教授の佐藤良明さん。数年前、放送大学で英文法の授業を組んだときのことだった。
「中学の学習内容を踏まえた教材を作ったら、かなり難しいものになってしまったようで、学生の皆さんがあっぷあっぷしていた。そうか、習ったはずなのに身についていないんだ、と」
身につかないのは、英語の教え方、ひいては言語の捉え方が根本から違っているからではないか。今の教育を動かしている人たちに「『ぎゃふん』とはいかなくても、『ぎゃ』ぐらいは言わせたい(笑)」。そう思って上梓したのが『英文法を哲学する』だ。
群馬県高崎市出身の佐藤さんは、NHKのラジオ講座で英語の勉強を始めたという。高校生の頃、アメリカのハイスクールに1年間留学。そのとき「英語で考える」ことを強いられた。
「自転車に乗れない子供が無理やり乗せられたような毎日を送りました。自転車は漕がないと倒れてしまいます。ただ英語という乗り物は、日本語と漕ぎ方が違う。人前でスピーチをしたりして、その漕ぎ方こそが“文法”なのだという感覚を、知らず知らずのうちに身につけていました」
本書は英語教育の変遷をたどりながら、日本語から離れ、英語の仕組みを理解した上で「乗っかる」方法を解説していく。
たとえば、従来の「五文型」の代わりに、「do動詞の世界観」「be動詞の世界観」という2つのパターンで考えることを勧める。また、12種類と習った時制についても、新しい「二つの時制(テンス)」「三つの時相(アスペクト)」という捉え方が紹介される。
「時制は〈現在〉〈過去〉の2つ。話の内容が現在に即するのか、過去の物語なのかを区別します。時相は私の考えでは、〈完了〉〈進行〉〈未然〉の3つ。それぞれの動詞がそれぞれの位置で、どのように時間と関わっているかを表します。時制と時相に分けて考えるのは、今世紀の海外のまともな文法書では常識。でも日本の教育現場では、12種類のほうが教えやすいからなのか、まだ導入されていません」
2022.05.30(月)
文=「週刊文春」編集部





















