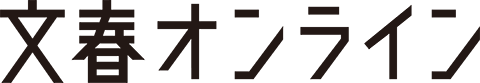フランスを一度離れてみて見えてきたことがある。人はみな一人ひとり、考え方も生き方も異なって当たり前で、その他者を尊重する姿勢がここフランスでは人々に刷り込まれているということだ。多様性を受け容れる、というと安易に聞こえるかもしれないが、環境も背景も民族すら異なった人たちが自分の信じたことや進みたい方向、権利といったものを得るためには時には闘いも辞さない覚悟がそれぞれにあって、裏返して言えば、そういう他者からたとえ自分に迷惑が降りかかったとしても尊重しようという寛容さにも通じている。

森喜朗元会長の発言が話題になって久しい。男女格差是正の政策がここ10年で急速に整備されたフランスでも、それは表面上だけという声もある。たしかに性差別反対の立場を取りながら、例えば遠回しに、または象徴などを用いて性差別的な発言をする人はいるし、セクハラや女性への暴力の問題はますます深刻になっている。
が、つくづく“平等”であることへの意識の高さに驚かされるのも事実だ。
男性は「働く男性」とはカテゴライズされない
例えば、私は先に「働く女性」と書いたが、その「働く女性」にあたる言葉はフランス語にはない。関係代名詞の主語、“qui”を用いて“les femmes qui travaillent”(働く女性)とは言わず、職場における男女不平等に関するという理由から、ただ“les femmes”(女性)と言うのだそうだ。
日本では「働く女性」がまだ大多数ではないからという視点より、男性は「働く男性」とはけっしてカテゴライズされないという視点に気づけなかった自分に愕然とする。と同時に、フランスでは言葉ひとつひとつにもフェアであることに心が砕かれてきたのを実感する。
男性が自身の発言を控えるのを“わきまえた男”とは言わない。“わきまえない女”でも“わきまえた女”でもなく、ただの女として自由に意見を出し合い、それが届く世の中になったら、私たちはどんなに生きやすくなるだろう。
先の森氏発言の件で問題を深刻にとらえた男性が多いと聞く。女性にとってフェアでないことを、男性に声を上げてもらう意義は大きい。こうした声がある限り、男性にとってフェアでないことや言葉ひとつひとつにも、目を凝らしていきたいと思うのだ。
◆ ◆ ◆

雨宮塔子さんの寄稿「フランスのジェンダー・ギャップ」は、「文藝春秋」6月号の「巻頭随筆」と「文藝春秋digital」に掲載されています。
2021.06.03(木)
文=雨宮塔子