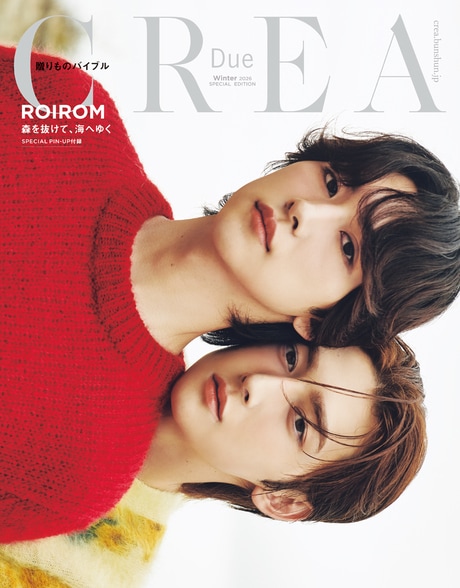2025年7月に待望の開幕となった『歌舞伎刀剣乱舞』の第二弾『歌舞伎刀剣乱舞 東鑑雪魔縁(あずまかがみゆきのみだれ)』。東京(新橋演舞場)、福岡(博多座)、京都(南座)の三都市で公演されます。
前篇では出演する俳優のバックボーンや演じる“刀剣男士”について、さらに見どころを解説しました。後篇では、囲み取材の様子やグッズ、そして歌舞伎ファンのライター・宇野なおみが実践している歌舞伎公演での“定番のお約束”を紹介します。
囲み取材で仲の良い様子を見せる俳優さんたち

最終リハーサルの後に行われた取材では、皆さん3時間20分に及ぶ舞台を完走したとは到底思えないなごやかな雰囲気。
若い俳優たちが話す折には、中央に立つベテラン・中村獅童さん、尾上松也さんが身を乗り出して、その様子を見守っていました(やや圧が強いきらいもあり笑)。

歌舞伎の世界では「お兄さん(先輩の俳優を指す)に教えてもらう」という文化が深く根付いています。初役を勤めるときは、その役を得意とする先輩方に教えを乞うのが習わしです。
それは連綿と続く伝統の継承であり、新たな世界へ後輩を後押しするということでもあります。
今回の『歌舞伎刀剣乱舞』の座組は、若い俳優や一般家庭出身の方たちが多く、皆さんキラキラと輝いていました。松也さんの歌舞伎の発展にかける思い、後輩への思いが伝わる舞台でした。
知っておけばより楽しめる「歌舞伎の基本・お約束」を解説
『歌舞伎刀剣乱舞』は、歌舞伎を初めて見る方でも十分楽しめる、現代のエンターテインメント作品です。しかし、同時に、歌舞伎400年の歴史で培われた数々の「お約束」や「見どころ」が織り込まれています。
知らなくても楽しめるけれども、知っていればより一層楽しめる、歌舞伎のお約束について解説します。
【1】主な演目の種類
歌舞伎をテレビで見かけたとき、「あれ? 普通に喋っている?」と思ったことはありませんか?
歌舞伎の演目は大きく分類すると「時代物」「世話物」「所作事」に分かれます。
武家や公家の社会の出来事や、江戸時代よりも前の出来事を描いた作品を「時代物」、庶民の生活を描いたものを「世話物」と分類し、「世話物」には朗々と謡うようなせりふはあまりありません。「所作事」は踊りを中心とした演目のことです。
「通し狂言」といって、一作を丸ごと上演する場合もありますが、大抵の場合、ひとつの公演では2~3の演目が上演されます。なので、歌舞伎の公演は休憩時間を含めると4時間ぐらいになることもよくあるんです。
【2】立役と女形
歌舞伎の大きな特徴として、女性の役も男性が演じることが挙げられます。女性の役を「女形(おんながた)」と言い、所作や声をコントロールして、女性を表現します。今作で言えば、尾上左近さんが倩子姫を、河合雪之丞さんが北條政子を演じているのがそれです。
基本的に女形は専門で演じる俳優さんが多いですが、例えば普段女形を勤める中村莟玉さんが、『歌舞伎刀剣乱舞』で髭切を演じているように、女形でも男形を勤めることがあり、それもまた楽しみのひとつです。
一方男性の役を演じる人を「立役(たちやく)」と言います。座って音楽を演奏する人を「地方(じかた)」と呼び、その前で立って踊る役者を「立方」と呼んだのがもとだそう。
皆さん、男前のことを「二枚目」と言いますよね? あれは歌舞伎の看板のことで、若くて魅力的な立役の名前がその二枚目に書かれていたことが由来なんだそうです。
【3】大向う
「〇〇屋!」と屋号を叫ぶ、客席からかかる声を「大向う(おおむこう)」と言います。大向うをかける人は「大向うさん」と呼ばれ、歌舞伎の公演には欠かせない存在です。
前篇の俳優解説で屋号もご紹介しましたが、松也さんなら「音羽屋」、獅童さんだったら、「萬屋」と声がかかります。
代目で呼ぶ、役者が住んでいる町の名前で呼ぶ、などのバリエーションもあります。なお、立役・女形のコンビとして有名なふたりが出てくると「ご両人!」という声がかかることもあります。
屋号や家紋は踊りで使う小道具の傘に書かれていたり、大道具の襖に書かれていたりすることもあるので要チェックです。