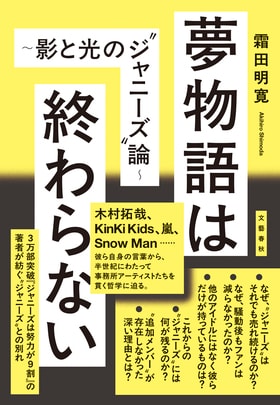「でも、長く楽家として栄えている家の出なんだから、生まれつき手の大きな、才能豊かな姫君が生まれてもおかしくはないんじゃないかな」
一方の倫は、奏者はうら若き乙女と信じ切っていた。熱っぽく語る姿には、彼女の楽才に心酔する勢いまでうかがえて、伶にはどうにも面白くない。
「奏している姿を見たわけでもないのに、よくもまあ、そう素直に信じられるもんだな」
「伶こそ何も見てないのに、よくもまあ、そう疑い深くなれるもんだね」
「俺達よりも若いのにあんな演奏が出来るなんて、天才でなけりゃあり得ないだろ!」
「じゃあ、彼女は真実、天才なんだろうよ」
いつまで経ってもこんな調子で、全くらちがあかなかった。
このままでは修業にも差し障りがあるのは明らかで、思いつめた挙句、双子は突拍子もない手段に打って出た。
つまりは、実際に姫が奏している姿を――御簾の内側を垣間見ればいい、ということになったのだ。
正式な楽人にもなれていない、下男同然の身でそんなことをしたと露見すれば、当然ただでは済まされない。最悪の場合、見習いとしての資格を剝奪され、母を悲しませることになると分かっていたが、どうしても好奇心には勝てなかった。
日中はいつも音が絶えない本邸ではあるが、夜になると見習いや楽人達は明日に備えて休むため、しんと静かになる。そうなると、ゆったりと演奏をするのはあくせく働く必要のない貴族身分の者だけになるから、耳を澄ませば、長琴の音を特定することは可能だと思われた。
それが聞こえないかと意識するようになった三日目の夜、とうとう、風に乗って届くかすかな長琴の音を捉えた。
実際、浮雲のものとされる長琴の音はずば抜けて響くものであったから、耳のよい双子にとって、それを追うのは決して難しくはなかった。遠くから響いてくる長琴の音を頼りに、屋敷の警護の兵に見つからないよう、身を隠しながら邸内を行く。
同じ東本家の敷地内とはいえ、外教坊と本家の者が生活する寝殿は遠く離れていたから、随分と長い道に感じられた。
2025.01.16(木)