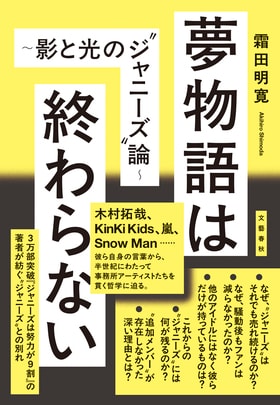月の明るい晩である。
思いのほか影が伸びることに気付いて焦ったものの、音に近付いていくのを実感している分、恐れよりも興奮が勝った。
相変わらず、聴く者の心を強烈に惹きつけて止まない演奏である。
前栽の陰に隠れるようにしてようやくたどり着いた離れでは、幸か不幸か、少しだけ御簾が巻き上げられていた。差し込む月明かりに、長大な琴と、それを奏でる手元だけが照らし出されている。
綺麗な、白い手だ。
想像していた通り指は長かったが、あのはっきりとした音のまま一曲を弾きこなせるとは思えないほど、跳ねるように弦を爪弾く指先は細くたおやかである。伶は、男のように大きく筋肉のついた、胼胝だらけの手を想像していた手前、なんとも女性らしい繊手に思いのほか動揺してしまった。
顔は見えない。だが、今、そこで長琴を奏しているのが、若い女であることは認めざるを得なかった。
御簾のうちから響く音はとろけるようで、聞いているうちに、ここに来るまでは皓々として恐ろしくさえあった月の光が、急に神聖なもののように感じられてきた。
そうしてぼうっと聞き惚れていた伶は、隣にいた倫がゆっくりと立ち上がったのに、すぐには気付くことが出来なかった。
月光と長琴で構成された穏やかな夜の世界に、急に鮮烈なきらめきが走る。
驚いて顔を上げた伶のすぐ隣には、誰に見つかっても構うものかと言わんばかりに、仁王立ちで竜笛を奏でる弟の姿があった。
一瞬、長琴の主は驚いたように手を止めたが、闖入して来た竜笛が自分の演奏に合わせたものであると気付くや否や、すぐにその動きを再開した。
長琴は、合奏を企図して作られたものではない。
それなのに、倫の竜笛は長琴を邪魔することも、しかしその音に負けることもなかった。明確に主張したまま絡み合い、まるで花祭りの晩に出会い、踊る男女のように足取りを合わせ、音は天へと昇っていく。
2025.01.16(木)