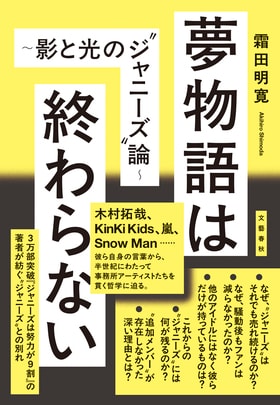その音はまるで、艶然と咲き誇る梅を容赦なく吹きこぼしてゆく春風のようでもあり、満ち足りた天上の世界から溢れて出た、光そのもののようでもあった。
――それ一面で、神楽のための一編成に匹敵する音。
なるほど、これが長琴かと、感嘆せずにはいられない。
堂々としているのに、不遜な部分はまるでなく、奏者自身が演奏を楽しんでいるかのような余裕さえ感じられる。
最後の一音の余韻が空気に溶けて消えるまで、誰も彼もが動きを止め、うっとりと聞き惚れていた。
演奏が終わった後も、しばし、声を発する者は誰もいなかった。
「見事なり!」
静寂を破って最初に声を上げたのは、東家当主その人であった。
それをきっかけに、宴に集まった人々は目を瞬き、まるで夢から覚めたかのように顔を見合わせた。徐々にさざなみのような興奮が沸き起こり、口々に御簾内の奏者を褒めだす中、伶はただただ呆然とその場に立ち竦んでいた。
「いやはや、素晴らしい演奏だった。今の奏者は、一体どなたかな」
にこにこしながら東家当主が問うと、中庭の梅の古木を挟んで、反対側に下ろされた御簾がわずかに揺れる。
「お褒めにあずかり、嬉しゅうございます」
控えめに喜びを示したのは、小鳥のように高く澄んだ少女の声であった。
「わたくしは、東清水の浮雲と申します」
* * *
時をおかずして、東清水家の浮雲は登殿に備え、正式に東本家の姫として迎え入れられた。
梅花の宴以降、双子の話題は、もっぱら本邸にやって来た浮雲の姫君のことばかりであった。
「音域からして、長琴がかなり大きいのは間違いない。手の大きさは、努力じゃどうにもならないはずだ」
「だから、替え玉だって言うの?」
「そうとしか考えられないだろ」
伶は、あの演奏をしたのが少女だとはどうしても信じられなかった。
ただの箏を演奏するだけでも、相当に体力が必要なのだ。
年端のいかない小娘がそれ以上の大きさのものを簡単に弾きこなせるわけがなく、御簾の裏側では、熟達した技術を持つ女房を代理に立てていたのではないかと疑っていた。
2025.01.16(木)