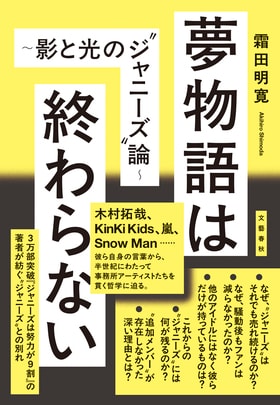話に聞くことはあれど、双子も長琴を間近で耳にするのは初めてである。そして、御簾内から聞こえてきた演奏に「なるほど」と得心したのだった。
音階が特殊で、高低の幅が異様に広い。
長琴は、姫を際立たせるためのものであって、他の楽器と合奏することはほとんどない。それひとつでどれだけ華やかな音が奏でられるかが肝というだけあって、どんどん弦が増え、構造が複雑化していったのだろうことは想像に難くなかった。
おそらく、この日のために相当練習をしてきたのだろう。
どの姫も年の割に上手だな、とは思う。だが、日頃一流の奏者に囲まれ、音楽をこれひとつと定めて生きている身からすれば、どうしても物足りなさが勝る。
つまりは、巨大化し難易度が高くなっていく長琴に、姫達の手の大きさも体力も、全く追いついていないのだ。
御簾の内側では年端のいかない娘達が息を荒げ、青い顔で演奏しているのが目に見えるようで、どこか憐れでさえあった。
伶がこっそり上座を窺うと、この宴席を設けた東家当主とその嫡男は、隣り合ってよく似た微笑を浮かべていた。微笑ましげに演奏を楽しんでいるように見えなくもないが、宴が始まってから一切表情に変化がないあたり、彼らにとってもあまり思わしい状況ではないのかもしれない。
これじゃ、長琴の演奏で若宮の心を射止めるなど、夢のまた夢だな。
溜息をつくと、近くで酌に勤しんでいた倫が似たような苦笑を向けてきた。考えることはどうせ同じだと思った、その瞬間だった。
突風のような音が吹き荒れた。
けだるげにしていた客人も、そつなく酒をついで回っていた下男も、その場にいた全員がハッと息を呑んで御簾へと目をやった。
一瞬、何の音なのか伶には理解出来なかった。
それほどまでに、これまでの演奏とは明らかに質が異なっていた。
連なる音はなめらかで、拙さを感じる部分はどこにもない。
一音一音が粒立ち、豊かな余韻は響きあい、耳から入って腰が抜けるかと思うほど、甘い震えを聴衆にもたらした。
2025.01.16(木)