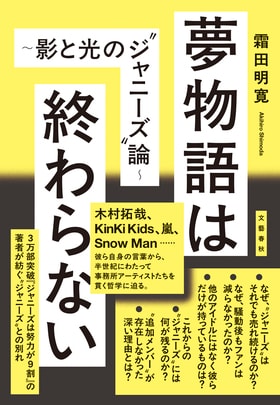「は……」
あまりのことに言葉が出ない伶を見て、先輩の楽人が苦笑する。
「若宮が一番気に入っていたのは東家の姫だったから、南家の姫は面白くなかったんだろう。さっさと宮中から追い出しにかかったようだぞ。東家としても、若宮の正室が決まっちまった以上、南家を刺激したくなかったってところかな」
想像していた以上に、登殿の儀は壮絶なものであったらしい。
――倫がいる東本家本邸に、浮雲の君が戻る。
一介の下男となった弟とかの人が関わりを持つとも思えなかったが、ふと、楽によって、言葉がなくとも通じ合っていた二人を思い出した。
本来であればあり得ないことではあるが、あの二人に限って言えば、あり得ないことでもないのかもしれない。
一度そう思うといてもたってもいられず、しばらくしてまとまった休暇を得た伶は、約一年ぶりに東領へと帰還した。
「おかえり、伶。元気そうで何よりだよ」
城下町で、大喜びの母と共に出迎えてくれた弟は、中央へ向かう自分を見送ってくれた時の憔悴ぶりが噓のように穏やかな顔つきとなっていた。
今でも竜笛は手放さないそうで、里帰りのお祝いに、と笑い含みに奏でてくれた音を聞いて驚いた。
倫の奏でる音は、雅楽とも、俗楽とも言えなかったあの頃とは、全く異なっていた。
朝廷の音楽とは明らかに系統が違うが、感情を表現する音楽としては、非常に完成されていたのだ。明るくのびのびとした、これもやはり天才の音というにふさわしい音である。
「実は、最近じゃ宴席に呼んでもらうこともあるんだ。珍しがられているんだろうけど、もしかしたら特例で、東家のお抱えとして認めてもらえるかもしれない」
「本当か!」
「ああ。この間は、お館さまからも直接お褒めの言葉を頂いたんだ」
やや照れくさそうに言う弟に、「良かったなあ」と伶はしみじみ返した。
浮雲とのことは訊けなかったが、倫の幸せそうな顔に、ひとまず胸をなで下ろしたのだった。
再び朝廷に戻った伶は、任せられる仕事が増えたこともあり、それからしばらくの間、東領へは足が遠のいていた。
2025.01.16(木)