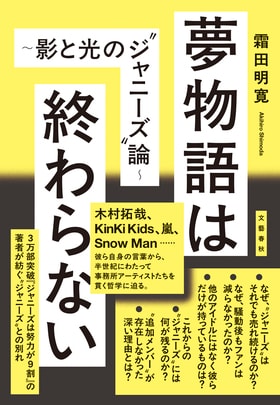「納得がいきません」
叫ぶ伶に、しかし、周囲の目は決してあたたかくはなかった。
結局、弟は自死であったということは覆らぬまま、埋葬されることになった。
「あの子は、別邸のお姫さまのことを、お慕いしていたから」
記憶の中にあるよりもすっかり小さくなってしまった母は、まだ土の湿った墓前で背中を丸め、ぽつりと呟いた。
「最近、別邸に中央から貴公子がお忍びで通っているという噂があったんだよ。もしかしたらそれで……それを、気に病んじまったのかもしれないねえ……」
身の程も考えずに馬鹿な子だよ、と囁いて泣きじゃくる母に、伶は何も言うことが出来なかった。
しかし不幸は、それに留まらなかった。
母を中央に連れて帰って三月後には、伶は上役から、西領の寺社へ向かうようにと告げられたのである。
愕然とした。
あろうことか、母親と一緒に西領へ向かいなさい、と上役は言ったのだ。
祭りに際しての派遣という名目ではあるが、その命令は、明らかに帰還を前提としたものではなかった。過去に、問題を起こした楽士が同じように厄介払いされたのを目にしたことはあるが、伶に思い当たる節は何もない。
何故かと食い下がる伶に対し、中央にやって来てからこれまで、親身になって世話を焼いてくれた上役は小さくこう言った。
「お前自身のためだ。もう、中央にも、東領にも戻って来てはいけない」
――到底、尋常ではない。
「一体、何が起こっているんです」
しかし、上役はそれ以上、何も言ってはくれなかった。
伶の疑問は尽きない。
何故、弟は死ななければならなかったのか。
何故、自分が東領はおろか、中央からも追い出されなければならなかったのか。
しかし、その時の伶には、命令に従うほかに出来ることは何もなかったのだった。
* * *
「あんた、本当に厨人なの? 包丁が全然手に馴染んでいないじゃないか」
いつでも手に持って慣らしなさいよとからかわれた伶は、ぐっと唇を嚙んだ。
2025.01.16(木)