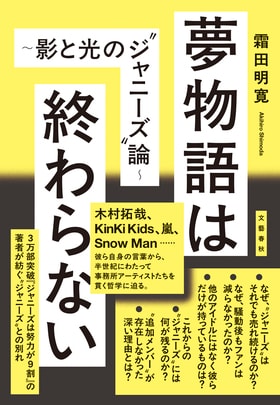倫は泣いた。身を振り絞るような、苦しい泣き方であった。
「伶。やっぱり、俺にはこの変わり果てた音が愛しく思える。そう思ってしまえる時点で、きっともう、手遅れだ」
「倫!」
馬鹿野郎、と伶は叫んだ。
彼女はあの一曲で、倫にはもう、もとの音が出せないと分かってしまったのだろう。だからこその慰めの曲であると思えば、見限られたような気がして、伶は猛烈な怒りを覚えた。
弟をこんな風にしたのは、あの女なのだ。
目を覚ましてほしいという伶の想いは届かなかったし、彼女が同調したのは、自分ではなく弟の恋心だった。
やはり自分には到達し得ない次元で、この二人は通じ合っている。
悲しい。悔しい。
そして、天才の弟を堕落させた、彼女が憎くて仕方がなかった。
* * *
倫が、再びの合奏を求めることはなかった。
浮雲の君はつつがなく登殿の儀を迎え、中央へと去っていった。
才試みで倫は落ち、代わりに伶が召人として、皮肉にも中央へ向かうことになった。
「これで良かったんだ」
寂しそうに笑った倫は、見習いの身分のまま、東本家の下男となって働くつもりらしい。
楽士としての資格を得たとはいえ、その中でも伶はまだまだ下っ端である。身を立て親族を呼び寄せられるようになるまでは、母も倫に任せることになった。
中央の流儀にならい、めまぐるしく働く一方で、伶は密かに登殿の様子を気にしていた。
宮廷の楽士ともなれば、少なからず若宮の后選びの詳報も入ってくる。あの奇跡のような美貌と才能に恵まれた女が、風流人だという若宮に気に入られないわけがないと思っていた。
「浮雲の君が、東領にお戻りになる?」
だからこそ、それは意外な報であった。
それまで、四家の姫の中でも浮雲は最も覚えがめでたいという噂を聞いていた。一体、何があったのか。
「どうも、南家の姫に一杯食わされたらしい」
「南家」
「おっかない女傑だそうで、若宮を押し倒して、無理やりお子を身ごもっちまったんだと」
2025.01.16(木)