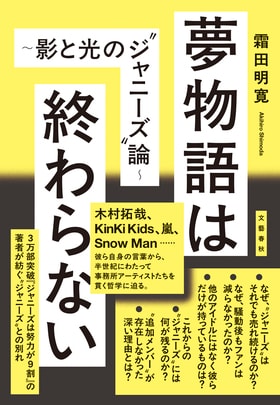でも、このままではいけないのも分かっている、と洟を啜る。
「もう終わりにするよ。最後に、あのひとにお別れをさせてくれ」
その言葉が倫のほうから出てきたことに安堵し、伶は静かに弟の肩を抱いたのだった。
その夜、見つかるのを覚悟で、二人は浮雲の君の居室の近くまでやって来た。
ただし、言葉を交わしている所を見咎められては言い訳のしようがないので、築地塀を隔てたところで、倫は竜笛を奏でることにした。
倫は、それで十分あのひとには伝わるはずだと確信を持って言い切った。
いつかよりも、ずっと月の冴える晩である。
月明かりの中、涙を流しながら奏でる倫の竜笛は、やはり、すっかり春のものから変わり果てていた。
山をたった一匹で歩む、牡鹿の求愛の声のような物悲しさ。
恋焦がれ、しかしどうしようもない苦悩と嘆きが籠もった音は、最初にここで演奏したものとは程遠く、笑えてしまうほど卑俗な響きをしていた。
しかし同時に、鳥肌が立つほどの凄みがあった。
伶の愛した倫の竜笛ではないが、これもまた、倫の音なのだろう。
これを聞いて、浮雲の君は何を思うのか。
どうか超然とした音を返して欲しいと、祈るような心持ちで、伶は彼女の応えを待った。目を覚ましなさい、自分にはその想いに応じるつもりはないという、はっきりとした意思表示が欲しかった。
沈黙が続いて、しばし。
息を凝らして待つ双子のもとに返って来たのは、場違いなほどに明るい音だった。
伶は息を呑み、倫はその場に崩れ落ちた。
彼女が返して来たのは、宮廷の神楽とはほど遠い、民草の間で流布しているような音楽であったのだ。しかしそれは、師匠のように「俗楽だ」と切り捨ててしまうには、あまりに素朴であたたかな音色をしていた。
――正道のものとはかけ離れているかもしれないけれど、その音も、私は好き。
伶の耳にも、はっきりとした浮雲の声が聞こえた気がした。
それは明確な、彼女からの慰めであった。
2025.01.16(木)