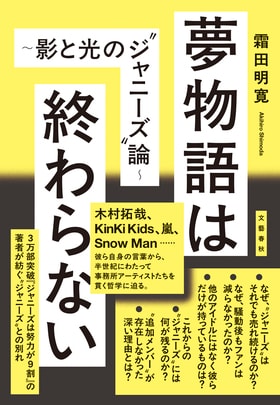初秋の頃、その変化は唐突に訪れた。
いつも通り稽古をつけてもらっている最中のことだ。師匠の鋭い声は、伶ではなく、倫に対して発せられた。
倫自身は、師匠に何を言われているのか分からずポカンとしていた。その変化を如実に感じ、ひやりとしていたのは伶のほうだった。
これまで、静謐で犯しがたい清らかさを持っていた、倫の竜笛。
その音色が、濁った。
春の終わり頃から、時折、音がいつもと違うように聞こえることがあった。気のせいかとも思っていたが、ここに来て、どうにも誤魔化しようがないほどに、音に変調を来たしたのだ。
指摘され、困惑の色を浮かべていた倫は、何度か指摘された箇所を繰り返すうちに、ようやく自分の変化を自覚したらしい。サッと青くなった倫に、「気持ちの問題じゃないのか」と、いつかの意趣返しをしてやる気には、到底なれなかった。
自分のそれよりも、倫のほうが遥かに深刻であると、分かってしまったからだ。
それ以降、音の変化は如実で、他の楽器との合奏の際、周囲の者がぎょっとするほどであった。
――天地を結ぶ音が人の心を動かすことがあっても、奏者の心が音に乗ってはならない。
倫の音は卑俗になった。高尚なそれではなくなってしまったのだ。
「原因は分かっているだろ、倫」
二人きりになった外教坊の裏手で、伶は、他の者には聞こえないよう声を潜めて倫を諭した。
「お前、夏中山に通いつめていただろう。もう、山での合奏は止めるんだ。遅れた拍子に合わせる変な癖がついているし、音に感情が乗り過ぎている。今ならまだ戻れる」
凡人の嫉妬と思われても構わなかった。ただひたすらに、倫の奏でる音を失いたくはないと思った。
皮肉にも、ここに来て伶は、自分は純粋に、弟の竜笛を愛していたのだと気付かされたのだった。
「あのひとは、俺が好きになってはいけないひとだった」
血の気のない顔で、倫は苦しく呟いた。
「最初から叶わない恋なのは分かっているのに、恋をしてしまった。あのひとが自分の音に応えてくれるのが嬉しくて……何よりも、生き甲斐になってしまったんだ。それに、ああ、どうしよう伶。正直、今の俺には、この変わり果てた音も好ましく感じられるんだ」
2025.01.16(木)