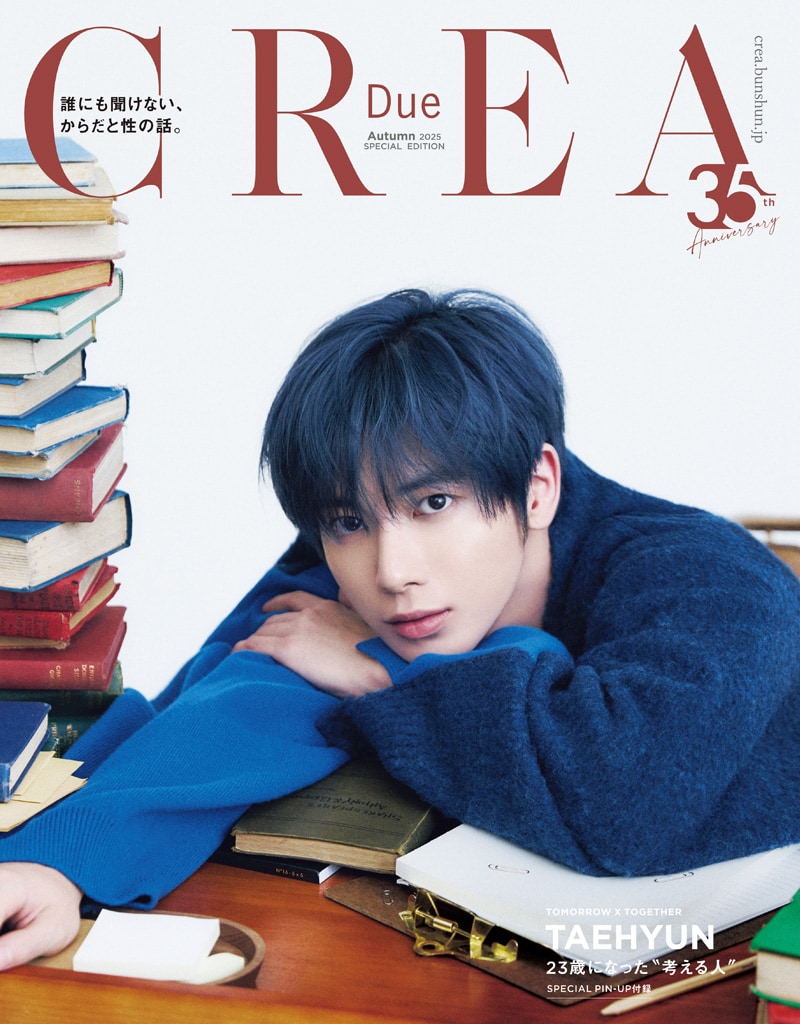小説に流れる時間は、戦中と戦後、そして少し時間を隔てて東京オリンピックのあった年になる。宮城県の農村が舞台で、近くに軍事目標もないらしい地方の「戦中」は、終戦の前の年であっても、比較的穏やかな日々として描写される。B29は飛ばないし焼夷弾も降らない。たった一回の、敵機による機銃掃射が印象的に描かれるが、その他は、国民学校の記述に戦時らしさがあるくらいだ。
昭和十九年の描写の中でも印象的なのは、章タイトルにもなっている秋の山の美しさ。「カエデの紅、ミズナラの黄金、ブナの橙、アカシデの朱、コシアブラの白銀――」、「山一杯に、祭りのぼんぼりが灯っているよう」と描かれる山の錦は、いまも変わらず美しいのだろうか。主人公の良彦(よしひこ)は、その夢のように美しい秋の山の只中を走る線路の向こうに、真っ黒に口を開けるトンネルを見てたじろぐのだが。
終戦二年後に描かれるのは、田んぼにのたうつ泥鰌(どじょう)だ。戦後の農地改革の影響で荒れてしまった土地の姿に言及されるものの、元気のいい良彦が、誰に教わるでもなく大量に捕獲し、家族の食卓に供する泥鰌は、やはり強い生命力を感じさせる。そのさらに三年後の章タイトルになっているのは薯蕷(とろろ)だが、考えてみれば泥鰌も薯蕷も、そして秋のきらびやかな山も、自然というものの強さの象徴ともいえる。人が愚かしい戦争に振り回されていても、変わらずそこにあり、傷ついた者たちに力を与えるのは、そうした自然の強さなのだろう。
それ以外に、際立って印象的なのは、女ながらにして一家の長であった多嘉子(たかこ)の野辺送りの場面だった。前日の準備から始まって、白装束に三角布、鉦(かね)と撞木(しゅもく)、北風に葬儀旗がはためき雪が降りしきる中を、粛々と葬儀の列が進む。「墨絵のような眺め」のその光景は、脳裏に美しく刻まれて離れない。
東京オリンピックの年の逸話に挟まれた、この戦中戦後の家族の物語は、昭和十九年、二十二年が良彦の視点、二十五年が良彦の母・寿子(ひさこ)の視点、そして二十六年が良彦の父・良一(りょういち)の視点から紡がれる。東京で中学の教師をしていたのに、生徒たちに「この戦争に日本は勝てる見込みがない。だから、未来のある諸君は、断じて戦争にいくべきではない」と言ってしまって、それが原因で職を失い、故郷に帰ったという良一。「神経症」を患い、「非国民」と呼ばれもした良一が、なぜそうした行動に出たのか、その謎が明かされるミステリーとしても、読み応えのある小説となっている。
- date
- writer
- staff
- 文=中島 京子(小説家)
- category