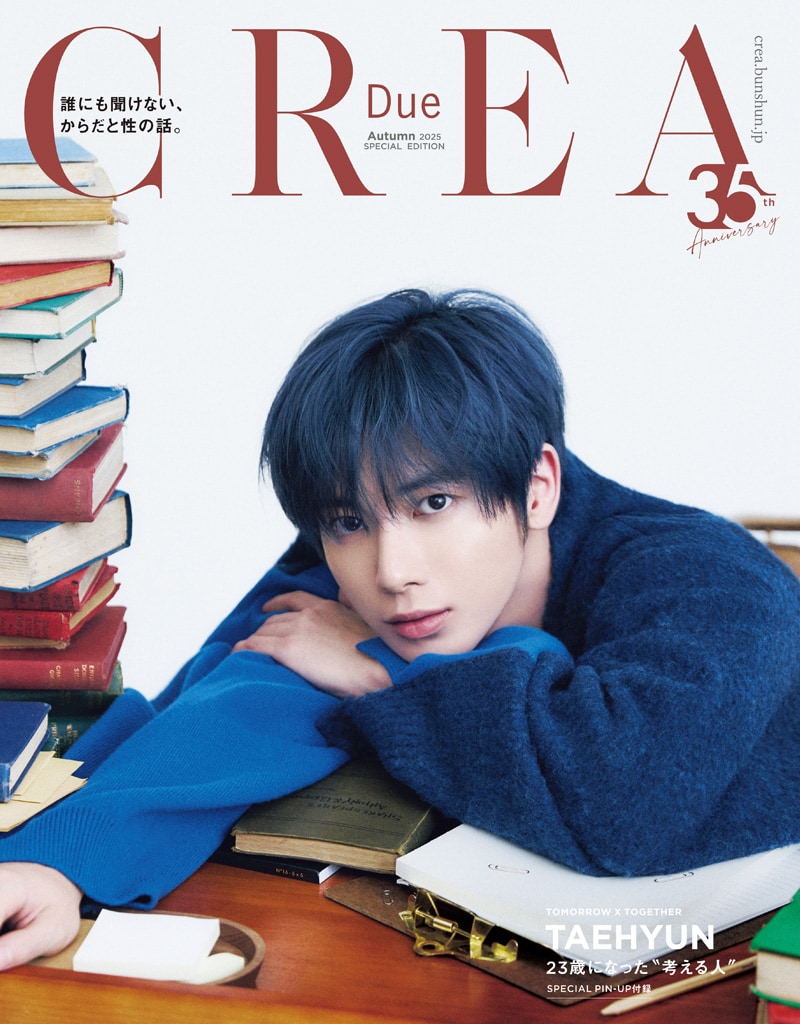李琴峰は台湾出身。十五歳のときに独学で日本語を学びはじめ、大学と大学院で日本文学や日本語教育学を専攻し、二〇一三年より日本で暮らしている。二〇一七年に「独舞」(のち「独り舞」に改題、二〇一八年、講談社、のち光文社文庫)で群像新人文学賞優秀作を受賞し、作家としてデビューしたのちは、二〇一九年に「五つ数えれば三日月が」(同、文藝春秋)で初めて芥川賞の最終候補に挙がり、二回目のノミネートとなった本作「彼岸花が咲く島」(二〇二一年、文藝春秋)で二〇二一年七月に石沢麻依「貝に続く場所にて」と共に受賞を果たした。ちなみに同年には『ポラリスが降り注ぐ夜』(二〇二〇年、筑摩書房、のちちくま文庫)で芸術選奨新人賞も受賞している。
こんなふうに羅列してみると、いかにも作家として順調なキャリアを積んでいるという印象だが、むしろここで強調しておきたいのは独学で日本語を学びはじめたという点――李自身の言葉を借りれば「自らの意志で日本語を学び」「自らの意志で日本に移り住んだ」という点のほうだ。
台湾の地方出身者であり、女性であり、性的少数者であり、在日外国人。マイノリティの属性を示す複数の記号を外部から否応なしに押しつけられてきた李は、「生きているだけで常に様々な隔たりを感じている」とエッセイ集のあとがきのなかで語っている。李にとっては、そうした「隔たり」に穴をあけてくれる可能性を湛えているものが言葉であり言語なのだ。
国籍というのは閉じられたもので、所定の条件を満たし、所定の手続きを踏まえ、所定の審査を通して初めて手に入るもの。新しい国籍を取得するためには古い国籍を放棄する必要がある場合もある。しかし「語籍」は開かれたもので、誰でもいつでも手に入れていいし、その気になれば二重、三重語籍を保持することもできる。国籍を取得するためには電話帳並みの申請書類が必要だけれど、語籍を手に入れるためには、言葉への愛と筆一本で事足りる。国籍は国がなくなれば消滅するけれど、語籍は病による忘却か、死が訪れるその日まで、誰からも奪われることはないのだ。
(「日本語籍を取得した日」早川書房『透明な膜を隔てながら』所収)
誰でもいつでも手に入れていいし、誰からも奪われることはない――「語籍」とは言い得て妙だ。「日本語文学」の担い手として、多言語を生きるひとりの人間として、李のありようを実に的確に示している。してみれば本作における〈ニホン語〉という言語自体が、李の考える「楽園」の体現だとみることもできるだろう。ひらがな、カタカナと漢語、おそらくは日本語中国語台湾語しまくとぅば(島言葉)の要素が混ざり合ったその言語に最初こそ面食らった読者も、本を閉じるころにはすっかり親しみを覚えているはずだ。その豊かで煩雑な過程こそが「他者を受容する」ということでもある。
デビュー作「独舞」では「死」という言葉を生のエネルギーに見事に昇華してみせた。『ポラリスが降り注ぐ夜』では日本の小説のなかで不可視化されてきたクィアの女性たちの群像を緻密に描き出し、新疆ウイグル問題に果敢に切り込んだ「星月夜」(二〇二〇年、集英社、のち集英社文庫)では、ともすれば塗りつぶされてしまう声を繊細に誠実にすくいあげた。ついでにいっておくと、本作のなかに〈女語〉のテキストとして登場する文章は李の「五つ数えれば三日月が」の一節だ。
李琴峰は誰からも奪われない/奪わない言葉で小説を紡いでいる。

彼岸花が咲く島(文春文庫 り 3-1)
定価 792円(税込)
文藝春秋
» この書籍を購入する(Amazonへリンク)
- date
- writer
- staff
- 文=倉本 さおり(書評家)
- category