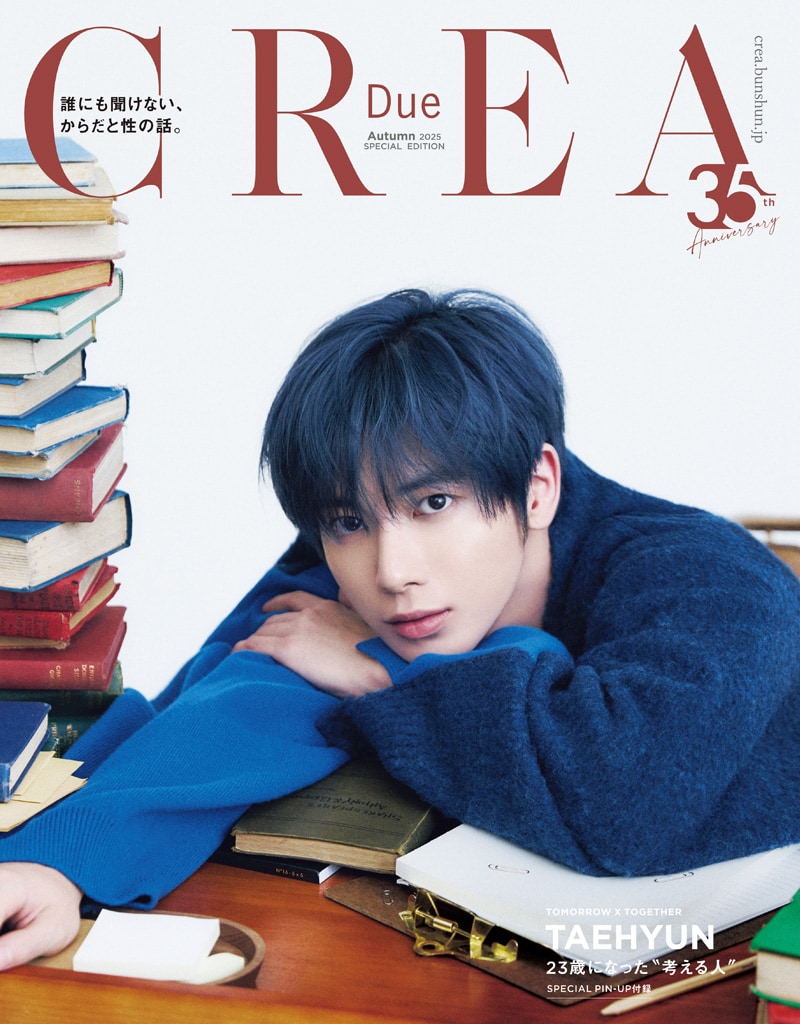そんな弱々しく無力な存在として物語に登場した「少女」こと宇実が、游娜をはじめ〈島〉の人びとと寝食を共にし、働き、祭事に参加し、笑いかわすようになるうちに変容していく。その過程において重要な役割を果たすのが「言葉の習得」というモチーフだ。大ノロが宇実に対してことさら厳しい態度を向けていた理由。それはのちに大ノロ自身の口から、ある重大な秘密と共に明かされることになるのだが、読者の視点からすれば別の解釈も可能だろう。〈島〉に辿りついてしばらくの間、〈ひのもとことば〉でしか話すことのできない宇実は、ここでの日用語である〈ニホン語〉で交わされる会話に参加することができず、游娜や拓慈らが〈女語〉に切り替えてくれるのを待つ場面が多い。だが大ノロとの面談を機に、〈女語〉に加えて〈ニホン語〉も覚えて積極的に用いるようになった宇実は、〈島〉で起こる出来事に対して能動的に関わっていくようになるのだ。
自らで考え、行動し、社会に参加する。言葉はそれらすべての営みの根にあたる。
いうなれば人と人が暮らすこの世界において、言葉とはそのまま力となり得るのだ。
言葉を学び、〈島〉の歴史を知った宇実は、畏れつつも自身が歴史を編む側に立つことを――すなわち自らが生きる世界を自らで担うことを選択する。その姿には「言葉」ないし「言語」というものに対する作家・李琴峰のゆるぎない愛と信頼が刻まれている。
だが綺麗事ばかりが綴られているわけではけっしてない。誰よりも上手に〈女語〉を話すことができるのに、ただ「男」に生まれたというだけでその事実を隠さねばならず、ノロになるための試験を受ける機会も与えられない拓慈は〈島〉の暗部を示唆する存在だろう。なぜノロには女しかなれないのか。なぜ歴史を受け継ぐための言葉である〈女語〉を男が学んではいけないのか。背後には〈島〉の血塗られた経緯があり、まさしくわたしたちが手を染めてきた/見過ごしてきた権力と暴力の轍がある。とはいえ男か女かの二元論に囚われているかぎり天秤が逆の方向に傾くだけで、本当の意味で自由ではいられないことは游娜も宇実もわかっている。わかっているからこそ、この小説は最後まで言葉で問いをまなざし、考えることを促し続ける。
- date
- writer
- staff
- 文=倉本 さおり(書評家)
- category