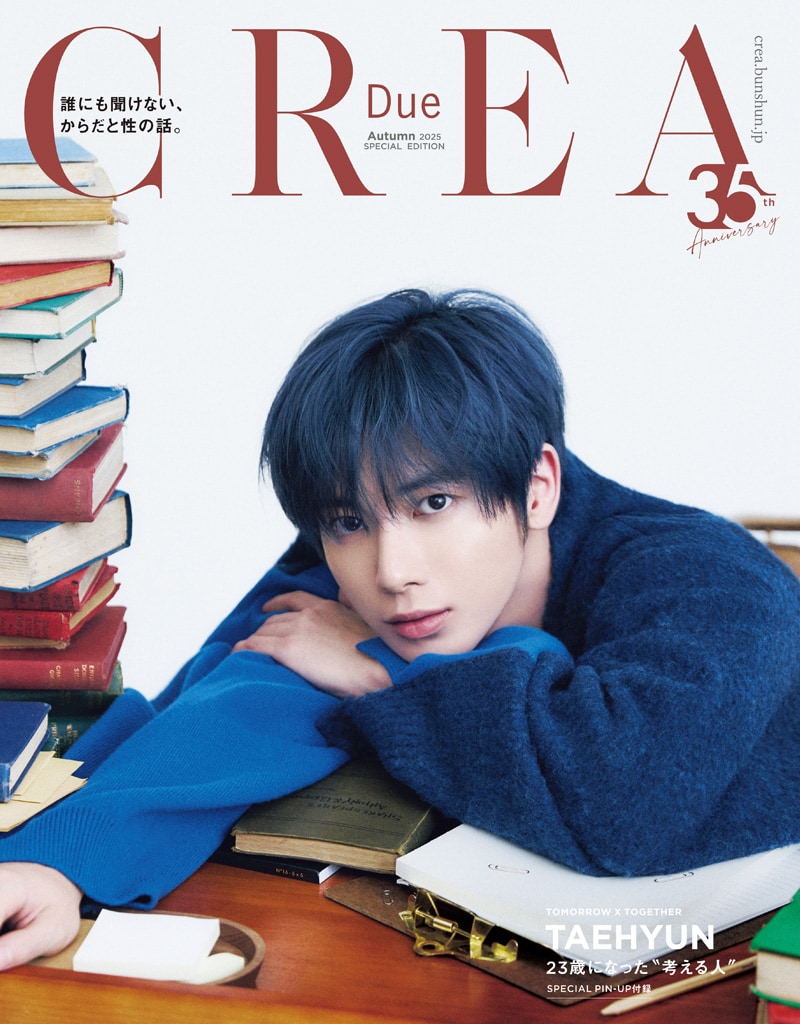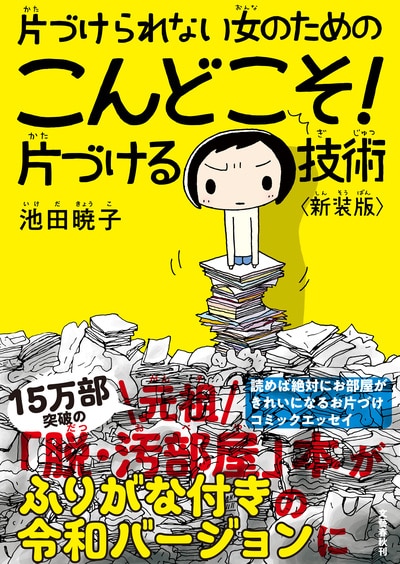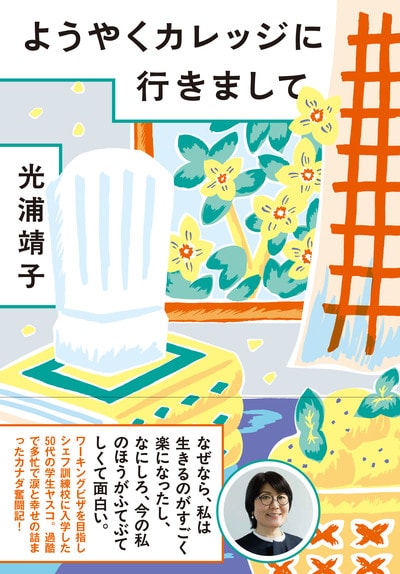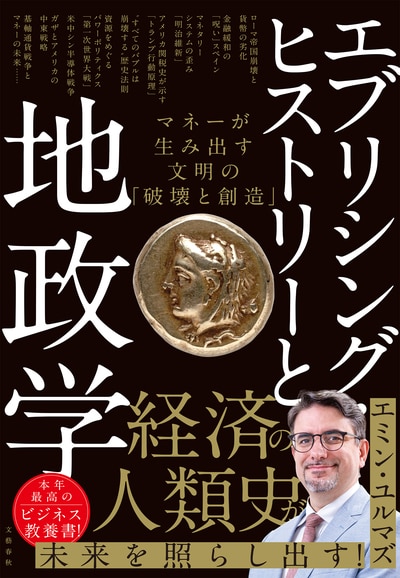タロットカードの彼女
ある日、彼女が午後の食堂で、タロットカードをしないかと言ってきたことがあった。引いてと言われて引いたら、「Feel Safe」と書いてある。曰く、
「あなたが囚われているものは、あなたがつくり出している偶像です。あなたにとっては、とても強く、パワーがあって、支配されていると思っているかもしれませんが、あなたがつくったパワーしか持っていません。あなたはもっと強いものに見守られています。自分自身の大きな未来に見守られています」
そうカードは告げているということで、彼女はわたしに「自分を大切に」と言った。
自分を大切にという言葉ほどむずかしいものはない。人は自分が何を望んでいるのか、本当にはわからないものだし、自分を大切にするという意味を、わたしはいまだによく理解できないでいた。

自分が望むものの形を手に取るようにわかる人がもしいたとしても、それは何らかの外的な要求によって、そう錯覚しているにすぎないのではないか。それに自分が大切にしたいことと、自分の大切な人が大切にしたいものとのあいだで折り合いがつかないこともある。
彼女にとって大切にしたいこととは何か。彼女に「自分を大切に」と言われる意味をかみしめながら、わたしは不吉めいたカードの柄を眺めた。
きっとこの人は、外でも立派に生活できる。なんらかの理由で、家族が彼女に求める生活の質というものに、彼女が到達できないのかもしれない。病というもののなかに家族全員が逃避したことによって、彼女がひとりここにいざるを得ないのかもしれない。それほど彼女との会話のなかに病理は感じなかった。あきらめと、それでもまだ大切な人を信じたいという気持ちの交差が彼女を満たしているように感じられた。
斜め下を向きながら、彼女は自分のなかの深い闇を見つめているようだった。その闇には、自分を病院に入れることを最善と信じて、めったに会いにもこない家族の心ない一言や、解消しきれない不信の場面、さまざまものが去来し、そして沈殿しているのだろう。
◆◆◆
その後、母は意識を取り戻し、自宅介護がはじまった。最初は要介護5がつき、おむつ介助もあった。退院してから、繰り返し同じ言葉を言う「常同行動」がひどく、わたしは“壊れたレコード”と呼んで笑い飛ばしていた。
笑い飛ばすくらいしか、日常生活のなかで異質な動きをする家族を受け入れる術はなかった。さいわい父は底抜けに明るいキャラクターで、ピンクのエプロンをつけてお料理しながら、“ラテン系介護”と自分のことを名づけていた。
家には毎日ヘルパーさんが入り、定期的にケアマネさんの面談を受け、父が休むためにショートステイも数か月おきに利用する。わたしは実家の近くに引っ越して通いながら、家族をもち、子どもを産んで、曲がりなりにも母に子育てを手伝ってもらったりする。
そうしているうちに母は、いまでは要介護2まで奇跡的な復活をとげ、わたしの悩みに適切なアドバイスをくれるようにまでなった。入浴介助のヘルパーさんとはもう十年のつきあいになり、まるで本当の叔母のように感じている。わたしたちは家族だけでなく、たくさんの人の手を借りて、母の彼女なりの自由を保てている。
こうして母と接しているとき、ときおりあの病院の女性たちは、いまもあの場所にいるのだろうかと思い出す。あの静かな連帯と、夜の食堂の窓辺で、自分が流した涙の冷たさを思い出す。

わたしが誰かわからない ヤングケアラーを探す旅 (シリーズ ケアをひらく)
定価 2,200円(税込)
医学書院
» この書籍を購入する(Amazonへリンク)
- date
- staff
- 文=中村佑子
- category