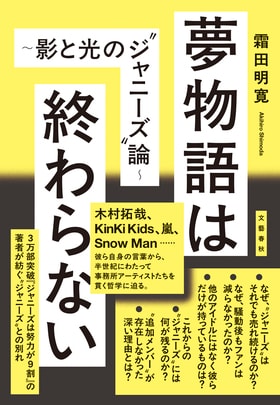外見も才能もそっくりではあったが、倫は昔から、伶よりもおおらかな気質を持っていた。
謂われない罵倒を受けた時、怒りに任せて嫌味を返すのが自分で、「どうしてそのようなことを言うの」と不思議そうに問い返すのが弟だった。
人の明るく優しい部分を形にしたかのような魂を持っていて、そんな倫が奏でる音は、奏者の性質を写し取ったがごとく澄んで、清らかなのだ。
――倫のような音は、自分には出せない。
伶は、肌身離さず懐に持ち歩いている竜笛を、ぎゅっと袷の上から握り締めた。
「梅花の宴は、気分を新たにするのにちょうどいいんじゃないかな」
押し黙る伶を励ますように、倫がわざとらしく明るい声で言う。
中庭には、紅白も鮮やかに咲きほころび、清しい香を放つ梅の木が立ち並んでいる。
それを囲む濡縁や透廊に、二人が緋毛氈を敷いているのは、明日にはここで梅見のための宴が開かれるからだ。
「宴って言っても、どうせ俺達は下働きばかりだろ。多少残飯のおこぼれがあるくらいで、ろくな楽しみなんかないさ」
伶が拗ねた声を出すと、倫は緋毛氈の皺をのばす手を止め、ぱちぱちと目を瞬いた。
「そんなことはないよ。今回はただの宴じゃないんだもの。普段なら、絶対聴けないような秘曲だって聴けるかもしれない」
「秘曲ねえ……」
明日の宴では、東分家の姫がここに集められ、楽人としての腕前を披露させられることになっていた。
将来この山内の地を統べる若宮殿下の后選び、いわゆる登殿の儀がもうすぐ始まる。四大貴族を代表する姫が中央の宮殿に赴き、若宮の寵愛を競うわけであるが、その候補者の選定が行われるのだ。
「楽家の姫と言っても、どれだけの腕があるのかは疑問だな」
どうせ血の濃さで候補を選んでいるんだろうし、と呟くと、倫は苦笑した。
「今の若宮殿下は風流人だから、お館さまは、多少縁遠くても腕のある姫を選ぶおつもりらしいよ。そうでなければ、こんなふうに姫君を比べるなんて真似しないだろ」
2025.01.16(木)